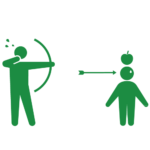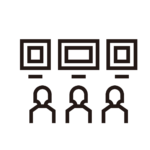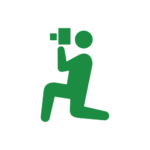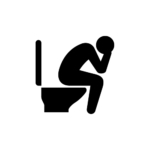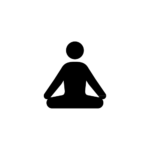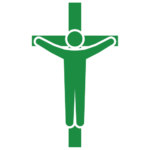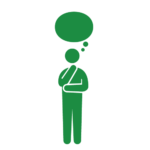「 認知 」 一覧
-

-
少しは自分を疑えよという。 ヒューリスティクス ・まぁ、割と間違えます。脳は元から精度よりも早さという価値観な所がある。ヒューリスティクス(発見的)とも呼ばれる。 結構な知名度となったが「バイアス」ま …
-

-
できる/知っているが言葉にできない知識。言葉にできる知識と反対の存在。「伝えたくても伝えられない」逸話は昔からある。 暗黙知とは 「知っているが言葉にできない知識」を指す。大きく分けて2つの使われ方が …
-

-
先延ばしにせずにさっさと片付けるライフハック:デビッド・アレンの2分ルール
2分ルールとは 5秒ルール同様、先延ばし対策になるルール。 シンプルな、「そのタスクが2分以内に終わるなら、今すぐ片付けろ」というルール。 2分ルールは前提として、そのタスクがやるべきことだと当人が認 …
-

-
2021/02/24 -心理・認知・感情・精神
認知認知バイアスとは 広くは、勘違い、早とちり、思い込みなどの間違いをしている状態を指す。事実と異なる認識。あるいは適切ではない材料に依る推論・結論。「バイアスがかかる」等の使われ方をする。 ここでの認 …
-

-
モノの見方について。視点と視野。 例えば普段は主観的にものを見る。自分の行動が正しいのか客観的に自分を見る。歴史の授業は俯瞰的に見る。の様な形でこれらの言葉は使われる。 この内、客観的と俯瞰的の区別の …
-

-
「みんな」って誰だよこの野郎。とか思うこと一度くらいあるだろう。結構昔からそう思う人は居たようで。 向う三軒両隣にちらちらするただの人 山路を登りながら、こう考えた。智に働けば角が立つ。情に棹させば …
-

-
なんでも「すぐに」自分のせいにする人と、帰属やバイアスについて。 全部自分のせい・自分が悪いと思ってしまう人元記事。 帰属とは、原因や責任の所在を考えること。既に起きたこと(結果)から逆算して原因を見 …
-

-
マインドフルネスは第三世代の認知療法と呼ばれることがある。第一世代、第二世代はなんだったかと、マインドフルネスが第三世代の認知療法であることについて。 わかりやすい仕切りはなく、各世代間で共通したり、 …
-

-
>帰属とは 成功、失敗、問題などに対しての原因として何らかの要素を挙げる心的過程こと。 属性としては能力(自分の先天的な要素)、努力、難易度、運の4つが多い。 なにか失敗した時にそれぞれ、 自分には向 …