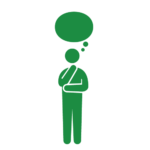・考えない人にも色々ある。
何も考えない人。やらかす。
自分で考えない人。やたらと聞いてくる。鬱陶しい。
「考えがない人」。意味は大きく変わる。自分の意見や方針を持っていないという意味。優柔不断なことが多い。
具体的に考えられない人。実践では学んだことが活かされない。表面的なことしか言えない/わからない。
人のことを考えない人。自分勝手。
要点としては、
①考えの深さ
②予測とその必要性
③独立心や責任感があるか/依存しようとしているか
このあたり。
「何も考えてない人」に見える言動
・自分で自分を「考えてない」と感じるよりも、他人にそう指摘されることの方が多いだろう。言動が、そう見えるということ。
客観的に見た時、対象が「考えない人」に見えるのは、
- 結果を予測しない
- 取りあえず動く
- 人に聞く回数が多い+内容のレベルが低い(当人の能力的にも「ちょっと考えれば分かること」を聞いてくる)
- 自分から動くつもりがない
- 次に何をやるかがわかっていない(段取りを意識していない)
このあたりで、特にこの話が職場で多いのは、それなりに自発的に動いてもらわなきゃ困るからだ。
ゆうても思ったこと口から垂れ流してて「自分は考えがある」とか思ってるのいるし、割と基準は曖昧である。
ただし、任せておいたら期待通りの成果を上げる人間は、間違っても「考えがない」なんて言われないだろうこともまた事実だ。
逆を言えば見ててなんか不安を感じるなら「考えてなさそう」なんて言葉は出てくる。その不安感は心配かもしれないし、「近くにいるとトラブルに巻き込まれそう」という危惧かもしれない。
・「考えない」という言葉は、正確に表現しようとすれば前後に他の言葉がつくことが多い。自分の考えがないだとか、考えないで行動するだとか、考えないですぐ聞いてくるだとか。
実質的にはその言葉が示すのは、態度か行動である。この点が変わらないのなら、いくら本当は頭で考えていてもそう言われ続ける。言う側の決めつけも多い。
何も考えてない人の特徴
・全体を通して物事に対してかなり表面的な解釈をする。それ以上考えない、それ以上は気にしない。済んだら忘れる。先のことを考えてないから覚えるつもり自体がないなど。
わかったふりをする
その場では「わかった」というが、実際にはできない。或いは翌日また同じことを聞く。
思い込みと勘違いでとんでもないことをする
一度「わかった」と思ったら止まらない。その理解が正しいのかどうか、実行したらどうなるかを考えない。
加減を考えない
- 「何を気にしてどこまで考えればいいか」、考えの広さや深さの問題。
- 「やればやるほどいいはずだ」という加減する気ゼロ。
これらは逆に考えすぎ、やりすぎのリスクも高い。
特に2つ目は、周りが止めても止まらないなどもある。
言われたことしかしない/自分からは動かない
・積極性がない。ある意味従順である。最小限しか動くつもりがない場合と、「言われたことしかやってはいけない」と思っている場合がある。
三種類ある。
- 言われたことしかやってはいけないと思っている。
- 何をやったら良いかわからない。
- 失敗したくないのでできる限り動きたくない。
サボりに見られることも多いが、萎縮していることもある。
反応が脊髄反射
・反応自体は素早いが、反射的、衝動的。一言で言えば「わかってなくてもできる応対」が多い。
例えば指示に対して返事だけは早いが、やらない。
謝罪はすぐにするが、その後で同じことをやらかすなど。
最も厄介なのは、わかろうがわかってなかろうが「わかった?」と聞かれれば100%「はい!」と答えるタイプ。
楽観的で無責任
・悪いポジティブシンキング。
「大丈夫だと思った」
「いけると思った」
「なんとかなると思った」
「気をつけてれば大丈夫」
「笑ってるんだから怒ってない」
「何も言われないってことは大丈夫ってこと」
自分のことなのに他人事のような態度
・責任を取りたくない。責任感が元からない。「自分がやらなきゃいけないこと」という自覚がないか、できれば他人に押し付けたい。
一方で、当人よりもやる気を見せる熱血サポーターや鬼コーチ気取りの外野とか居ると、一歩引いてしまう人もいる。
何かを極端に盲信する/何かを頭から否定する
・考えない=騙されやすい+人の話聞かない。盲信しやすい。
何かを頭から否定するのも「これは違う」と何かを盲信している状態に変わりはない。
「頑固であること」は、他を知らないし考えてないだけの可能性もある。自分では「意志が強い」と思っているかも知れないが。
額面通りに受け止める
・或いは「言葉通りに受け止める」。要するにこれは「文脈」という概念がないことを示す。勘違いからの大激怒なども。
「発言の意図」ではなく、「言葉の意味」で解釈する。アスペルガー障害の傾向としてこれがある。
・ただし、緊張が原因でこうなることもある。緊張が過ぎるとフォーカスが「話」レベルから「単語」レベルになってしまいやすい。
「言われたとおりにしなければならない」と構えた上で、指示が(言葉としては)雑だったりだとかもある。一概に性格や能力の話とも言い切れない。
ただしこのせいで、相手の言葉尻を捕らえる、揚げ足取りにしか見えないなど、どの道かなり攻撃的/挑発的な印象を与えやすい。
覚える気がないようにしか見えない
・わかりきったこと、何度も教えたことを、今日もまた聞いてくる。今日で何回目だよとかそんな頻度で。
実際に他人をメモ帳かなんかだと思ってるようなのもいるが(聞いたほうが早いとか言う)、自信がないから「確認」として聞いていることも多い。
・まず聞き方が悪いというのが有る。ゼロから聞くというか、分かってない態度での聞き方をする。聞かれた側は答えるなら長々と喋らなくてはならない。「確認のための質問」には聞こえない聞き方。
次に、自信のなさからくる場合は「分かってるのに聞いてくる」形になる。相手から見ると鬱陶しい。独り立ちできるのにしないわけだから。
どの道、相手からは「一人前になる気がない」ようにしか見えない行動になる。裏を返せばこれは「依存されている」「寄生されている」と思わせる。
何も考えてない人
・殆どの場合、「先のことを全く考えていない」「どうなるか全くわかっていなかった」ということを指す。理由としては予測やシミュレートの不足、または欠如。つまり考える前に動く傾向。
理由は色々考えられる。
- 衝動的であり、考える前に実行に移してしまう
- 知識・経験不足であり、先を読むことができない(この上で行動に移る)
- 考える必要性を感じていない(これは「もうわかっている」という油断を含める)
など。
日本人は遺伝的に悲観主義の傾向があり、これは「悪い結果を予測し対策を立てる」という生真面目さの基盤となっている(防衛的ペシミズム)。要は慎重派が多い。
基本的に慎重/丁寧がベースの価値観があるので、怖いもの知らずで案の定周囲を巻き込んで自爆するような者は、見ていて面白くないという心理はあるだろう。
それこそ自分を巻き込んでトラブルを起こすであろうという「予測」は周りの者は立てられるので、抑止、警戒、あるいは排除の対象にはなり得る。
深く考えない人
・「考えが浅い」なんて言ったりもする。結末まで考えず、途中まで考えて「行けそうだからやってみた」みたいなタイプ。状況次第ではそれほど悪くもない。
・この中には始めから「都合の良い結論」を出すことが目的で考えているタイプが混ざっている。その後のことは考えずに実行する。
「考える」と言っても2つあり、今回は「正しい判断」が求められている事が多い。しかしこのタイプは「やりたいことのシミュレート」を行い、その後のことは考えていない。トラブルになることも。
・「時間割引」という目の前の問題は大きく、将来のことは小さく評価する傾向が人間にはある。これが特に強い場合、目先のことしか考えていない状態になる。
水平線効果
・人工知能の話で、水平線効果というものがある。例えば将棋で10手先までしか先が読めないAIは、「10手までは好調子だが、15手目で必ず負ける」という手を、「良い手」だとして採用してしまう。
水平線の向こう側の様に、先がいきなり全く見えなくなるから水平線効果。「見えている範囲での最良を選ぶ」。
この時問題になるのは、見えているものだけで「全て」として判断すること。知らないこと、見えていないことは存在しないとする、盲目的な考えとなる。この上で、別に「暫定」としては悪くない。適宜修正するのなら。ただし当人は大抵、出した答えにしがみつく。
これにより先のことを考えない/考えが浅いと見られる。「見えていない部分がある」可能性を考えないとこうなるだろう。
・この「水平線」がどこらへんになるかは、結構人によって違う。あまり遠くまで見えないタイプで、さらに間違えるわけには行かないような場面では、用心深くなったほうが良いだろう。
あるいは頻繁に予測をし直すこと。10手先しか見えず、15手先で詰むのなら、5手進んでから改めて予測すれば気付けるし間に合うわけで。
分かる前に動く人/考えるより先に手や口が出る人
・衝動的。考えるより先に動く場合、かなり反射的な言動となる。早さ優先で精度がない。
正しく理解するよりも前に「わかった」として動く可能性もある。結果的に「わかってないのに動く」ことになり、最悪なことになりかねない。
たとえ本来は頭が良くても、最適解を導き出すだけの知識と時間を持っていたとしても、考えが行動に反映されることがない。やらかしたと自覚する頃にはもう手遅れになっている。この場合は頭を使っていなかったとも言え、「考えてない」となる。
これはやらかしたあとでなら自覚できる場合が多い。恥や後悔、周囲のため息に依ってであり、もう遅いが。後で強く後悔する割には、この時に声をかけても聞く耳持たない/止まらないことも多い。
あるいは答えが出る前に行動は終了し、思考は途中で破棄される。失言や早とちり、見切り発車など。
・ミスそのものよりも、やらかした後の「悪あがき」の方が問題になりやすい。理由があったんだ、誰かのせいだ、ちゃんと言ってくれないから、などなど。合理化/正当化しようとする。
面白いことに一部の人間は、バカだと思われるよりはクズだと思われたほうがマシらしい。このためエラー/ミスの自覚があった上で「わざとやった」「わかっててやった」と嘘を付く者もいる。
「簡単だ」と思ったことにもいくらか慎重さを残した方がいい。
実際に何も考えてない人
・口癖が「わからない」「知らない」「覚えてない」。これを即座に口にする。一秒も考えてないように見える。
何も考えてないで行動する人。行動力、自信、やる気「だけ」あるタイプ。最初から行動するつもりがあり、考えるつもりがない。
疑問を持たない
・考える必要性の不足。考える目的や動機がない。
対象を自分には無関係だと思っていれば、それだけで考えは浮かばない。
具体的に考えられない
・具体性の不足。厄介なことに、これでもなんとなくわかった気はしてしまう。実行に於いて困ることになる。
自分で調べない
・「聞いたほうが早い」というのが常套句。
・「話のネタ」として疑問をストックしている場合もある。
メモを取らない
・一度聞けば分かると思っている。
・或いは聞いた時の「わかった」という感覚は錯覚だったり一時的なものだったりすることを知らない。
・またこれは、何度も教えたり質問に答える側の手間を軽視した、身勝手な態度。
早合点
・説明開始数秒で結論を妄想すると、それ以降はただの「消化試合」になる。
適当にコクコク頷いて、相手が話し終わったら「わかりました!」と言って飛び出し、わかってないことをやらかす。
・「わかった」と思ったら誰でもそれ以上はあまり考えないだろう。この「わかった」と思うハードルが異様に低い。
行動の質じゃなくて量でカバーしようとするタイプに多い。要はせっかち。
・後述する失敗恐怖に繋がるが、先延ばしグセ、完璧主義の一部は慌てグセが身についた結果「じっくり/しっかり考える」ことをやらない傾向がある。
これはいくらIQが高かろうが、考える時間があろうが、軽率な結論しか出なくなる。逆を言えば焦れば誰だってこの傾向は強まる。
考えないと何が困るのか
- 騙されやすい
- 共犯者になりやすい
- 警戒される
・自分にとってのまともな判断をしないのだから、事態に対して受身になるしかない。騙されやすい、過剰反応(狂信者)、フェイクニュースの拡散に参加することになる。ネットリンチの加害者などもあり得る。
・大前提として、人間は「わからない」という状態をかなり不快に感じている。通常調べたり考えたりしてその解消を試みるが、それが適わない場合は不快から逃れるために「何かを盲信する」あるいは「それっぽい答えにすぐ飛びつく」という傾向が出てくる。
災害で情報が錯綜していたり情報不足な状況で、専門家は信頼できる情報だけを発信し、自称専門家は憶測を発信するなんて話がある。この時憶測の方もバズりやすい。多くが不安を感じ、その解消となる情報が得られない状態で「飢えていた」から。結果、偽物に飛びつく悪食となる。
・散見される無責任な態度は大きく懸念材料になるだろう。他人からは厄介事を作り、そして押し付けてきそうに見られる。特に仕事上では信頼ができないため、「アイツに頼むより自分でやったほうが安心できる」とはなる。
・意図せずにキングメーカー(後述)になりやすく、これが結構嫌われる。
関連ページ:
深く考えない人と微妙にそれが羨ましい人:防衛的ペシミズムとネガティブ・ケイパビリティ
多くは「答えのでない事態」に耐えられない。結果すぐ動こうとしたり、考えてないようなことをしてしまったりもある。ジョン・キーツは、答えのでない事態に耐える力をネガティブ・ケイパビリティと呼んだ。
何も考えない人はなぜ嫌われるのか
・覚える気がないなら相手にするだけ無駄だ。毎回同じことで聞いてくるのはもう「介護」に近い。
・現実には考えすぎて精神病み気味な人間のほうが多いから、その分正反対すぎて考えない言動は目立つ。
考えることへの苦手意識について
・特定の分野や考えることそのものに苦手意識を持っている場合もある。
人は苦手なことを考えなければならないと思うと脳に「痛み」が走るらしい。数学嫌いが数学の問題に取り組まなくてはならない時、そのような反応を見せるという実験結果がある。
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/434/”]
考えることそれ自体に「痛み」を感じる人間がいたとしたら、考えることそのものを避けるクセは付きかねない。
・救いとしては、この様に痛みを感じる人でも「実際に数学の問題を説いている時は、ほとんど痛みは発生しなかった」ということ。
「想像するだけで嫌だ」ではなくて、「想像が苦痛をもたらしている」のが現実だということ。
裏を返せば「苦手意識」そのものが苦痛の最大の原因であること。
自分で考えない人
・わかりきったことを聞いてくる、自分で考えるべきことを相談してくるなど、独立心が極度に低い印象を受けるタイプ。
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/4409/”]
- 自分のことも決められなくなるし、わからなくなる
- 自分がない分、誰か何かに同調/盲信するようになる。利用されやすいし騙されやすいが、共犯者や実行犯ともなり得る。
- 性格や能力が原因の可能性もあるが、ただの経験不足の可能性も大きいので、まぁたまには自分で考えてみましょう。
自分で考えない、決められない障害 依存性パーソナリティ障害
・パーソナリティ障害には「自分で考えるつもりがない」ものがある。
・依存性パーソナリティ障害は、過度に他者に頼り、依存する。
参照:https://byouki-scope.empower-column02.com/byouki-scope/disease/dependent-personality-disorder/
10代、遅くても成人期早期に症状が始まり、「自分一人では何もできない」と考え、他人に過度に面倒を見てもらおうとする。結果、自分で判断すべきことでも他人に意見を求める。
交友関係は狭く、対象に極度に依存する。仮に相手から虐待を受けても耐える場合が多い。依存対象を失った場合、再び依存先を探す。
人口の約0.7%がこれだとされている。案外多い。
依存先は限定され、誰でもいいわけではないのだが、例えば「職場」という範囲での依存先として上司や同僚が選ばれるなどは珍しくない。学校でも誰かにべったりな子供とかいただろう。仮想的な「親子関係」の子供を演じているように見える。
「考えてはいけない」
・自分で考えない人の中には「指示待ち症候群」と呼ばれる自分で考えて行動ができない人もいる。言われたことしかやらない、或いは応用力がないと評価される人の中にも。この場合依存性パーソナリティ障害とは限らない。
・単純に「考える」というのは一種の自発性だ。
「余計なことはするな」「言われたとおりにやれ」「失敗するな」というのはこれまた単純に「教えた芸をアウトプットしろ」というだけで、元から思考の余地はない。
・「考えろ」って言葉もあんまり考えてない言葉で、判断しろ、理解しろ、気を使え、あるいはいちいち聞いてくるなって意味である余地もあるな。
ただ、こんなブレのある言葉に対して「じゃあ考えなくてはならない」とか「自分は考えがないのか」と素直に思うのなら、従順に過ぎるというのはあるだろう。
暇ならエゴグラムって心理分析をやってみると良い。多分「AC」って要素が高いかもしれない。
・環境的に「自分で考えるべきだ」と思えないような要素、または「勝手なことをやってはいけない」と思うような要素はないだろうか。
正直「考えろ」って言葉は、思い通りにならない奴に言う意味のない言葉でもある。「気が利かない」とかもそうだね。気にしなくていいかも知れない。
「責任を持ちたくない」
・厳密に言えば考えないのではない。行動が正解である保証、あるいは失敗した時の保険を欲しがる。
・失敗したら人のせいにするとか、人の「手伝い」じゃないと動けないだとか。自分のことほったらかしてまで人の手伝いしようとするのも居る。
一長一短で、じゃあ逆に自信満々の無能とか想像してみれば、おとなしいほうがまだマシなわけで。
「責任を持ちたくない」というのも、ある意味責任感が強いから(=自分が責任を取らなきゃいけないと思っているから)、「自分にはこの責任はとても持てない」と判断していることもある。考えすぎて動けないような状態。
「失敗したくない」
・これも厳密に言えば考えないのではない。「自発的な行動をしない」=考えないように見える。緊張や過度の失敗恐怖などで一時的になり得る。
・精度や成功率をあげようとした場合、何度も確認するというのは不思議ではないだろう。確認手段の1つとして「人に聞く」はある。
・特に人に聞かないと不安だという気持ちと、そこから来る思いついた事を片っ端から聞いてくるという行動になりやすい。
聞いた上でもやっぱり動けなかったりもする。そうなるとまた聞いたり確認したり。
・特に「アタリマエのことを聞く」というのはかなりディスコミュニケーションになりやすい。例えば「自分には思いつかない見落としはないか」と確認したくて聞く場合もある。これは姿勢としては評価されてもいいくらいだろう。頻度で台無しになってるのかもしれないが。
しかし聞かれる側としてみれば、まぁ初手では「わからないから聞いてくる」というのが先に頭に浮かぶし、うんざりするのも確かだったりする。この辺りは聞く前の前置き程度でクリアできることがある。それこそストレートに「見落としがないか話を聞いてもらいたい」とでも言えばいい。
聞き手のストレスとしてよくあるのが、「何の話かすぐにわからない話し方」とか「こちらの取るべき姿勢がわからない」とかだ。その辺りをクリアすれば案外スムーズ。話す始めに「相談です」とか「確認です」とか言いましょう。
言われたことだけやるのは何が悪いか
・一部は「言われたとおりにしたのに何が悪いのか」と不思議に思う人もいる。逆を言えば言われたとおりのことだけをやるのが「正しい」という認識を持っている人はいる。
これは実際「余計なことするな」と言っておきながら「自分から動け」と怒るような奴もいるため、誰が悪いんだか断言できないことが多い。言われたことしかやってはいけない業種なども確かにある。
言葉だと「加減」がほぼ伝わらないのも原因の一つだろう。
・また、この上でも自分から動かないことは正解かもしれない。「無能でやる気がある奴は撃ち殺すしかない」とネットミームで言われるほどには、行動力しか無いことは面倒事を生み出す。
・何が悪いかって話だが、単純に他人が其の者をいちいち「操作」しないといけないからだ。操縦者は自分の仕事が犠牲になる。仕事だったら雇った意味がほとんどない。
・あと盲点になりがちだが、「短期的な」言われたことしかほぼやっていない事が多い。
「今日は/今から」+「これをやれ」には対応できるが、昨日教えたことは今日は無関係であるかのような反応を見せることは多い。
「言われたことしかやらない」というよりは「言われてから動く」という行動パターン。だから次の日も言われてからじゃないと動かない。
これは自分の「役割」を持たない、身軽な「お手伝い」の立ち位置といえる。実際には既に担当業務があるのなら、これはよろしくない。このあたりの縄張りをはっきりさせない会社も多いけど。
他人事に対して、出しゃばらないようにしていた場合には正しいあり方だろう。既に役割が与えられているのなら、「無責任な態度」になる。
・わかりやすく「自分からやるべきこと」として明示してやればいいじゃないかと思うが。文句言う側はあまりやらないね、特に口伝で教えるような所は。
いちいち他人が気が利くかどうかを試してるというか、気を利かせてくるのを待ってるようなのもいるしな。この「頻繁な試し行動」は、する側の人格に問題が有るケースも有る。まぁ、やめれるならやめたほうがよろしかろう。
・自分で判断できない、考えてもわからない。或いは自分でそう思っているから初めから考えない。そうなると「人に言われたとおりに動こう」というのは妥当な計算結果ではあるだろう。
状況判断が正しければそれが正解になる。逆に間違いだとされるならば、状況判断が間違っているかもしれない。既に責任はあるかもしれないし、周りは当人が自分でやるべきことだと思っているかもしれない。
・単純に材料不足の場合もある。ボーッとしてたら考えを言うように言われ、そこから考えればまぁ的外れなことが出てくるか、何も考えられないかだろうし。
考え始めるのが遅い
・それが自分に関係ある話だと分かるのが遅れれば、それだけ不十分な思考となる。
「言われてから動かなきゃいけない」と思っている場合、大抵は状況把握の段階で出遅れる。
・考えを示すのは、発言か、行動かになる。頭の中で何を練り上げていたところで他人には知覚できない。逆を言えば、発言や行動が遅れる、あるいは「動かない」という時点で、考えがないとは思われる。
キングメーカー
・kingmaker. 王を創る者。当人は表にでないが、裏方で大きな影響力を与える者。
ゲームではこれは「自分は勝てないが誰を勝者にするか決めることができる者」を指す。
例えば七並べでもやっていて、自分はもう絶対に勝てないが、2を出せば左の奴が勝ち、Qを出せば右の奴が勝つというような状態。
ゲームの勝敗は当人の運や実力に帰属されるべきであり、他人が全て決めてしまうキングメーカーの存在は「興を削ぐ」とされている。
・例えば2つの派閥が対立している状態で考えがない=意見を持っていないというのは、他者から見れば敵にも味方にもなりうるということでもある。
その対立が拮抗状態なら意見がないというそれだけでキングメーカーになってしまう。望んでその立場になりたがるのもいるにはいるが。
もしも望みが「厄介事に巻き込まれたくない」という場合にも、最終的にどちらかに決めるつもりがあるのか、それとも関わりたくないのかくらいは考えておいたほうがいいだろう。じゃないと勝手に注目が集まり、余計に巻き込まれる。
興味がないのにスタンスを考えておかなくてはならないという、社会的な面倒くささが詰まった話である。
考えがない人
・考える方針がないから考えが出てこない。考えなきゃいけない理由や目的がない。
・その案件に対して、共感や感情移入をしていない。しなきゃいけないわけでもないが、その状態は完全に受け身なため、考えは出てこない。
端的に言えば対象に介入や干渉する意思がない。深入りしたくない、関わりたくないと思っているとこうなりやすい。
「関わりたくない」というのも意見だし別にいいと思うが、万事にそうだとしたら淡白な性格か、脳が疲れた状態か。
・何か突発的な、難易度の高い仕事が舞い込んだとしよう。活躍したきゃ飛びつく。サボりたきゃ逃げる。スタンスが何もなければ、棒立ちだ。
これは対応の指針がないことを示す。指針は目的、悪い言い方をすればエゴであり、欲でもある。
出世欲があるなら活躍しよう、目立とうとするだろう。自然とそのための手段は考える。
或いはサボりたいなら楽をしよう、目立たないようにしようとするだろう。自然とそのための手段は考える。
・「考える」という言葉は能動的/意識的な印象をもたせるが、実際には勝手に頭に浮かぶ物がスタート地点であることは多い。
頭になにか浮かぶには状況の把握の他に「それに対して自分はどうあるか」のスタンス、一種のエゴが必要になる。
関連:
自分の意見が思いつかない人
具体的に考えられない人
・考えに具体性がない場合、言ってることは理想論、やってることは泥まみれになる。
思考に実行難易度や共感などは加味されず「AならばBするべき」と言いやすい。
・これは案件にかなり影響を受ける。通常、知ってることなら具体的に考えられるが、知らないことなら考えられない。その前後、因果関係、動機、理由も予測できない。
例えば自称貧困で生活苦の者の出費一覧を見て、食費が多いというケース。内訳は外食やコンビニ弁当。割とあるが、これに対して「自炊しろ」という声は案の定多い。もやしで一ヶ月しのいだ武勇伝とか語り始める奴とか出たりしてな。
で、私も後から知ったんだが、家に冷蔵庫がそもそもない。電気止まってる。ガス止まってる。と、そういうレベルもあるそうだ。つまり自炊ができない。もやしに火を通すことすらできない。
街中でキャンプカレー作るわけにもいかないだろう。できても多分余計にコストかかる。地区によっては焚き火の時点で通報される。外食したくてしてるんじゃなくて、他に選択肢がない。
で、相手がその状況かもしれないと思ったら、「自炊しろ」と気軽に言えるかどうかという話。
・人間、知らないものに対しては結構、薄情だったり冷酷な意見が出たりする事が多い。意見としてはサイコパスやアスペルガーと同レベルになる。具体的に考えないのは、こう言った意見を連発することになる。
私が彼らの問題が一般の人間に十分当てはまると思うのは(そして大抵の人間が彼らの特徴を見て自分は/アイツはもしかしたらそうかも知れないと思うのは)、瞬間的に似たような状態になり、似たようなことやってるからだ。
ちなみに敵意や軽蔑で共感能力や理解しようとする動機は減衰する。「自炊しろ」ってのも相手を「そんなことも自力で思いつかないバカ」として扱っているアドバイスであり、同レベルの人間がそれでも困っているという視点ではないだろう。動機がどうあれ、発言内容はそういうことになる。つまり人は簡単に人をバカだと思うくらいにはアレなのが一般的と言える。
具体的に考えない場合、分かる前に切り捨てる形にほぼなる。意図せずにやるにはデメリットが大きい。
・裏を返せばこの状況で自分の考えがないというのなら、少なくとも悪いことは言わずに済むのだから良いことなのでは。別に無理してコメントする必要もない、というか喋る機会を積極的に伺ってるタイプは大抵失言が多いし。
あるいは「自炊すればいいのに」と思いつつも、「そうしないのは何か理由があるのか」と疑問につながるなら、それは自分で考えていると言える。たとえそれで結論がでなくても、そっちの方が共感的ではあるだろう。
重要なことだが、「考える」といっても「気づき」がまず必要なことはあるし、「知識」がなければ正解に至らないことも多い。
人のことを考えない人
・これは大抵、人に迷惑をかけた時の言葉。
自分のことを分かってもらいたい人が、他人にこう言ってケチつけることもある。実際に人のことを考えない人もいるにはいる。
・悪意や傲慢さがあるなら普通に人格障害かなんかとみなして絶縁すればいいが、それ以外の可能性について。これは予測が不足しているタイプだろう。
例えば後片付けしない人。共有物を私物のように扱い、共同スペースを私室のように散らかすが、後で他人が不快な思いをしたり面倒をかけるという考えがないと言える。
基本これは「そこまで考えていない」というタイプで、自分勝手だとよく言われる。言動からしたら自分勝手なのは間違いない。
「人に迷惑がかかるとわかってたら同じことをやるか」と聞けば「やらない」と答える。まぁこれを信じるなら、予測不足。不足というか一切してないようにも見える。わざとなら人間関係の問題。人間関係の問題も多そうだけど。
ただし、迷惑かけられた側は高確率でわざとにしか見えない。普通は学習するので同じことは起きないか、少なくとも軽微で済むだろうし。
「考えない」と言う人
・その「考えない人」とやらに過度な要求や期待をしている場合、相手に問題なくても上記諸々に当てはまる考えない人に見えてくる。
要するに文句言ってる側がおかしい可能性もある。
こちらはこちらでかなり多い。「お気持ちヤクザ」とか「繊細チンピラ」とか「モンスタークレーマー」とかそういうの。
・誇大型を含む過敏型自己愛。或いは「自己愛的な甘え」と呼ばれるもの。甘えなので直接的に要求することができないため、間接的に相手が自分の予測/期待どおりに動くように無意識に仕向ける。大体こちらのほうが鼻に付く。
特に指摘が「自分に気を使っていない」ことに帰属するなら可能性は上がる。
他者への操作性、支配性など。人格障害は大体これが強い。例外もあるが。
・一部は「考える人」を嫌う。というか自分の意見を持っている人を嫌う。従順で、自分のミスや薄っぺらさに気づかないでくれるニブさを持っている相手を喜ぶ。
そのくせに「お前は考えてない」「お前は考えが浅い」と平気で言う人間は、まぁそこら中に居る。
考えるには・考えさせるには
・動機、方針、材料が必要になる。これまで述べてきたが「考える」という言葉は意味を多く持つ。方針は特に重要だということ。
予測するのか、自分の意見を作るのか、仮説をたてるのか、計算するのか。
大抵の場合思考能力そのものはある。機会がないだけで。また、同じパターンの思考は次からは早くなる。判断が早すぎると早とちりとなるが。
喋れ・喋らせろ
そもそも自主性がないタイプの「自分で考えない人」の日常を見てみると、相手が一方的に喋り当人は一方的に聞いている構図が多い。学校の授業か。
実際に意見を求められた際のリアクションが「ぼーっと授業聞いてて急に指されて話聞いてなかったやべぇ」とかそういう顔してるの多い。
喋ってないと当事者意識の欠如につながる。というのもあるが、そもそも他人の話を聞くことができる集中力が70秒前後だという話もある。それ以上「待ち」の時間が長ければその分話しも頭に入らないし、その分考えも出てこない。
・ちなみにどの学習法が効率がいいかの図である「ラーニングピラミッド」によると、「講義」の学習定着率が5%とダントツでカスだ。一方で「他者と議論する(ディスカッションやディベート)」は50%。10倍。
これはそのまま「黙って聞いている」「自分でも少しは喋る」との対比だろう。
ちなみに「他人に教える」のは90%。もう一度言うが講義は5%。一方的に教える行為は教える側のためにしかなってないかもね。
授業でもトークでも観客というか聞き手を巻き込む手法があるだろう。馬鹿でもわかるような質問を投げかけて、答えを得て、その答えを引き継いで話を続けるという予定調和的質問が。
聞き手からするとうざいんだが(人は基本、馬鹿でもわかる質問を投げかけられるとムカつく)、あれをやると「質問される」ことが前提となって聞くから、少なくとも話にはついてくるようにさせることができる。逆にやらないと居眠りされるね。一対一なら、相手の意見を聞いたり、ついてこれてるか当人に「まとめ」を言わせたりとか、まぁ色々できる。
なお、勝手に長い話初めた上でこれをやられると腹が立つので注意。元からうざいんだし。
後単純な、本能的な話だが、片方が一方的に喋り片方が一方的に聞いているというのは、心理的に一種の優勢劣勢や上下関係として認知する。やりたい放題のやつと我慢してるやつの構図。そのくらい黙って人の話聞いてるのは結構不自然なものだ。本能的には。
これだと「やり過ごす」姿勢になる。話が終わるのを待っているだけの状態になる。意味理解よりも聞いてるふりの方にウェイトが傾く。適度に相手にも喋らせる「会話」の体裁を意識したほうがいい。
シミュレート
・「考える」という言葉が示す思考活動には種類ある。計算だったり、分類だったり。推測や予測だったり。
・例えば火薬庫で火遊びしてて「どうなるかくらい考えろ」と怒られたとしたら、これはシミュレートを求めらているということだ。つまり「予測」。
予測をしたところで楽観的だった場合はおめでたいことになり、考えない人になる。「大丈夫だと思った」と事情聴取で述べることになるだろう。
こういった性格的特性が原因の場合、考えても無駄だったりする。当人にとっては現実的なのは「何も起こらない」ことである場合は、考えの問題よりも認知の問題になってくる。
・ともかく、「どうなるか少しは考えろ」と言われる場合、この「予測」の量か質に問題が有るだろう。少なくともそう言った相手から見るとだが。
・ゴール設定が重要になる。というかゴール設定が間違っていることが多い。前述の悪気なく片付けない身勝手な人を例にあげれば、道具が用済みになればもう用はなく、関心がなくなっている。
言い方を変えれば、「使うことしか考えていない」。次に使う人が困るとか、文句言われるとかは、片付けていないその道具を見てももう思わない。
思考の素のゴール設定を近場にする癖がある。深読みが苦手なタイプ。これが危険なのは、人はゴール到達時点で分かったとか、できるとか、終わったとか、そう思っちゃうことだ。時にはゴール前にこうなる。
この手のうっかりミスを連発するタイプは、片付けたらおしまい、みたいに自分に言い聞かせるしか無いだろう。帰るまでが遠足。
過学習に注意
・「頭が固い」系の考えない人。
・人工知能の学習における問題に「過学習」がある。オーバートレーニングとか過剰適合とも言う。
人工知能に同じ問題ばかりやらせすぎて、その問題に適応しすぎて、他の問題に応用が効かなくなる現象。
少しでも学習内容と違うと誤った答えをだすようになる。つまり未知の問題に大して融通がきかなくなる。適応能力の低下。
・人間でもたまにいる。同じ模擬試験やり過ぎて少し言い方や表現が違うだけで全くわからなくなる奴とか。
・これを防ぐための方法が、
1:「学習データ」のバリエーションを増やす
2:学習した内容のいくらかを無効にする
などがある。どちらも「柔軟性」を持たせるためなのがわかる。AIですら柔軟性がないといけない。人間なら尚更だろう。
・反対に辞書が正義、Wikipediaが正義、それ以外は間違いってのも問題としては似たようなものだ。この場合は学習量が少なすぎて相対的にその情報の優位性が高い。状態としては過学習に似ている。ひな鳥の「刷り込み」の方がもっと似ているが。
まぁそれで「わかった」って思ってるんだからこちらのほうが駄目だが。
「わかってない」と言われた
・或いは相手の話をちゃんと聞けない、聞いたつもりでわかったと思ったのに理解できなかった場合。
・「文脈」を気にしたほうがいいだろう。「コンテクスト」とも言う。脈絡、前後関係。或いは状況、環境という意味もある。割とあちこちで使われるが、今回は特に言葉のつながり、言葉同士の関連性、言葉の前後、全体像、背景。
・例えばこのページで「考えない人」と言っても色々あることも、言ってる側が問題ある可能性も説明してきた。これはこのページの文脈だと思えばいい。衝動的な人のことかもしれないし、考えてはいけないと思っている人かもしれない。
別の場所で単に「考えない人」と言ったら大体「トラブルメーカーのアホ」を指す。このページを読んだ上で、こちら側の意味に捉えるなら、まぁ読んだ意味ないね。これが言葉通りに捉えるということだ。
・大体このパターンは単語単位で聞いているか、相手の話の中から「要点」だけを狙い撃ちでピックアップするつもりで聞いている。平たく言うと話をものすごく省略する。原型とどめていないくらい。
これをやると色々すっぽ抜ける。「やること」だけを聞いて飛び出す、というのも文脈は初めから読む気はない。
結果的に相手の話を「辞書に載ってる意味」としてしか理解できないか、思い込み、決めつけが激しいことになる。言葉、文字、単語だけに対しての過剰反応。
・SNSによく見る「言葉狩り」も大体これだ。ツイッターはシステム上、前後の文脈を切り取られやすい上に拡散しやすいから尚更。
- この場面で●●という言葉は不適切だ
- ●●という言葉は悪い
- ●●という言葉を使ってはならない
1をみて2の解釈をする者、2を見て3の解釈をする者という形で「考えない人」がすごい数居る。悪目立ちしているだけだと思いたいが。
まぁSNSは知性よりもスルースキルの方が有効。
・皮肉なことに、「しっかり聞こう」と力むと「言葉だけ」に注意が向くことになる。結果文脈はわからなくなる。顔を近づけすぎて全体が見れなくなってるようなもの。群盲象を評す、みたいな。
自分で考えてみる
・ベタだが、必要だ。忠告しておくが、「自分の頭で考える」のは「頭がいい」とは別の話だ。
なんか「頭いいこと思いつかなきゃならない/言わなきゃならない」と勝手にハードル上げてるのが居る。
それ自体は別にいいんだが、その結論が「できそうもないから考えない」じゃ意味がないだろう。
あと、でてきた答えは基本役に立たない。習作だと思っておいたほうが良い。新説や珍説を作るためではなく、理解のための消化作業に近い。
・要点は「自分の頭で考えたかどうか」だけだ。別にそこら中に転がっているありふれた一般論が結論だとしても全く構わない。
それに対してなんとなく知っている奴とは違い、理解は深まるだろう。
これは習熟すれば「正当の出し方をトレースできる」ということになる。
・トレーニングだと思えばいい。ジョギングはスタート地点から折り返し地点に行き、またスタート地点まで走って戻るわけだが、無駄ではないだろう。
これが思考だとケチになるというか、なんか成果物求める傾向は高いね。
・結論が出るならなお良い。完走したということだ。
質は問わなくていいだろう。個人的に考え、というか「意見」というモノは、拡張性やら柔軟性やらがないなら窒息死すると思っている。
あくまでも「その思考の結論」であり、その答えが何かを決定的に左右するということはない。自分で考えて結論を出したという実績が身につくだけだ。
なお、情報不足で自分で考える+その結論を真実だと思い込み執着する場合、ほぼ陰謀論者のようなめんどくさいことになる。
逆を言えば、情報を十分に集め(広く、多角的に)、なおかつ結論を個人的な思考の成果物や「暫定」だと心得る場合、考えない人だと言われることはないだろう。