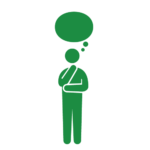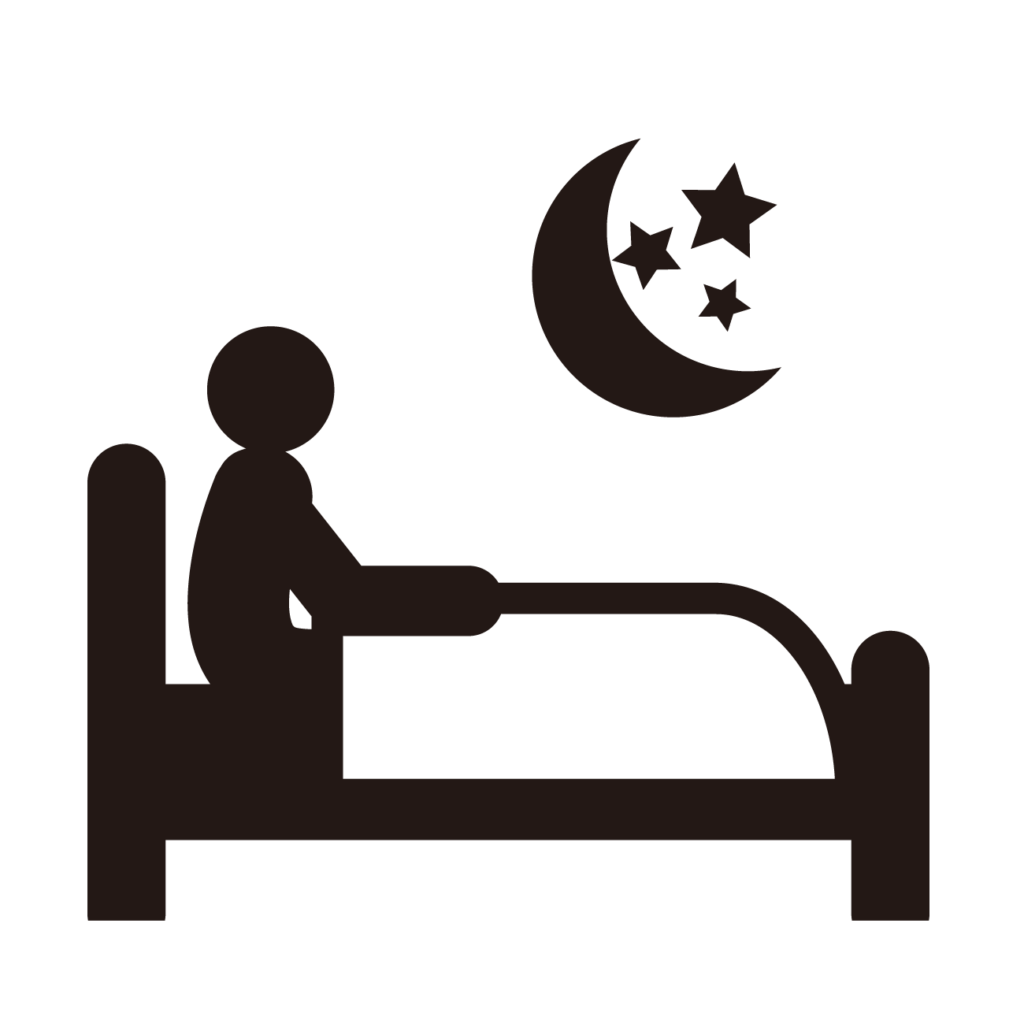
2つに分ける。
1:「明日が来る」のが怖い人
2:「今日が終わる」のが怖い人
「今」に未練があり、寝たくないのは同じ。
どちらも結論から言うと、「気持ちはわかるが、寝ないことは全くの逆効果になるから寝ろ」となる。
明日が来るのが怖い人
・寝たくないのではなく、明日になってほしくない。就寝は「明日になること」と近い意味を持つため、無理して起きてる場合がある。
・明日の予定に特別に何かあるのではなく、「日常」に対して嫌悪感がある場合も。時に「繰り返し」そのものが、嫌悪感を抱く対象にもなる。「つまらなすぎて辛い」ことも。虚無。
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/1784/”]
ドフトエフスキーの考える究極の拷問は、「意味もなく半日かけて穴を掘らせ、半日かけてそれを埋めさせる」ことだそうな。「無意味」とは苦痛であり、日常を「無意味な繰り返し」と認知するなら毎日が辛くなるだろう。逆に意味を持たせることは充実感につながる。
寝る時に明日のことを考えてしまう
・明日への不安は、人間関係が原因の場合も多い。「明日会うだろう人」が嫌。嫌な上司、嫌な教師、嫌なクラスメイト。家族って可能性もある。
嫌な奴が消えてなくなることも滅多に無いので、人間関係の悩みは「解決しない耐え続けなければならないストレス」と捉えられやすい。つまり環境要因に近い形になる。それが明日、また初めから。
・日中の活動に辛さを感じている場合もある。労働環境がブラックなケースがわかりやすいか。今回の「明日が嫌で寝たくない」というのも、大体は職場を指していることは多い。
中には明確に会社に行きたくなくて夜から眠れないと自覚している例もある。この場合でも「仕事内容」ではなくて「環境」の問題が多い。同じ業種でも職場次第で天国と地獄は分かれるって話もザラにある。
・翌日が休日や祝日の場合のみ、このページのアクセス数だけが半減する。これも「日常の何か」が問題であって、時間が進むことが問題ではないタイプが多い証拠だろう。
休日の夜はアクセスが一番多い。明日平日だから。毎週このパターン。
・「日常」に感じる不快や疑念は、次第に麻痺していくことがある。「慣れる」ではなく「麻痺」。感情鈍麻などと呼ばれる。
日常となってしまい異常とも思わないし危機感も感じない。ただしストレスは溜まる。ビジネス都市伝説で言うところの「茹でガエル」と呼ばれる状態になる。[efn_note] 水を張った鍋にカエルを入れて徐々に温度を上げると、逃げようとしないで茹だって死ぬという例え話。なお実際には普通に逃げるそうな。 [/efn_note]
この透明なストレスは、何か致命的なことになるまで自覚されないこともある。ある日突然会社に行けなくなったなんてことはある。
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/2314/”]
今日が終わることが怖い人
・「今日がこのままで終わることが惜しい」から寝たくない人も結構いるようだ。今日一日に対して不完全燃焼の感覚や焦るような気持ちがあり、それを抱えたまま大人しく寝る気にはなれない。
後述するが、時間不安という心理がある。時間が流れることに対しての不安・恐怖。
もっと意義がある何かができたはず、今ならまだ充実した一日にできるかも、こうしている間にも他の奴らは先に進んでいる、今のうちに差をつけないと、などなど。
このような思いがある場合、眠りにつくことは機会損失になるようなことを自ら行うことになる。
カネをドブに捨てれるか、と問えば大抵の人間はできない。人によっては「活動時間」を「睡眠に使えるか」はそれと同じ気持ちになる。
・ストレートに「まだ寝たくない」、「もったいない」という気持ちになりやすい。リベンジ夜ふかし/報復性夜ふかしと呼ばれる、つまらなかった今日への憂さ晴らし的に夜ふかしする心理に近い。
リベンジ夜更かしは他にも「今(夜、一人の時間)が自由で快適だから」という理由が大きい。
不自由な社会的活動、あるいは家族や集団の構成員などの社会的役割から開放される時間を自分から手放したくない。風呂やコタツから出たくないのと同じ心境。別に日常が破綻しない限りは悪いことでもないだろう。
[blogcard url=”embryo-nemo.com/1919/”]
ただ、明日のことを考えるのは、今はやめた方がいい。
相対的に衆人環視に囲まれた不自由な状況だろう明日は最悪になる。そして人間は「比較」によってその価値を決める傾向がかなり強い。
どれくらいかと言えば、嫌いなことをもっと嫌いなことと比べると、比べる前よりやる気がでるくらい。つまり、人が絶対的な評価基準を持ち合わせていない可能性がある。この場合、比較対象次第で評価が全く変わる。
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/4067/”]
眠い時に寝ないとどうなるか?
・睡眠不足はまぁ、色々とよろしくない。
- 疲れが取れない
- 代謝が悪くなり肥満の原因に
- 血糖値や血圧が乱れ生活習慣病のリスクを上げる
- 脳疲労が取れないためミスが増える
・脳疲労についてちょっとだけ追記。
昔は脳は疲れないなんて意見もあったが、バッチリ疲労物質が溜まってるのが観測されたので[efn_note] cf.https://karapaia.com/archives/52315176.html [/efn_note]脳は使えば疲れると思って良い。
先に言っておくが、何もしてない時の方が脳は働いている。余計疲れる。集中している時の方がむしろ静かだ。このため「ぼんやりした頭でなんとなく寝たくないからやること無いのに起きてる」と悪循環。
・疲労物質が溜まる場所が意思決定や集中に関わる場所のため、判断ミスからヒューマンエラーまであらゆる失敗の確率を上げる。
・判断能力が低下するために衝動性が増す。「すぐ満足できる楽なこと」に流されやすく、後で後悔する。
意思決定が遅れることもある。特に「やる」という決断ができない=「先延ばし」は増える。
加えてリベンジ夜更かしは「寝ることの先延ばし」「寝る決断ができない状態」とも呼ばれる。
つまり、「寝たくない」という気持ち自体が、脳疲労による決断力の不足の状態かもしれない。
トドメとして、脳疲労を回復させるには休憩か睡眠しかないと、現状ではされている。
・つまり寝ないと、明日はもっと思い通りにならなくなる可能性がかなり高い。ついでに明日はもっと寝たくなくなる可能性もそれなりにある。
先延ばしもまた悪循環する余地がある。先延ばしからの失敗→苦手意識が強くなりまた先延ばす、という負の連鎖。
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/3283/”]
どうしたら寝ようと思えるか
・思えなくていいから眠気があるなら寝ろっつの。
・真面目な話、その寝たくない気分が睡眠不足のせいかもしれない。前述の通りの「負の連鎖」、夜更かしすれば翌日が思うようにならず、ミスや不満足によりその夜は「明日が怖い/今日が不満足」となって尚更に寝たくなくなる可能性は高い。
・どちらかといえば気分じゃなくて行動(寝る)で解決する話で。行動ができないのも意志力なんていう汗臭いものじゃなくて脳疲労の可能性が高い。
この状態で元から眠ることに「時間を失う」イメージを持っているなら、「寝ないで済むこと」をし続けることになる。
最悪の場合「寝る気分になれる方法」を「寝ないで済むから」という理由でやることになるだろう。
明日が怖いと思う心理
「時間が流れること」自体に不安を感じることがある:時間不安
・睡眠ではなく「就寝」の場合、明日を迎えるとの意味を含める。これは「今日が終わる」ことと同じ意味を持つ。
「今日」にやり残しや未練、不満があり、それが未消化のまま、別の一日が始まることに対しての「何か間違っている/見落としている」感覚。
・心理学で「時間不安」という概念が有る。時間がない、時間が迫っている、時間に追われている、時間が足りないなど、時間に対して感じる焦りと不安。
時間不安が強いと常に焦りを感じるし、神経質な生活態度になる。寝たくはなくなるだろう。
・時間不安には3因子が見いだされているが、今回の話と重複する点が多い。
・第一因子 経過意識
- このまま年をとっていくのか
- 自分の人生が過ぎるのが早い
- 時間が過ぎるともう戻れないのではないか
- 休日を過ごしていてすぐ終わる感じがする
- 休日の夜、明日から学校だと思った時
- 過去を振り返ってみた時
第一因子は時間が流れていくことへの恐怖。寝れば翌朝になっている「就寝」というイベントは嫌だろう。
・第二因子 予期懸念
- これから嫌なことに立ち向かわなければならない
- 周りに取り残されているように感じる
- 授業などで自分が発表する順番を待っている時
第二因子はこれから嫌なことがある場合の予期。
後述するが、脳は嫌なことを想像している時の方が、本番よりも苦痛のシグナルを発している。本番よりも怖れ、緊張するため寝るのは難しい。
「その時」が実際に近づくから寝る=時間を送りたくもない。
・第三因子 目的未達成
- やらなくてはならないことがまだ手つかずで、何もできずに一日過ごしてしまった
- 予定をうまくこなせていない
- 課題の締切が迫っているのに、それがまだ完成していない
- 試験があるのに勉強していない
第三因子は、やり残したことがある感覚。「寝るのがもったいない」または「寝る訳にはいかない」という感情に近い。まだ何もできていない、やらなきゃいけないことがある、まだ満足していないという気持ち。
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/388/”]
・これら一つが原因とは限らず、複数かもしれない。このような気持ちを抱えたままで「今日を終える」行為である就寝は、やはり難しくなる。全てが「寝たくない」という気持ちを発生させる余地はある。
時間不安から見れば、眠ることが「猶予期間や自由時間である時間の喪失」を連想させるには十分だろう。しかし実際の所は寝ないと翌日が更にグダグダになるので、感情が間違っているとも言える。
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/3692/”]
ブルーマンデー症候群
・日曜の夕方あたりに明日のことを考えて憂鬱になること。サザエさん症候群とも呼ばれる。
この概念を知らない人でも「ちょうどサザエさんが始まる頃に明日のことが気になって嫌になる」と言う人は多い。恐らくちょうど日暮れの頃だからだろう。
休日が終わり平日になることへの憂鬱。こちらも自由の終焉であり、不自由の始まりを予感している。
就寝=プラベートな活動時間が終わり、また平日という社会的な時間が来る、と差し替えると、今回にも該当する。毎日がブルーマンデー。
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/2384/”]
この後で嫌なことがあると思うと脳は痛みのシグナルを発する
・「後のことを心配している状態が一番苦痛を感じる」ことは忘れないほうが良いだろう。実際の明日よりも、そのことを心配している夜のほうが「つらい状態である」可能性を。
数学嫌いは「これから数学のテストがある」と思った時に、脳が痛みを感じているのと同じシグナルを発している。心理学者曰く「燃えてるストーブに手を乗せたときと同じくらい」だそうだ。
この時、物理的な危険や身体的な危害が予測できる状況で活性化する脳の部分と、同じ場所が活性化していた。
明日が来るのが嫌だと思うときにも、脳が実際に「痛み」と同等のストレスを感じている可能性がある。苦手意識と予測という同じ材料が揃っている。
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/3248/”]
—
・重要なのは、彼らの脳が実際に数学の問題を解いている時にはほとんどストレス反応を示さなかったことだ。「不安」が現実以上のストレスを与えていたことになる。
また、この痛みは主観的には恐らく「痛み」として認識されない。数学嫌いがテスト前に痛い痛い言ってるわけじゃないだろう。
その痛みと同等のシグナルは、恐怖や悲観などのネガティブな感情として知覚されていると考えることができる。
もちろん「嫌な明日」自体は存在するのかもしれないが、下手をするとその実体験以上に今現在苦痛を味わっている可能性すらある。
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/434/”]
・想像に対して、このように身体が反応することがある。梅干しとかレモンとかイメージしただけで唾液が出るとか。
人がなにか過去を思い出している時、それを「追体験/再体験」しているという説がある。未来を予測や想像していても同様に。
メンタルタイムトラベルというのだが、実際の碌でもない時間+それについて考えている時間=それについて悩まされる時間だとするならば、やりすぎは損だろう。
程々のところで思考を切り上げるということができないと、思考に囚われるかもしれない。
「案ずるより産むが易し」なんて言うが、産むのが容易いのではなく、時に案ずることが非常に苦痛をもたらすのではないか。
・「自分が寝たくないと思うことが問題」ならば、日常をなんとかする必要があるとは言えない。日常がなんとかなったらぐっすり眠れそうでもあるのだけれど。大体はそっちのほうが難しい。
「嫌なことに対して無防備でいたくない」という気持ちが、時に裏目に出る。言葉通り「寝たほうがマシ」なのだが、当事者はとてもそんな気になれない。不安から目を離すことができない。(かと言って完全な現実逃避が可能だった所で、その場合むしろ不安が増すという研究もある。対策はしてないわ覚悟もしてないわで。)
ついでにいうと、夜は嫌なこと思い出しやすい。根本的な部分で悩むのに向いていない時間帯だ。明日が気になりだす前に、眠れるなら寝たほうがいいのかもしれない。
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/1919/”]
予定がストレスになる:予測がストレスを生む
関連ページ
予定/約束があると落ち着かない/ストレスになる人
「予定」である限り、それが楽しかろうが辛かろうが時間が近づいてくるにつれストレスになるなんて心理もある。予定に対してうまくやろう、しっかりやろうと意識し過ぎであり、それがプレッシャーになっている面が大きい。
また、予定に対して備えなければならない不自由な状態自体がストレスなどもある。心理的には「仕事」の状態に近くなる。遊ぶ約束でも。
先程このページが休日前からアクセスが減ると言う話をしたが、入れ替わるように「予定がストレスになる」というページのアクセスが上がる。恐らく休日の予定がストレスだということだろう。遊ぶ約束とか、自分で決めたこととか。もちろん「付き合い」ってのもあるが。
スケジュールや予定自体が割とこんな面があり、今回は更に「明日が嫌だ」と思うだけの何かがあり、嫌でも意識させられる。
厄介なことに、人は不安を感じるものに対して無防備でいたくない。
このような心配や不安という形でそれに対して思いを巡らせることは、対策を練っている、心の準備をしているようなつもりになっていることが多い。
ただしこれは反芻思考と呼ばれる現象で、基本的に何かの結論を導き出すこともなく延々と繰り返す。ネガティブ感情を呼び起こす場合は侵入思考とも呼ばれるが、今回はそちらが相応しいだろう。この場合当人を緊張させ、消耗させる。緊張状態にさせるため、心臓や血管に負担がかかる。
うつ病の可能性について
一見すると鬱病の症状と少し似ているが、どちらかと言えば適応障害の方が近い。
・うつ病では、「職場や人が怖くなる」ことがあるとされる。これは「明日が怖い」「会社が怖い」というのとはつながる。
「不安」はうつ病の代表格でもある。悪夢も多いとされ、どれも寝たくないという心境は発生しうるだろう。どちらが先なのかは微妙なところだが。
・うつ病は大きく分けて2種類あり、上記は「定型うつ病」や「メランコリー型うつ病」と呼ばれるタイプの話。従来のイメージ通りのうつ病という認識で良い。
これとは別に、非定型うつ病/ディスチミア型うつ病というものがある(10~30代を中心とした世代に多い)。こちらの症状は従来のうつ病のイメージといくつか違う点がある。今回に関連していそうな要素だけ並べれば、
- 楽しいことは楽しめる(会社では死んだ目をしていてもプライベートでは元気など。メランコリー型は好きなことも楽しめなくなる)
- 夕方から夜にかけて具合が悪化する(メランコリー型は朝が具合が悪く、夕方から夜にかけて軽くなる)
この2点、楽しいことは楽しめる上に夕方から夜にかけて具合が悪化するということは、つまりは平日が大分苦痛なことになる。つまらない時だけ元気で、自由な時間に具合が悪くなるのが毎日なのだから。
ただ、非定型の方は過眠の傾向もあり、寝たくないという気持ちとは一見一致しない。早合点もよろしくないだろう。
抑うつと不安や焦燥
・不安が焦燥感に繋がり、じっとしていられなくなるという話はある。
うつ病の場合の「焦燥」とは、静かに座っていられない、足踏みをする、手首を回す、皮膚や服その他のものを引っ張ったりこすったりする、といった症状が含まれます。
https://utsu.ne.jp/depression/mind/
この仕草は心血管疾患に成りやすいとされるタイプAとも酷似している。加えて日本人のタイプAは、「断ることができずに仕事を抱え込む仕事中毒」が多いとされる。うつ病になりそうなパーソナリティではある。
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/800/”]
うつ/抑うつによる不安→焦燥感→上記の行動傾向→寝るつもりねぇなコレ、というのは言える。
これだと結局「明日が嫌だと眠れなくなる」ということの証明にしかならないが。
なお、うつ病に限らず「抑うつ状態(気分が落ち込んだ状態)」とすれば、これは心理的な状態であり、うつ病じゃなくてもなる。
・不安というのは必ずしも悪いばかりでもなく、「しっかりやるため」に機能している側面が有る。侵入思考などの「悪いことが思い浮かぶ」のも、そうならないための予防や回避的な行動を本人に取らせるための機能だともされる。それが焦燥となってしまうと、むしろ失敗の原因ともなるだろうが。
・案外、寝たくないのはネガティブな不安ではなく、ポジティブな意気込みなのかもしれない。どちらにせよ気にしすぎなのは確かだろう。
出社拒否症は明日が怖くて寝たくないのと似ている
・うつ病に似た症状として適応障害があり、適応障害の一種として出社拒否症がある。
うつ病との違いは「ストレス源から離れても症状が持続するか」。
・出社拒否症はかなり今回の話と合致する。露骨に会社に行きたくないと思うし、行こうと思うと体調不良になるし、会社の玄関まで行くと身体が硬直する例もある。
前兆としてうつ病と同じく倦怠感と不眠がある。うつ病になりやすい性格と出社拒否になりやすい性格が似ていることも興味深い。
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/2411/”]
周りに合わせることに疲れてきた場合、社会的な「日常」には拒絶感が出るかも知れない
・過剰適応と言って、「周りに合わせすぎる」心理がある。他者に合わせる分、自己は抑制される。その分疲れるし、そのうち嫌になる。
表面上周囲と適応できているが、心理的に納得いっていない、自分らしさがない、やりたくないことをやっている感がするなどを「内的不適応」と呼ぶ。さらに「そんなことを思ってはいけない」と本心である感情を否認する傾向も有り、これをやると病みやすいし、反発から更に周りに合わせようと頑張り過ぎることもある。
これらの性格的特性はうつ病になりやすいとされるメランコリー親和型性格と似ている。真面目で責任感が強く、自己犠牲的。これは個人的な意見だが、うつ病の前兆として恐らく過剰適応は見られるのではないだろうか。
大抵自覚がないとされる。無理をして周りに合わせていることへの自覚がない。ただストレス自体は蓄積する。「いつストレスが溜まっているのか」くらいは身体がわかるだろう。
明日が何の変哲もない平日で、なおかつ寝たくないほど嫌なのならば、日常的に過剰適応しているのかもしれない。
- 本来感 自分らしさを実感すること
自分の意志で率直に動けることと、その実感。
明日が嫌で寝たくないことの対策
・陳腐な意見だが、寝たほうがいい。日常に問題があるのは確かだが、寝ないで憂さ晴らしすることは全く解決に貢献しない。それどころか悪化する。
今回「不眠」ではないので眠れるはずだ。
不安と不眠の悪循環の危険性
脳的に言えば、不安や恐怖は扁桃体が過剰に働いている状態となる。
これを抑えるのは前頭前野と呼ばれる領域だが、睡眠不足が続くとこの場所の働きが弱まってしまう。
睡眠不足により、感情のコントロール能力が減るということ。その分感情に「飲まれる」ことが増える。次はさらに不安感が増す。繰り返せば更に感情のコントロール能力が失われる。
今はまだ「寝たくない気持ち」で済んでいるのなら、寝たほうが良い。「眠れなくなる」前に。
・そもそもその「初めの不安感」自体が、蓄積された睡眠不足(睡眠負債)のせいではないかと疑うことも出来る。
時には「無表情な人の写真」を見て「怯えた顔」に見えるなども起きる。これは扁桃体がその様なイメージを作り、それをフィルターとして見るためだとされている。中立的な属性のものが、不安や恐怖の対象に見えるということ。
言い方を変えれば扁桃体が過剰に働いていると、嫌なことや不安になることを見つけよう、思い浮かべようとしている状態に近くなる。
・一方で睡眠はストレス解消にはかなり良質な行動だとされている。本当に、眠れるならば寝たほうが良い。寝たいかどうかという「気分」での判断ではなく、寝る時間かどうか、眠れるかどうかだけで決めてしまった方が。
恐怖と不安について
・心理学では恐怖と不安は別物とされる。恐怖は具体的な対象がある。不安は精神医学的には「対象のない恐れの感情」とされる。今回の「怖い」がどちらになるのかはそれぞれだろう。
・恐怖(=原因が具体的なもの)に対しては、準備をすることは有効になる。仕事が忙しい、難しい、だから明日が辛いという言は多かったが、対処法の中で効果があった経験談には「予習復習が有効だった」という声もある。
明日というより仕事とかが嫌すぎて、反対に自由な時間には仕事のことは一切考えないようにしようなどの「避ける意識」は多いように見える。
しかし「安心」をするためには、それと向き合って準備や予習復習などをするほうが良い。気晴らしでは気分が晴れるだけで、「安心」は手に入らない。
・不安に対してだが、具体性がないのが難点だ。対策のしようもない。この上で警戒対象も漠然としているのなら、「何か」があるのかもしれないと常に警戒し続けることと等しいため、精神が疲弊する。
裏を返せばただの「気分」、もっと言えば「気のせい」かもしれない余地もある。
例えば友人と遊びに行く予定がストレスだ、という人も多いが、「行ったら楽しい」との感想もまた多い。この上でまた予定が決まるとストレスだったりする。不安を感じることが正しいようには思えないし、役に立っているようにも見えない。このような、気にしないに越したことはない可能性はある。
考えないようにする努力は逆効果になるかもしれない
・考えたくなくても考えてしまうことは、侵入思考と呼ばれる。繰り返されるので反芻思考とも。これに対して、「考えないようにする」という方略は恐らく逆効果になる。
・論文にも書いてある有名所だと、シロクマ実験がある。「何考えてもいいがシロクマについて絶対考えるな」と言われるとシロクマのこと考えてしまう話。
厳密には「シロクマの一日」みたいなビデオを見せてから「絶対にシロクマのことだけは考えるな」と言ったグループは、「覚えろ」と言ったグループや「考えても考えなくてもいいよ」と言ったグループよりもバッチリ覚えていた。[efn_note] ダニエル・ウェグナーによる皮肉過程理論の実験 [/efn_note]
・解説として有効なのが、「シロクマについて考えてはならない」ということを「覚えていなくてはならない」時点で割と矛盾が発生しているからだ。
シロクマのイメージは頭の「ブラックリスト」に入るわけだが、ブラックリストの中を見なきゃ、何を考えちゃいけないのかがわからない。中を見たら、それはもう考えたも同じ。そういう矛盾。
この上で常に考えないように脳内をチェックするため、結果として「他の動物を見てもシロクマを連想しやすい」というところまであり得るとされる。
代替思考
・別の研究では厄介なことに、思考の「抑制」は一時的には効果があるが、その後もっと酷くなる傾向が観測されている。
それよりも代替思考、つまり「何か他のこと考える」ことのほうが害なく考えずにいられる。
・代替思考の内容次第では、もっと酷いことになる。うつ病の人間は、日頃からネガティブな代替思考を行っていると示唆されている。
良い効果が出やすい代替思考の内容は、
- そのことに関連している方が効果がある
- ポジティブな方が効果がある
この2点。
現状に関連し、ポジティブな結末か意味付けを行う思考。私が呼んだ論文では、ことわざを使っていた。
例えば何か失敗した件に対して、「失敗は成功のもと」という言葉のほうが、「笑う門には福来る」という言葉よりも効果は大きかった。
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/1240/”]
系統的脱感作法
不安を感じることをイメージしながら体をリラックスさせる。要は不安を感じるようなことに対して身体が反応しないようにする訓練。
イメージ対象は、軽く嫌なものからすごく嫌なものまで予め階層化しておき、軽いものから慣らしていく。
弛緩法(リラックス法)としては、身体に10秒程力を込める→20秒ほど力を抜く筋弛緩法などがある。論文などではシュルツの自律訓練法が使われる例が多いが、あれは独学でやるのは少し危険かもしれない。
系統的脱感作法は、パブロフの犬などの古典的条件づけがベースとなっている。
「ベルを鳴らす+エサをやる」→「ベルが鳴るだけでヨダレが出る」という条件付けばかりが有名だが、この状態から「ベルでヨダレが出るが、エサは出てこない」ということを繰り返すと、条件反射は観測されなくなる。
これは「消去」と呼ばれる。個人的には「なにもない」ということを新たに学習した「上書き」だと思うが。
系統的脱感作は、想起と反応(今回の明日のことを思う+眠れない)を、ここで言う「消去」を狙って慣らすことになる。
後の暴露療法(暴露反応妨害法)へと発展するが、あちら系は専門家以外がやると酷いことにしかならないだろう。
関連:
_第一世代(行動療法)
マインドフルネス
・マインドフルネス(禅や瞑想に近い)で扁桃体を沈静化出来るとされている。系統的脱感作よりは副作用の心配はないだろう。
マインドフルネスにおけるデタッチメントという概念は、思い浮かんだことに「反応しない」ことに努める。今回のような、嫌なことが思い浮かぶ→心身がストレス反応を起こすという条件反射そのものに効果がある。
関連:
_マインドフルネス認知療法(MBCT)
_アクセプタンス(受容)とマインドフルネス
_可塑性とは