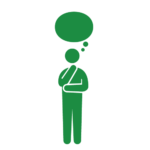・主に積極性/消極性の話になる。
自己効力感とは
・「やる気と自信の源」と言っても過言ではないだろう。
・自己効力感は、その人が何かしら行動により結果を出そうとした時に感じる、「自分はそれをうまくできる」という感覚のこと。一種の自信。
当人の実感であり、事実とは必ずしも一致しない。このため不当に高い、不当に低いということはあり得る。ただし自己効力感が高い場合、実際に達成する割合もまた高い。
・自己効力感を感じた場合のメリットが以下。
- その物事は達成率が高い。
- 挑戦しよう、努力しようというモチベーションが高い。
- 似たような状況でも行えるだろうという認識を持ち、状況が変化しても積極的になる。
- 不安や恐怖が少ない。反対に自己効力感が低い場合は不安や恐怖は強い。
リハビリや自己管理を要する治療などの達成率も、自己効力感に比例するという発表がある。
・提唱者であるカナダの心理学者、アルバート・バンデューラの定義では「達成をもたらすような一連の行動を計画し実行する能力に対する信念」。
「信念」という言葉は誤解を招きそうだが、意図的な思い込みなどではなく「認知」に近い。
「自分がそれに効力を発揮できるか」という認知なので、自己効力感が有れば自信が湧き、無ければ自信がなくなる。
達成のために何をしたら良いかわかる。そしてそれを実行することができる、という自信。
また「自己効力感が強いほど実際にそれができる傾向がある」としている。
・パンデューラは恐怖症を克服した様々な人々にインタビューをした。彼らには恐怖症を克服したことにより、ある変化が共通してあった。
自分は困難を克服できる、自分は現状を変えることができる、と信じられるようになったと。
これに興味を持ち、継続して研究した結果、上記のように「自分は乗り越えられる/変えられる」と信じられる自己効力感のある人は、困難にぶつかっても挑戦し、立ち直りも早い傾向が証明された。
一見すると自己効力感は、タスクに対して能力と比較する「できるかできないか」の認知なのだが、もっと総合的な「自己評価」の認知なのが実態のようだ。
だからAが良ければBにも積極的になれる。自分がAで成果を出したから。
・自己効力感が高い人ほど、不安/恐怖/恐れが減少し、心拍数も安定する。
これは「自分でなんとかできると思ってるから落ち着きが有る」と言える。
・テストで測ることができる。外部からの影響を受ける(コントロールできる)。感覚として当人が認知できる。
・自己効力、自己可能感ともされる。
・セルフ・エスティーム(自尊心)とは別物。これは自分だけを見ている状態だから。自己効力感は自分と対象を見ている認知。ただ、全く無関係でもないだろう。前述の通り、自己効力感も「自己評価」の側面が有る。
行動遂行の先行要因
・人が行動を遂行するか否かを決める事前の要因として、結果予期と効力予期がある。やったらどうなるか、自分にそれができるか。
・結果予期は「その行動をした後にどうなるか」であり、行動できるかどうかではない。
なので「悪い結果になるだろう」と予期できるならば、実行できてもやるべきではない、となる。
簡単な話、平時に非常ベルを押すだけなら誰でもできるわけだが、騒ぎになるからやらないだろう。「自分にはできる」とか言って押したら馬鹿確定だ。止まるべき時には、止まらなければならない。
・結果予期の材料は、
過去の経験
学習済みの知識
今までに積み重ねてきた見聞
など基本的には事前に決まっている、知識/経験。
・結果予期が情報不足で機能しない場合、人は「どうなるかわからない」となる。この際は効力予期が参照される。他の要素でもブレーキ/アクセルはあるが。
「何かあっても自分にはなんとかできる」と思うならやるだろう。
これは博打だし、なんとかなっても結果オーライにしかならず、後でクッソ怒られるかも知れんが。
「自分では対処できない事があるかも知れない」と思うならやらないだろう。
これは無難な選択である。ただし、それでも行動しなくてはならない時には足かせになる。
今回は効力予期の方に目が行きがちだが、結果予期を伸ばすことも同じくらい重要だと思われる。悩むことが減るからね。自信を持って撤退することもできるわけで。
・効力予期(効力期待とも)は、自分への信頼に近い。
目的を達成するために必要な行動を、自分自身が問題なく遂行できると思えるかどうか。
「自己効力感」といえばほとんど効力予期を指している場合も多い。
パンデューラの定義では、「自分が効力予期をどの程度持っているかの認知」が自己効力感となる。
結果、自己効力感が有る=やろう、自己効力感がない=やめとこう、となる。自己効力感自体が直感的な「結論」だと言える。再考もできるだろうが。
自己効力感のタイプ
・これは対象によって区別される。「何に対して自信を感じるか」。
- 自己統制的自己効力感:自分の行動を達成のために制御する事ができる、という自己効力感。真面目、理性的、努力、集中力がある。
- 社会的自己効力感:対人関係における自己効力感。うまくやっていける、既にそうできてる、という認識。
- 学業的自己効力感:学習能力における自己効力感。自分なら覚えられる、理解することができるだろう。
・これらは自己認識であり、現実と乖離している可能性もある。
だが自己効力感があったほうが積極性が増す=挑戦回数が増える。
これは現実での経験値を稼げるということだ。実際は残念な結果だったとしても課題発見にも繋がるだろう。学習能力があれば。
・以下は自己統制的自己効力感について。
自己統制的自己効力感について
・「自信」に近い存在だが、自己効力感は「自分とそのタスクとの関係性」に依存する。
つまり「自分をどう思っているか」だけではなく、「そのタスクをどう思っているか」も要素に入る。
見方を変えれば、自信を持とうとするよりも、そのタスクに自己効力感を感じようとした方が打てる手は多いかもしれない。ターゲット2つあるからな。
・どれだけ取り繕ったところで無理だと思えば、必要に迫られない限りは積極的にはやらないことは多い。
これは【自己効力感がない】=【消極的な傾向が強まる】ということになる。
それでもやらなきゃいけないとしても、大体は緊張し、身構える。
踏み込みが甘くなるから、達成度も低くなっておかしくない。
これは認知、つまり当人がそれをどんなイメージで把握しているか、という話だ。
「実力」の話ではなく、それ以前の「手を付けるかどうか」の段階の話。
この段階で無理だと思ったら、実力はあっても「できない」ことになる。
・自己効力感の話に限ってしまえば、認知の話に終始してしまう。
生きるに於いては、実力を知ることは必須だろう。じゃないと
「いい思い込みをもちましょう^^」
程度の話になるし、最悪「できると思い込め」なんて暴論まで出てきそうだ。
プラセボ効果とか考えればそれはそれで効果はあるかもしれないが、大体の場合は練習でもしたほうが早い。
自己効力感に影響する4つの情報源
・バンデューラ曰く、
- 制御体験:思考が行動をコントロールすることで成功した経験。最も強く影響するとされる。
重要なのは客観的な正否ではなく、当人が「自力でやり遂げた」という実感を持つこと。 - 代理経験:他者の体験を見本にする。モデリングとも。自分と同じような人間が成功したら自分もできるかもと思い、失敗したなら同じ轍は踏むまいと考えるなど。
- 言語的説得:成功できると思わされることを言われること。励まし、認められるなどで上がる。反対なら下がる。
- 生理的情動的状態:感情、気分、身体的な反応などの自分の状態。例えば、緊張して脈拍が上がるような状態であれば、自己効力感は下がる。反対にリラックスして堂々と振る舞えたなら、自己効力感は上がる。
・「当人がそれをどのように認知するか」によって、自己効力感を強めたり、弱めたりする。
例えば言語的説得では、当人がそれを「あり得ること」だと認知できればプラスになるが、「そそのかされている」と感じれば当然マイナスになるだろう。言い方が問題の場合もあるが、当人の認知の問題なこともある。
・いくらか「他人の余計な手出し/口出しで嫌気がさす」ということへの説明にもなっている。
・補足だが、この4つは表記ゆれが激しい。
例えば制御経験の位置に「達成経験」が来ることもある。だがただの「達成」ではなくて制御した結果の達成であるとの認識のほうが正確だろう。
またO.マダックスによって「想像的体験」が加えられた。言葉通り達成を想像すること。イメージトレーニングとして解釈すれば、それほど荒唐無稽でもないかもしれない。
他には承認、つまり他人からそれが成功だと認められることも要素となる。
・上記にさらに追加して、影響を与えるとの報告されているのが6つ。
- 意味づけや必要性(何のためにそれを行うか)に重きを置いている。
- 方略(この場合は手立てのこと)を知っていて、それを活用できる。
- 原因の帰属。つまり「この結果は何のおかげか」という認知。面白いことに「努力」よりも「能力のおかげ」だと思う者のほうが自己効力感が高い。
- 利用可能なソーシャルサポート(社会的関係の中でやりとりされる支援)を多く認識していること。
- 認知能力が高いこと。過去や未来と今の自分との因果関係や、我が身を振り返る反省能力など。バンデューラはこれを自己効力感における「前提」としている。
- 健康であること。身体的な衰えが、老人の自己効力感が低下する原因になるなど。
・活気がある、あるいは反対に倦怠感があるなどの「気分」でかなり左右されるともされている。
・帰属の件はちょっと面白い話だな。
言い換えれば「頑張ればできる」と思ってるより「才能/実力があるからできる」って思ってたほうが自己効力感高いってことになる。
自己効力感の有無は「手を付ける前の心理的ハードル」に直結するだろう。それを気楽にするのは「元から可能である」という認識が有効ということになるか。
逆に達成には努力が必要だとの認知、つまり「これには努力を要する」という認知の場合、そりゃ気軽ではないだろう。「その気になればできる」は「その気にならないとできない」ということだ。
そして達成を努力に帰属するということは、だいたいのことに対して「達成のためには努力が必要」と思うということだ。
思うに人は、かなり努力を始めとした自己制御だけに依存した自己効力感を持っている。
・努力という名のハンマー釘病からは、卒業する必要はあるかもしれない。
努力自体は結構だが、あらかたの人間が、ほぼすべての出来事を、
「失敗したのは努力が足りない」
「成功したのは努力したから」
と努力に「帰属」させていることは断言できる。
多くの日本人がそういうシナリオが好きなのは間違いない。
(これは結果を「自分の力」そのものではなく、忍耐や努力に対して世界/社会が与える「報酬」だと歪めて認知しようとする試みに思える)
これで 失敗 = 自分のせい という図式は成り立つから、完璧主義やうつ病になることに一役買ってるのではないだろうか。
努力信仰は、努力以外の問題をスルーして突き進むことになる。
流石に話が逸れてきたので以降は割愛。
自己効力感によるスパイラル
・自己効力感は、行動変容(自分を変える行動)を起こす原因になっている。「先行要因」、つまり先立って存在し、行動変容を生み出すものとされている。
自己効力感があれば自分がより良く変化しようとするし、ないなら諦める。この分岐に関わる。
変容を可能とする認知的変数、要するに頭が柔らかい。柔軟性が有る。思い込みで勝手に行き詰まったりしない。
そしてこれらは良い循環を生む。自分の限界を決めつけずに、より「できること」を拡大していくことになる。
・うまく行ったら「次もうまくいくだろう」。
うまく行かなかったら「次からはもっと用心しよう」。
このようにある種の調整が為されている。
穴があるね。初めから自己効力感を感じられないもの、つまり「やらない」場合、無条件で「正解」となる。やらない選択を取り続ける。
まぁ穴と言うか、このように迷いもしないで「これ無理やらない」と(脳が勝手に)決めたという結論なのかもしれないが。
・これは、自分が感じる自己効力感の有無だけに従っていると最終的には「できないからやらないこと」が増えていくことになる。
インフレして(=調子こいて)失敗した結果下がり、適度な自己効力感になるなら妥当だろう。だが、元から自信がそれほどないことに更に失敗したら。それが繰り返されたら。これはもう学習性無力感ではないのか。
何よりも「自身の成長性」に対しての自己効力感が失われてしまったら、よろしくない。「心が折れた」という状態になる。
逆に考えれば、負のフィードバックに対しての耐性(あるいは認知的処理)の有無も自己効力感を「維持できるか」には関係していると考える。
簡単に言えば「失敗を気にしないって強いよね!」ってこと。まぁ必要分は気にするべきだが。
メモ
・一つだけ懸念点。自己効力感は「最後まで走りきれるかどうか」という計算に近い。
割と打算的というか、合理的というか、そんな立ち位置。
これは「遂行」のための計算であり、「挑戦するかどうか」ではない。
逆に挑戦しようと思った上で「できそうだ」と思うなら、自己効力感が際立ち、挑戦心による行動とは言えなくなる。
結果、「挑戦心」は「できないかもしれない」という対象にしか現れる余地がない。
失敗恐怖症とか、まぁそんな感じの「できなそうだからやらない」系の精神的状態はあるが、これは挑戦心がないのではなくて、自己効力感がない=やるべきではない という構図が染み付いているだけかもしれない。
ともかく、行動するしないの指針には確かになるのだが、これだけで判断していると、やっぱり「できることしかやらない」になる気がする。
この上で負のフィードバックによりできることが減っていくと、まぁ結構怖い。
http://blog.livedoor.jp/pellow413-jcda/archives/3169520.html
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jans1981/20/2/20_39/_pdf