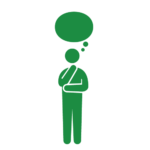・特定の相手とではなく、「人付き合い」そのものがめんどくさい、疲れることについて。
人付き合いをめんどくさいと思っている人たち
- 歩いてる時に対面から知り合いが来たらルート変更
- スマホや時計などを気にするふりをして目を合わせない
- 話しかけられてしまったら嫌がる素振りは見せず友好的
- でも話題がないから早く会話を終わらせたい
- あるいは無理にでも話題を探さないといけない使命感を感じる
- 別に相手のことを嫌っているわけじゃない
- 楽しく話をしていても、会話が終わって相手と別れると疲労感を感じる
- 別れた後は、なにか変なことを言わなかったか、あの言い方じゃ嫌味や自慢に聞こえただろうかと1人脳内反省会
- 一人でいるのが基本で、人と会うのは「イベント」である
- 知らない人とは話せるが、仲良くなると苦手になる
- 二人きりなら話せる。あるいは反対に三人以上でなら話せる。
- 美容院の人に世間話を振られるのが苦行
- でも放置されても寂しい
動機としては大体は、
- 自分のために金・時間を使いたいのにそのペースが乱される
- 他人を気にする・他人と合わせることに疲れてしまう
のどちらか。
元々人付き合いに対して、嫌い、疲れる、めんどくさいと感じているタイプと、急に全部嫌になってきたタイプと、仲良くなってからそう感じ始めたタイプとがある。
関連:
仲良くなるとめんどくさくなる
今回は最初から苦手意識を持っているを中心に。
人付き合いが苦手・疲れる人の2つの要素
要素としては2つある。
- 人付き合いが「こなす作業」であり、元から楽しむつもりもない、他人に興味がない。
- 相手のことも悪く思ってないし、人付き合いも楽しい/うまくなりたいが、一人になってからものすごく疲れる。
1の場合は相手によったりする。極端な話、恋人や友人と休日を過ごすのと、嫌いな上司の遊びにつきあわされるのとじゃ同じなわけがないだろう。この義務感や作業感を、割と広範囲の人に感じている場合。単にドライだったりクールだったりかも知れないし、一人でやりたいことが有るのかも知れないし、理由も様々だ。
2はユングの内向型。ユングは内向型を「社交によって疲弊する」「孤独によって回復する」としか定義しておらず、別にシャイだったり人見知りとは限らない。ユング自身は内向性と病的さとの関連は否定し続けた。つまり個性というか、性格というか、割と自然な気質。
内向型は、当人は社交的な性格であることも割とある。社交によって疲弊するのは人付き合いが嫌いだからではなく、外向型よりも多くの気づき、思考、気配りなんかをしているため。無意識にそうして疲れてしまうため、一人の静かな時間が必要だという話。
まとめると、「人付き合いをすること」が問題か、「人付き合いが苦手・疲れること」が問題かで分かれる。両方ってこともあるが。
人間関係リセット症候群
・人付き合いが面倒すぎて、嫌になって人間関係をリセットしたくなることもあるし、実際に行動に移す人もいる。
巷では人間関係リセット症候群と呼ばれ、転勤や引っ越しへの衝動がある。周囲から見ると突然の音信不通となる。
あるいは引っ越しやアドレスを変えたなどをいい機会とし、以前の付き合いの相手には一切教えないなどがある。
・大抵が「仲良くなりすぎたら失敗」という価値観か(自分の時間を守りたい。相手側の距離感の問題も大きいのだが)、「見せたい自分に見せかけることに失敗したから(完璧主義な傾向。ただしこれは万人にある欲求だ)」が多い。
人付き合いが面倒になってきている人にとっての適度な距離感とは、ある程度の「他人行儀さ」が残っているやり取りだろう。
図々しい、馴れ馴れしい、とまではいかなくとも、愚痴を吐いてくる、同調してもらいたがる、プライベートに興味を持たれてキモいなど、まぁ普通の「仲良し」には十分ウザさを感じる余地はある。
相手のことを「知りすぎた」から嫌気が差すこともあるし、「知られすぎた」から居心地が悪いこともある。
空気や距離感が読める/分かる以前の問題で、「好み」そのものが違う。中には悪趣味なのも居るが。
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/825/”]
仲良くなるとめんどくさくなることもある
・プライベートという概念には、「自分の情報のコントロール」が含まれる。要するに、「これは知られたくない」というのが守られない場合、プライベートは成立しない。
・一方で、ジョハリの窓という概念がある。自分や他人の視点から見た自分の4系統であり、自分にまつわる側面の内どれを公開し、どれを隠蔽するかという自己開示にまつわる考え方。
- 解放の窓:公開された自己
- 秘密の窓:隠された自己
- 盲点の窓:自分は気づいていないが他人から見られている自己
- 未知の窓:誰もまだ知らない自己
当人が他人に「許可」するのは、解放の窓だけである。一方で付き合いが長ければ相手の情報を知る機会も増える。その中には秘密の窓、盲点の窓、そして未知の窓から覗かれたもの、つまり当人からしてみれば「隠すことに失敗した情報」に属するものもある。
まぁカッコつけるのを諦めて気心知れた仲になっていったりもすることもあるのだが。
・総じて仲良くなるとめんどくさくなる余地はある。自分のことを知られすぎて。これは気にし過ぎも多いが、相手側がデリカシーがなく、実際にプライベート/プライバシーが守らている感覚が全くしないこともある。
あまつさえ、他人の秘密を「コミュニケーションの道具」にする者も居るし、それを咎めるでもなく参加する汚い集まりもあるわけで。
さて当人だけの問題なのだろうか。殆どの場合、人付き合いが面倒と言ってもその対象は「今の人間関係」であり、根本的な人間嫌いとは異なることが多いし。
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/1205/”]
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/1916/”]
内向型は人付き合いで疲れたり面倒になったりしやすい
・内向型に原因があると言うよりは、外向型との相性がやっぱり悪いのが原因なんだが。
内向型は「社交で疲弊し、孤独により充電する」と言われるくらいには、元から人付き合いに疲労感を感じる。これは個人の好き嫌いとは関係なく、たとえ相手が好きでも、コミュニケーションを楽しんでいても、終わったら疲れるといった感じになる。
多くは極端な内向・外向ではなく、その中間の両向型だとされるが、その中でも内向よりなのかもしれない。
なお、内向型の人間関係は「狭く、深く」になりやすく、社交のイメージである「広く、浅く」とは本来正反対。
この観点だけで見ると、外向型は人付き合いで回復するよくわからない存在になるので、張り合ったり付き合ってると疲れる一方にはなる。
内向型の4分類
同じ内向型でも、さらに分けられる事がある。このため、疲れる理由は異なる可能性がある。
ウェルズリー大学のジョナサン・チークは、内向型を4つに分けた。
- 社交系内向型
単純に好きで一人でいたいタイプ。非社交的ではない。 - 思考系内向型
思慮深い。関心が内面に向いている。外面を意識せざるを得ない人付き合いに苦手を感じる可能性。 - 不安系内向型
人見知り。「見られている」と感じて緊張し、疲れる可能性。 - 抑制系内向型
じっくりと考えてから動きたいタイプ。自分のペースを乱されるから、人付き合いが苦手な可能性。
外向型として振る舞ったあとは充電が必要
ブライアン・リトルという研究者がTEDで行ったトークがある。彼は内向型であるが、自らの特性を超えた(外向型としての)振る舞いをしなくてはならないことについても語っている。
柄にもないキャラを 長期間にわたって演じているときは くれぐれもご注意を
自分自身を大切にしていないと 気づくこともあるでしょうから
私の場合「擬似」外向型人間として しばらく振る舞った後は
独りになって回復する場所が必要です
つまりは疲れ、「充電」が必要になっている。内向型にとって人付き合いとは、元からそんなもんだと言える。
なお、内向型は別にマイノリティではない。つまりは多くの人間が人間関係に対して「やせ我慢」していたり、面倒だと思ったり、ちょっと疲れていることになる。
関連:
内向型について
人付き合いじゃなくて「予定」がストレスの可能性
人付き合いが面倒というのは「予定がストレスに感じる人」と重なる所が多い。予定という概念自体が「仕事を連想させる」としてストレスになったりする。
相手のことは嫌いじゃない、むしろ好きかもみたいなことがあるとか、
ちょっと無理して友好的・社交的に振る舞おうとする責任感が強い所とか、
実は自由な時間が大切とか。
人付き合いも「予定」の内ではある。予測可能なパターンは、そのまま予定となりえる。
平日に於いても「お決まりのやり取り」が、休日に於いても「無難な振る舞い」が予測でき、意識しすぎるならば、ストレスにはなるだろう。
突発的なイベントにしても、自分のペースを崩される、一人の時間を邪魔されることには代わりはない。やはり面倒に思ったり、疲れる理由にはなる。
これはほぼ自動的であり、予定が入った時点で始まる。脳内シミュレートやリハーサルなどが無意識に始まり、それがストレスになる。集中力も落ちた状態となる。
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/1060/”]
他人を気にする自分が嫌い・人を気にする自分が嫌い
頭の中では、実際の人付き合いの時間以上に、準備、予測、終わった後に例の「一人反省会」つまり内省など、それ以上の時間がかかっている。もちろん後で「あんなに自分を出すんじゃなかった」と思うようなら、実働に於いても注意が必要になる。
つまるところ人付き合いの前後の時間、頭の中は他人他人他人他人、で自分がない。まぁ気にしなきゃいいだけの話なんだが、気にする人は無意識的に、勝手にそうなる。そのような他人を意識している時間、頭の中の自由がないから人付き合いが嫌い、というケース。
これは割とそういうものであり、本能に近い。社会と本能は一見すると相対的だが、犬や猿、イルカやカラスなんかも群れをなして生活できるわけで、別におかしな話でもない。ちなみにイルカはイジメまでするそうな。
人付き合いと個人と社会
「社会」と言うと、なんぞスーツでも着ているイメージを浮かべる人もいる。しかし単に他人との付き合い程度の意味を表すことも多い。つまり人付き合いは「社会的」である。
ヒューマンが3匹いれば、もう社会性を帯びると思えばいい。自分、相手、「その他」の3者が存在する限り。この時点で相手からの評価でなく第三者からの「評判」などの概念が成立するし、なんならゴシップやら悪評を流すことやらも成立するようになる。一対一以外は全部社会だな。ちなみにどちらが得意かは人による。
他者の評価を根拠とする自尊心である、「随伴性自尊感情(要は褒められて自信がついたとか)」という概念がある。
面白いことに学生を対象とした調査では、随伴性自尊感情が高いほど不安や抑うつが高く、自律性も低くなる。この上で学校生活の満足度も高いという、結構いびつな事になっている。
要するに、メンタル疲弊して、自分から動いたりしなくなり、満足度は高い。一見すると意味わからんが、「集団への所属」が満足感を与え、そのために自律性を犠牲にしている。
性格分析であるビッグファイブの「協調性」は、高すぎると「一人じゃ決められない」という状態を示す。随伴性自尊感情の話とそれほど矛盾はしていない。
社会的活動をするためには、「本来性(自分らしさ)」をいくらかは抑える場面は多い。
関連ページ:
本来感 自分らしさを実感すること
一方で、冒頭の人付き合いがめんどくさい人たちの特徴を見る限り、大半は個人の時間や自由を大切にしたいタイプだろう。社会的活動は、元から必要最小限にしたい欲求があっても不思議はない。
総じて彼/彼女たちにとって、世間で言う人付き合いは「重い」可能性。
特に自覚のない緊張
車の運転をするために、ハンドルを握ったとする。この時、それだけで血圧が上がる。
例えば時速30~40km程度の安全運転時でも、平均すると最高血圧が25mmHg上がり、
時速60~80kmでスラローム運転をすると、最高血圧が平均で43mmHgも上昇するという報告がみられます
https://www.healthcare.omron.co.jp/resource/column/life/62.html
また、電話の着信でも、メールの返信をしなきゃいけないときでも、脈拍やら血圧やらは上がるという話がある。格ゲーやってるときの体温が38℃位あるって写真を見たこともあるな。
人はそのくらい即応的かつ緊張のし過ぎなところがあり、相手からの評価を気にしたり、恥をかかぬようにと自己監視する所がある。「人付き合い」は評価者となる相手と対面するわけで、気にする人にとっては緊張の余地はそれ以上にあるといえる。
加えて言えば、日本人は防衛的ペシミズム(心配事を見つけてそれを予防する)が異常に多いともされる。上手くやり遂げるために悪い想像を積極的にして、自分から緊張しに行く感じ。
以上から、「人前」でいる限りは疲れるのが普通な気もしてくる。
繰り返しになるが、人嫌いだとか相手が嫌いだとかの話ではない。単に人付き合いは元からノーコストノーリスクじゃないし、クールタイムは人それぞれだということ。
その他関連しそうなもの
コミュ障なのか
コミュ障って言葉もだいぶガバいからなぁ。立ち話では便利だろうが、考える時に使う言葉でもないような。
何よりも、個人個人で人間関係は様々だ。実際えんがちょな人間しかいないようなコミュニティで萎縮してるんだったら、それはコミュ障と呼ぶのはふさわしくないし。
コミュ能力と人付き合いが面倒と感じることにあまり相関もない。人付き合いを苦手としている人も、振る舞いとしては無難なことは多い。結構こういう人は本質的には気配りというか、「良く気がつくタイプ」が多く、気を使いすぎてしまうから面倒、疲れてしまうから苦手、というケースもある。
特に女性に於いては、共感性が高い傾向がある。同調しないといけない、共感しないといけないと考えがちだとされることもある。その分排除意識が高い群が発生することも在る。一種の義務化とそのエスカレート。
「周りから求められる距離が近い」ことも多い。結果的にその距離感が苦痛=人付き合いが疲れる、ということはある。
要は相手というか、コミュニティの「普通」と合わない可能性。ただこの場合、ほぼ全員が苦痛を感じながら普通のフリを続けるなど、かなり奇妙なことになってる場合もある。
対人恐怖症
・自覚がない場合もある。赤面恐怖症などは、一見普通に振る舞っているが実は、と言うケースも。
他者からどう見られるか、どう思われるか、これらを気にしすぎることにより悪化する。
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/1321/”]
苦手意識を感じる程で落ち着いているならば、軽度とは言えるだろうが。
感情労働
空気を読みすぎる人、気を使いすぎる人、相手に合わせすぎる人などは、無意識的にそうしてしまう。それとは反対に、意識的に共感しようとすることなどを指し、感情労働と呼ぶこともある。
感情労働は主に対人サービスの業種で言われる概念。ざっくり言えば、わがままな相手に対して素直に感情を出すわけにも行かず、我慢しながら笑顔を浮かべて相手しなきゃならないこと。
これを乗り越えるため、人は2種類の演技をする。
- 表層演技:愛想笑い、適当に話を合わせる、表向きの同調
- 深層演技:心の底から相手に同調しようとする労働
どっちみち疲れる。後者の場合は精神を病む可能性すらある。
また、相手のお望み通りじゃない場合の報復を危惧し、防御的な動機でこれを行うこともあるとされる。
感情労働させる者は横柄で攻撃的な態度とも限らず、同情を買うだとか、気を使わせるだとか、そういった方面での「腫れ物」のような相手も含める。
要するに愚痴っぽい奴とか、すぐ「相談があるんだけど」という奴とか、怒りっぽい奴とかの相手は元からめんどくさい。当たり前だな。というかこの手の輩は元から嫌われているわけだが。
まぁ、深層演技は止めよう。確かに中には表層演技を見抜いた上で、「心の底からの同意じゃない」と非難する者もいるが、大抵の場合は他人にそんなもん求める時点でそいつの頭がおかしい。攻撃的で偉そうな病んだ「甘え」は有る。
「充電」の機会を確保する必要性
内向も外向もどちらもそうだが、本来の気質とは逆のこと、この場合で言えば内向型が外向型なことを続けていると「ものすごく疲れる」事が挙げられる。一人の時間が必要な人が、一人じゃいられない人たちと付き合ってたら、そりゃ疲れる。
一人でいる時が充電になるタイプと、人付き合いが充電になるタイプとが一緒に遊んでたら、潤うタイミングと干からびるタイミングは正反対になる。
外向型は言ってしまえば太陽光発電で充電しているようなもので、家でクレイドルに安置しないと充電されない内向型がいつまでもそれに付き合ってたら死ぬ。外向型は曇り空が続いたら死ぬ。この点、外向型の無理解は結構多いが、内向型自身がこれ知らないこともあるのだからまだなんとも言えないかもな。
これは充電の話であり、「社交的かどうか」とはあまり関係ない。ここで「嫌いじゃないが疲れる」ことは辻褄が合う。社交的な内向型や、社交的なHSPなどは存在している。どちらもあとで疲れる点で共通しているが。
内向型は悪いことではない。そして、わざわざ「悪いことではない」と言わないといけないくらいには一部のイメージはマイナス気味。外向と内向の世間のパワーバランスは外向に傾いている。数としては対して変わりゃしないだろうに、内向型は自分がマイノリティであると思っている傾向が高いように見えるのだが。
また、感受性や共感能力が高すぎて自然と「相手に合わせすぎてしまう」こともあるようだ。
人は内向的な面と外向的な面、両方持っている。どっちで充電できるかとか、どっちが気楽にできるかで外向・内向は決まるが、もう片方が無理ってわけじゃない。加えて片方を過度に使い続けると「補償」と呼ばれる揺り返しが起きる可能性が示唆される。後述。
拒否回避欲求
・承認欲求って概念があるが、あれには賞賛獲得欲求と拒否回避欲求がある。
前者はイメージ通り。
後者は失望されたくない、嫌われたくない、バカにされたくないなどのネガティブな評価を避けたい欲求。
当然「そこそこな振る舞い」はする必要がある。
当人の拒否回避欲求が強い場合、日頃から人前では緊張していることになるし、休日に知人とエンカウントしたら「無事に切り抜けるもの」になる。抜き打ちテストみたいな。
冒頭の例でも相手が嫌いなわけじゃないのに疲れる、苦痛を感じる、終わるとホッとするなどがある。
加えて「一人反省会」は、そのまま「ネガティブな評価を受けなかっただろうか?」という感情からくる反芻にも見える。
このような他者評価への警戒、緊張、不安、そして疲労。
好意を持たなくてはならない
・「いい人」に多いと思うが、付き合う人間に対して好意を「持たなくてはならない」というような義務感がある場合。
実際には立場を傘にする嫌なヤツだとか、相手の自然体が我慢ならなかったりと、ぶっちゃけ嫌いな奴とも付き合わなきゃならないことも多い。
このような場合に無理に好きになろうとするのはもう、感情労働だろう。しかも深層演技=疲れる。
・「我慢して付き合わなきゃならない相手」は、損得勘定や利害的な関係となる。別に好きにならなくてもいい。
心理学者アドラーが提唱したライフタスク(人との距離感)は3種類ある。
- 仕事のタスク(永続しない人間関係)
- 交友のタスク(永続するが運命を共にしない)
- 愛のタスク(永続し、運命を共にする)
人間関係で緊張するタイプはここで言う所の交友のタスク・愛のタスクレベルでの付き合い方しか「するつもりがない」ように見える。だから仕事のタスク(仕事に限らず浅い人付き合いすべてを含める)が疲れる。「心をこめすぎて」。
危惧してそうなので言っておくが、これらは相手に対しての点数付けではない。距離感の方針だ。感情労働の概念がいい例だが、もうちょっと精神的エネルギーをリソースとして「運用」することを考えるべき時期かもしれない。まぁ簡単に言えば節約。
「圧力」
内向型は人付き合いで疲れてしまうだけで、人が嫌いでも人付き合いが嫌いでもない。遊びに誘われると、行くまでは憂鬱だが行くと「楽しかった!」となったりする。また、心の底から一人で平気なタイプの人もいるようだ。この場合でも別に人嫌いではないし、そこそこ付き合ったりはする。
外向と内向の話でよくでてくるが、社会が求める社交性に便乗しての外向型の同調圧力(内向にはそう見える)で嫌々付き合ったりしてて疲れる、というのもあるようだ。マジョリティに悪気はなくとも、マイノリティには同調圧力かデリカシーが無いように見えることは多々ある。
就職関係のサイトのアンケートなんかでたまにあるが、ぶっちゃけ飲み会も休日の上司からの電話も半分かそれ以上は「ふざけんな」って意見があったりはする。が、表立ってそれが主張されることは少ない。
この点においては、特に有利な立場の側の無自覚な横暴(やられる側にはそう見える)に対しての憤りの声を、当人が見て驚愕することもある。まぁ逆にそれを傘にどうせ断れないだろうみたいな振り回し方する奴もいるんだが。
前述の「仕事のタスク」の立ち位置の人間に対して、交友のタスクのような扱いをしなければならないと思わせる、同調圧力のようなプレッシャー。これは仕事の人間関係で多い。また、自分で勝手にそのようなプレッシャーを感じてしまい、誰に対しても気を使いすぎる、ということもある。
人付き合いがめんどくさくても、人が嫌いとは限らない
嫌いなわけではない
・大体の場合、人が嫌いなのではなく、「人付き合い」のリスクの過大評価による緊張からの苦手感。あるいは今、人付き合いに疲れていて、「少し休憩したい」感情。あるいはちょっと一人の時間が欲しい。
リスクの過大評価や緊張と言っても、まぁ相手がいる話であるから、相手次第ではそれが妥当なこともある。
ともかく、その警戒心・緊張感が妥当であると自分で判断するならば、そのままのほうがいいだろう。だが限界を感じているのも現実のはずだ。なんか適度で上手な力の抜き方があるといいね。ポイントだけ抑えるとかね。
固定された距離感に注意
・一般的には距離感はおっかなびっくり着いて離れてで「調整」するものだ。最初から加減するから、失敗しても損害は軽微。だが我慢強いタイプと厚かましいタイプが出会ってしまうと一種の上下関係、力関係が生まれ、そのまま固定される。
問題は、厚かましいやつが我慢強いやつ相手に調子こいてるのか、それとも積極的タイプが消極的タイプをサポートしているのか、見ててわからんことだ。時には当人たちにもわからない。まぁわからないと言うよりは、決まってないのだろう。これは「自分から見て相手はどうか」によって決まることだからだ。
だからこそ共感能力ないとコミュ障扱いされる。アスペルガーだとか、サイコパスだとかがそうか。これらは先天的なものだが、もちろん先天的な要因ではない「分かるつもりがない奴」もいるし、「必要以上に分かってもらいたがる奴」もいるし、もうめんどくさいので「相性の問題」ってことにしたほうがいいかもしれない。割れ鍋にも綴蓋って言うし。
まぁ少なくとも、厚かましい方向で「コイツ精神年齢低いな」と思ったら、付き合うこと自体を見直したほうが良いと思うが。ポイントは言葉じゃなくて振る舞いを見ることだね。口だけならインコでも哲学者になれる。
急に人付き合いが全部めんどくさくなったら要注意
燃え尽き症候群の可能性がある。感情労働し過ぎで感情がわかなくなる症状。別名燃え尽き症候群。
うつ状態やイライラが症状としてある。あるいは感情が枯れる、あらゆることに無関心になるなども。そのものズバリ「人付き合いを避ける」ってのもある。急に、全部嫌になるだとかだったら要注意。
ただこの場合でも、「疲れただけ」だと捉えたほうがいいだろう。一時的なものとして。もちろん休息が必要だ。
何件か、こうやって全部嫌になって、ご丁寧に全方面と絶縁して、その後寂しくなりました、なんて話を知っているからね。
この様になった場合には、日常の感情面での負担が高すぎたことは、認めるしかないだろう。ちょっと周りに気を使いすぎていたとか、キャラを演じることに一生懸命になりすぎたとか。
「補償」について。ユングの理論に於いて、片方を使い続けた果ての揺り返し。自動的な調整機能とされ、これによりバランスをとると考えられた。個人的には同じ部分ばかりを使い続けた結果、回復が追いつかない、あるいは焼き切れた感がある。
仲良くなるとめんどくさくなる
一方で仲良くなるとめんどくさくなる、嫌いになるというケースも有るようだ。
仲良くなるってのも色々ある。相手が厚かましくなってきたとかもあるかもしれないがそれは今回は除外しよう。
相手を気に入って、好感をもった場合。当然今までよりも嫌われたくはなくなるだろう。
ところで、承認欲求は特性としてのそれ(本人の性格のようなもの)と、状態としてのそれがある。
状態承認欲求は、その名の通り状況、状態で変化する。
- 相手が大事になった
- 嫌われたくない=拒否回避欲求が強まる
- 緊張するからめんどくさくなる
は、あるかもしれない。
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/1205/”]
人付き合いの結果仲良くなるというのは、相手に気に入られるという意味でもある。
気に入られたのが「演じた自分」であった場合、だんだんと疲れてくるかも知れない。
通常、初めはある程度お行儀よくして、段々と自分を出していく、という形になると思うが、この切替時や加減を見極めるのが苦手だと緊張するかもね。
人付き合いを楽に/気楽に人と付き合えるために
・逆を言えば、現状は以下のようなことをやっている/やっていないことになる。
・自分を尊重すること。「生贄」として差し出さないこと。やればやるほど居心地が悪い人間関係になり、そして周囲はそれが普通だと思いこむ。
自分には「充電」の時間が必要であると告げずに、あるいは「ちょっと疲れた休みたい」と言えずに無理して付き合っている現状なのだとしたら、それが何よりの証拠だろう。
・相手の不快な言動に対して愛想笑いを浮かべるなどもよろしくない。
別に抗議するまで行かなくてもいいが、せめても無表情でスルーするくらいはした方がいい。
この様なささやかな自己主張を否定してくるようなら、その相手はそもそも付き合うべきじゃない人間だ。
・わかりやすい人間になること。どの様な人間かのシグナルを発すること。開示できるものは開示すること。わからなければ考えること。自分のことも結構、考えなければわからない。
ただし、自分を尊重すること、生贄として差し出さないことを忘れてはならない。開示しないものは開示しないこと。「心を開かなくてはならない」という義務など存在しない。それは、やりたくてやるものだ。
人付き合いに疲れるタイプは、自己主張をする性格ではない。ここまでは自覚がある。
それ以上に「違う性格を演じている」方が問題であり、こちらは自覚が殆どない。
フォーマルな、問題のない、無難な、適応的な、協調性の有る、クセのない性格を。それが素の性格ってこともあるにはあるが。
確かにそれは他人としては理想であるが、仲良くなりたい人から見ればその行儀の良さは「壁」に見える。お互いに疲れる人間関係、となるかもしれない。
あるいはよく見せようとし、相手の期待が高まり、それに応え続ける/演じ続けるのが面倒になる。
恐らく「周囲は自分の表面的な面しか見ていない」と思っているだろう。それはあり得るが、それと同じくらい「自分のツラの皮が厚い」可能性にも思いを馳せること。
自分で自分がわからない、というのもあるかもしれないが。
・他の人も割と面倒だと思ったり疲れていることが多い。日本人の文化依存症候群は対人恐怖症だと言われている。得意な奴の方が少ない。上手いかどうかとは別。
まとめ
基本的には、
- 今まで平気だったのがめんどくさいと感じるようになったのなら、感情労働に疲れた。この場合人間関係的な意味で休息を取りたい。仮病でも使おうか。
- 元から人付き合いめんどくさいと思ってたなら、一人でいることで充電するタイプであり、世間の馴れ馴れしさにうんざりしている。ただ、世間の半数くらいはそう思ってるはずなので、意外とその手の話題で気が合う人がいるかも知れない。
・莊子曰く、君子の交わりは淡きこと水の如く、小人の交わりは甘きこと醴の如し。
醴(れい)は甘酒のようなものでベタベタしている。めんどくさいからカルピス原液に脳内変換してくれ。
要するに、人格者の人付き合いはさっぱりしているが、凡人の人付き合いはベタついているということ。で、我々は凡人だからベタついてるわけだ。どうも本能的な欲求として他者との交流を求める気持ちはあるみたいだし。でまぁ、色々それで脳内ホルモン出るし。オキシトシンとかセロトニンとか、ドーパミンとか。
交流中毒とでも呼ぼうか、どうも一部の「人付き合い」は、ベタベタな上に長続きすることが前提の考えがあるように見える。相対的な位置にいる場合、これはキツイものがあるだろう。
莊子の言葉はこう続く。君子は淡くして以て親しみ、小人は甘くして以て絶つ。
君子の付き合いは淡いからこそ長続きするが、小人の付き合いは甘いからこそ途絶える。飽きるだとか胸焼けするとかそういった感じの。
まぁなんというか、カルピス原液みたいな付き合いしてたらそりゃ疲れるだろうと。濃すぎて拒絶とかもあるだろうし。薄める=力を抜くことを考えたほうがいいのかもしれない。