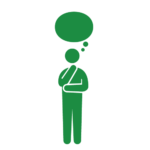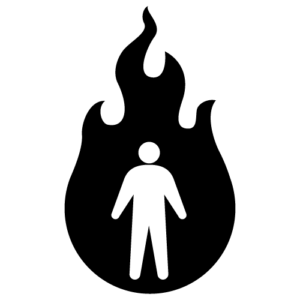

燃え尽き症候群/バーンアウトシンドロームとは
・今まで精力的/活動的だった人間が、急にやる気を無くすことを指す。
・高いモチベーション、真面目さ、共感能力など、何らかの精神的な機能を酷使し、故障したような状態。
深刻な場合は、あたかも燃え尽きたかのように意欲を失い、社会に適応できなくなることとされる。
・
燃え尽き症候群はうつ病の一種
・燃え尽き症候群は医学的にはうつ病の一種とされる。うつ病は3つに分けられることがあるが、心因性のうつ病。
心因性というのは、まぁうつ病と聞いてイメージされるうつ病だ。ストレスによってなるうつ病。他には性格のせいとか認知の歪みでなる内因性のうつ病とかがある。
燃え尽き症候群の原因が主に職場からの継続するストレスとされるため、心因性とされることが多い。しかし個人の性格はやっぱり影響ある。裏を返せば気の持ち方や認知の仕方でなんとかなる余地もいくらかあるのだが。
燃え尽き症候群の症状
・全体像としては、うつ病。それまで精力的だった人間がいきなりそうなるから燃え尽き症候群と呼ばれる。
・生き方や仕事などに人並み以上に頑張っていた人が、突然「燃え尽きた」かのように急に仕事や人に対しての感情や気力を失う。意欲の低下、投げやりな態度となった状態。
本人にしたって突然のことで、なぜできないのか、やる気が出ないのかわからないこともある。当人は「やるべきだ」と思っていることが多く、それができない自分への嫌悪や落胆も多い。
・何よりも「燃え尽きた感覚」が大きいとされている。このため自覚は比較的されるだろう。
・そのまま治らずに離職などのケースも。
燃え尽き症候群の精神面の症状
- うつ状態
- 無気力感 やる気がでない
- 感情が湧かない
- イライラする
- 自己嫌悪
- 希死念慮/自死念慮(死にたいという欲求)
- 仕事への意欲や重要性が感じられなくなった
燃え尽き症候群の行動面の症状
・意欲減退、ストレスを避ける、憂さ晴らし。
- 今までに行っていた日常的なことが困難となる
- 朝起きられない
- 仕事に行きたくない
- 急に遅刻や欠勤が増える
- 酒の量が増える
- 金遣いが荒くなる
- 人と関わりたくない
- 人への機械的な応対(脱人格化)
- 人への無関心
特に会社に行きたくない、遅刻や欠勤などは出社拒否症とも共通する。これもうつ病に似ており、適応障害の一種とされる。
適応障害が特定の状況やストレスに対してのうつ病みたいなものであり、そうなりやすい性格もやはり「それまで真面目だった」例が多い。
燃え尽き症候群の詳細
燃え尽き症候群の由来
・精神科医であるハーバート・フロイデンバーガー自身が目にした光景から。
当時彼は保護施設に勤務していた。一年余りの間に、精力的で目標に満ちた同僚たちが、次々と仕事に対しての意欲・関心を失い、精神的、身体的異常を引き起こした。まるで燃え尽きたかのように。
この症状をフロイデンバーガーは「燃え尽き症候群」と名付けた。
名付け親のハーバート・フロイデンバーガーによる定義
・持続的な職業性ストレスa)職務上の義務・責任感や圧力、要求、自分の能力では足りない場合などでもやらなきゃ/我慢しなきゃいけない。それを続けなきゃいけない。今日も、明日も、明後日も。そういうストレス。に起因する衰弱による。
衰弱により以下の症状が出てくる。
- 意欲喪失
- 情緒荒廃
- 免疫力の低下
- 乾いた人間関係になる
- 人生への不満と悲観
- 職務上の能率の低下
- 職務怠慢
その他の定義ではWHOの「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」に於いて「重要な枯渇の状態」とされている。
何れにせよ、「衰弱」「枯れた」「燃え尽きた」など、元々あったはずのエネルギーがもう無い/出ないかようなニュアンスがある。
燃え尽き症候群のチェック
・バーンアウト (燃え尽き症候群)ヒューマンサービス職のストレスより。
やり方。まずは質問に対してYESかNOか記録するだけの方がいい。アルファベットの意味は後述。先入観があると答えが割と変わってしまうので(自己イメージの答えを言うようになる)。
| 1 | こんな仕事、もうやめたいと思うことがある。 | E |
| 2 | 我を忘れるほど仕事に熱中することがある。 | PA |
| 3 | こまごまと気配りすることが面倒に感じることがある。 | D |
| 4 | この仕事は私の性分にあっていると思うことがある。 | PA |
| 5 | 同僚や患者の顔を見るのも嫌になることがある。 | D |
| 6 | 自分の仕事がつまらなく思えて仕方のないことがある。 | D |
| 7 | 1日の仕事が終わると「やっと終わった」と感じることがある。 | E |
| 8 | 出勤前、職場に出るのが嫌になって、家にいたいと思うことがある。 | E |
| 9 | 仕事を終えて、今日は気持ちのよい日だったと思うことがある。 | PA |
| 10 | 同僚や患者と、何も話したくなくなることがある。 | D |
| 11 | 仕事の結果はどうでも良いと思うことがある。 | D |
| 12 | 仕事のために心にゆとりがなくなったと感じることがある。 | E |
| 13 | 今の仕事に、心から喜びを感じることがある。 | PA |
| 14 | 今の仕事は、私にとってあまり意味がないと思うことがある。 | D |
| 15 | 仕事が楽しくて、知らないうちに時間がすぎることがある。 | PA |
| 16 | 体も気持ちも疲れ果てたと思うことがある。 | E |
| 17 | 我ながら、仕事をうまくやり終えたと思うことがある。 | PA |
割とよく聞く愚痴が多い。大勢燃え尽きてるのかも知れない。
DとEはYESの数を測る。PAは逆転項目(聞きたいことの逆を聞いている)のためNOの数を数える。
じゃあ結果を見てみましょう。
燃え尽き症候群の重症度を測る3つの要素(D,E,PA)
・クリスティーナ・マスラークのMBI(= Maslach Burnout Inoventory)の定義。
医療職・対人援助職の人々を対象とした聞き取りの中で、いくつか共通するテーマが見て取れた。例えば「感情が枯れた」など。それらを指標としたもの。
- (E) 情緒的消耗感/疲弊感
- (D) 脱人格化/シニシズム
- (PA) 個人的達成感/職務効力感の低下
・この3つの要素を別々に測定する。さっきのチェックリストのこと。
セーフアウトの二分はしない。全体的に高い場合は燃え尽き症候群とされる。
・なおWHOの2019年の定義やMBI第四版は、燃え尽き症候群を職業上の経験と位置づけている。
情緒的消耗感/疲弊感
・情緒とは、事に触れて起こる様々な、微妙な感情を意味する。また「情動(急激で一時的な感情)」を意味することもある。
どっちにしろ感情のことだね。これが消耗した/枯れ果てた感覚が情緒的消耗感。
・「仕事を通じて、情緒的に出し尽くし、消耗してしまった状態」と定義される。
これが燃え尽き症候群の主症状だとされる。
人への無関心、人付き合いを避ける傾向はこれが枯れたためだと見られる。枯れたのであって「やりたくない」よりは「もうできない」と言った感じが近いか。
逆を言えばエネルギーを浪費する環境では燃え尽き症候群になりやすい。相手の表情を読み、気遣いをし、行動を予測し、信頼関係を構築し、それらが日常である環境。つまり感情労働。
看護・介護職などの対人サービス業において燃え尽きることが多いとされるのは妥当だろう。
脱人格化/シニシズム
・脱人格化は「相手に対する無情で非人間的な対応」とされる。ロボット的と言おうか、そのような非共感、被情緒的なテンプレやマニュアルのような対応。
・仕事への熱意が減退し、仕事に対して否定的な感情や冷めた感情を抱く。このためシニシズム(冷笑主義)とされることも。
・テンプレな対応や、人として見ていないかのような対応となる。逆に事務的な仕事などに生きがいを感じ始めるとされる。他人から見たら急に人間嫌いになったように見えるだろう。
くれぐれも言っておくが、今まではむしろ正反対の熱心な仕事ぶりだった人間が、こうなる。人格の話じゃない。状態の話だ。だが現実には人格的振る舞いの問題として取り上げられるだろうね。
これは既に枯渇しているエネルギーの「節約行動」、これ以上エネルギーを使わないための防衛反応であるとされる。
対人サービス業で多い点、それまでは精力的だった点から、必要なエネルギーを使いすぎて言葉通り燃え尽きた、あるいは枯れ果てたと見るのが妥当だろう。
個人的達成感の低下
・今まで真面目に、一生懸命、熱心に仕事をしてきた当人自身が、誰よりも今の自分の能力・言動に落胆している。それによる今まで持っていた有能感、達成感の喪失・低下。
能力や活力の低下は自覚できるため、「今まで通りにできなくなった」ことが嫌でもわかる。
このまま自己否定、自責の念に繋がることも少なくないとされる。
燃え尽き症候群の原因
・一定の期間、強い緊張とストレスを与える環境にいると発生が多いとされている。絶え間ない過度のストレスとも。
燃え尽き症候群になりやすい職業
・当初は対人サービスの職に就く人々がなりやすい、とされていた。医療や介護。
今では、
- ビジネスマン
- スポーツ選手
- 教師
- 研究者
- エンジニア
- 受験生
- 子育てする親
何でもありである。根本的には頑張りすぎが原因であるため(裏面として休むのが下手)、そうさせる要素が多ければ多いほどリスクは上がる。
絶え間ない過度のストレスが直接的の原因であるため、職務上ストレスがあって当たり前とされる職業はやはり燃え尽きるリスクは高い。
・対人サービスは特に感情労働(後述)であり、自分本来の感情とは別に笑顔やら親身さやらを演出しなければならない。このためストレスは溜まりやすいが、人付き合いに緊張するタイプは仕事じゃなくてもこうなりやすい。
急に人付き合いが嫌になり、人に会いたくない、めんどくさい、誰も自分のことを知らない所へ引っ越したいなんて思う人間関係リセット症候群には、そうなるまでは愛想良かったタイプがやはりいる。
・もちろん職業だけが原因ではない。特に義務感や責任感が強い場合、なんでもあり得る。
業種よりも人間関係の方が問題になりやすい。あと本人の責任感や義務感も。
誰が燃え尽き症候群になりやすいか:燃え尽きやすい人の性格
・燃え尽き症候群になりやすい性格としては、
- 仕事人間
- 責任感が強い
- 仕事をするための能力が不足している
- 完璧主義
- 真面目
- ひたむき
などが挙げられている。要するにほっといても勝手に頑張る(orそうするしかない状況にいる)人。
仕事の能力不足は、結果として勉強したり、トレーニングをしたりという意思決定を引き出すだろう。今まで以上に。仕事熱心に見えるだろうね。
完璧主義はほんともう、常連だな。本人たちも難儀しているらしい。
ワーカホリック
・ワーカホリックは仕事中毒を指す。この時点で働きすぎなのは確か。
「仕事熱心」という割と肯定的なイメージを持たれることも多いが、「私は働かなくてはならない」という仕事への不快感がモチベーションなので精神衛生はあんまりよろしくなかったりする。
どの道、無理をしてやってる感がある働き方。
・仕事にやりがいを感じている場合はワークエンゲージメントと言われ、ワーカホリックとは別物とされる。モチベーションは「私は働きたい」。
ただし、好きでやってりゃ無敵なのかと言えばそうでもなく。好きなことを好きなだけやったら大体破綻するので節制は必要だと思われる。
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/3154/”]
メランコリー親和型性格
・一般的なうつ病をメランコリー親和型うつ病とすることがある。これになりやすいのがメランコリー親和型性格。上記特徴をメランコリー親和型性格と比べてみると、
- 秩序を重んじる
- 人に気を使う
- 几帳面
- 仕事熱心
- 責任感が強い
- 他人の評価が気になる
- 問題が起こると悲観的
- 凝り性
- 完璧主義
- 弱音を吐かない
だいたい一致している。
・また社会既定型完璧主義(自身が完璧であることが社会への貢献であるとする)にもかなり近い。これまた完璧主義の中では病みやすい方。
理想が高すぎる
・理想が高すぎる傾向。
メランコリー型だって見方を変えれば「立派な人間として振る舞うよう心がけている」ように見えるだろう(実際世間の目を気にする傾向はある)。そのイメージがハードル高すぎると、日常が苦行になる。
高い理想が動機づけを高めることは否定できないが, あまりに現実とかけ離れた理想をもつことは, Bramhall & Ezell(1981)の言葉にもあるように, 燃え尽き症候群の第一段階にあると言わざるをえない。
http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2007/01/pdf/054-064.pdf
・理想は二種類に分けられることがある。義務自己(今できなくてはならない)と理想自己(いつかなりたいから目指す)。
病むタイプの完璧主義者は、理想が義務になっている。このため無理をしがちだ。
真面目
・燃え尽き症候群なりやすい人の特徴として、真面目な努力家が挙げられる。裏を返せばストレス発散や休憩を取ることは下手。
燃え尽き症候群の原因として一つのことに集中して頑張りすぎたからというのがある。この状況を発生させやすい。
・真面目にも種類がある。
単にストイックな者もいれば、何らかの強迫観念で「仕事をしていないと不安」「もっと頑張らないと不安」というタイプもいる。こちらはやはり病みやすい。
・その真面目さが、メランコリー親和型性格のように他者に規定される基準に合わせすぎる性分だとか、理想が高すぎるせいで勝手に頑張りすぎるとかの結果である事が多い。
感情労働_深層演技
・感情労働とは、「心の商品化」とも呼ばれる感情的な演技が必須な職業。介護士や看護師が代表例。燃え尽き症候群になりやすい職業とこの時点で思いっきり重なっている。
大体対人サービスのことをさすが、愚痴を吐く奴を宥めるなどの日常的な文脈でも存在する。
・「飛行機の乗客は、チケットと同時に乗務員に怒りをぶつける権利も買っている(つもり)」なんて言われている。加えて経営者側もそれを売っているつもりになっていると指摘される。
燃え尽き症候群はこのような感情労働が原因とされることがある。直接的な原因であることは疑問視する向きもあるが、遠因(ストレス)ではあるだろう。
・感情労働は「感情の演技」だと思えば良い。親身になったり思いやったりする表現。
これには表層演技(表面だけ)と深層演技(心からそう思おうと務める)がある。後者は精神的に病む原因になる。
面白いことにベテランは表層演技で仕事をして、新人ほど深層演技をする傾向がある。そうじゃなきゃやっていけないから変化するのか、深層演技をしないから生き残れたのかは不明だが。
共感のし過ぎ
・共感能力は一見するとよろしいものだとみなされがちだが、見方を変えれば自分の感情が他人の影響を受けることに他ならない。これも情緒的な不安定さにつながる。
面白いことに他人の感情で不安定な気持ちになった者は、安定を得ようとしてその他人の問題を解決しようとする傾向がある。
第三者が見れば人のことに一生懸命、と映るだろう。自覚として「感情的な人間に振り回されている」と思うのなら、燃え尽きるリスクも高いかもしれない。
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/2824/”]
燃え尽き症候群になりやすい環境
・自分の性格が燃え尽きやすい性格に該当しないからと言って、すぐに安心とはならない。
・研究初期の頃から対人サービス業や医療職に多いと言われており、やはり人相手に感情的な演技を用いる日々だと燃え尽きやすい。ちなみにカウンセラーも割りと病みやすい。仕事内容を思い浮かべれば納得だろう。
燃え尽き症候群は基本的に職場上の体験とされてはいるが、「自分に気を使うように強制する者」の相手をし続けたら職場関係なく燃え尽きてもおかしくない。つまり人間関係での燃え尽きはあり得る。自己愛上司とか、モラハラ上司とか言われるのが代表例。
同じく職種ではなく社風などの「職場の空気」により燃え尽きやすくなる環境も存在する。根性や気合が合言葉な所なら、そりゃ枯れるのも早かろう。
・まず、「ストレスが溜まる職場」が挙げられる。そりゃそうだ。他には、
- 長時間勤務
- 厳しいノルマ
- 仕事をするためのサポートの欠如
などのオーバーワークになりがちな要素は、燃え尽き症候群になりやすい環境として挙げられている。
・上記のような厳しい環境の上で、さらに給料が安いことにより仕事に意味を見いだせなくなり発症、というケースも。意義や重要性を感じられない仕事の場合、燃え尽きやすい。
ただ、燃え尽きるまでは精力的だったわけで、当人の感じる「やりがい」に依って気づかずにオーバーワーク、臨界点を超えた疲労が一気に出る、という感じか。
・加えて環境/当人の行動両方に当てはまるが、時間的に仕事の比率が高い(ワークライフバランスの偏り)、適切なセルフケア(運動や食事)をしていない、という点がある。特に食事は雑になるらしい。これは忙しいってだけでもそうなり得る。
・これらのなりやすい原因を、やりがいなどの「感情的報酬」を抜きにして見れば、「ストレスをためやすい性格、ストレスを感じやすい環境、ストレスを発散していない生活」となる。まぁ健康的ではない。健康には気を使ってないんだから当たり前かも知れんが。
燃え尽き症候群から回復するには
・まず、これは頑張りすぎた結果の疲労または衰弱の状態であり、この状態でさらに気合を入れて頑張ろうとするのはよろしくない。休息が必要である。
もはや手垢の付いた話だが、うつ病の人間に「頑張れ」と言うな、というのは聞いたことがあるだろう。
休息が必要ではあるのだが、大体は強迫観念的に「やらなくてはならない」「まだ動かなくてはならない」と思っているため、気は休まらないだろう。
・うつ病の一種なので、深刻な場合は医師への相談が適切となる。
検索するとなんぞ胡散臭いのが割と上位に来るので、自己治療も危険だろう。
殆どのサイトがさっきの燃え尽き症候群チェックリストを、逆転項目のことを伝えずにそのまま載せている。言い方を変えれば17の質問の内の6つが仕事をしていない。
多分だがコピペしただけで中身を見てない。PAの質問が他からアレだけ浮いてるのにおかしいと思わないなんてことはないだろう。検索上位を読んだ所でそのレベルだと自覚した方がいい。
・環境が原因の場合。燃え尽き症候群と類似した出社拒否症(実質適応障害)は、やはり会社の理解と仕事の量や責任の調整が治療となる話が多い。
燃え尽きた人の大抵は騒ぎを大きくしたくないし、交渉する気力なんて真っ先に枯れているかもしれないが、「相談」くらいはしたほうがいいだろう。相手にこちらの状況を匂わせる目的も込みで。
・当人の性格や認知。燃え尽き症候群がきっかけとなり自分の仕事ぶりを見直し、仕事との適切な距離感が取れるようになった、との話も割りとある。
これは「突き放した関心」とも呼ばれ、過剰な肩入れ(責任感/義務感)をしない立場相応の距離。
となると、やはりベテラン看護師が表層意識を使うのは、後天的に獲得したスキルなのではないか。
・まぁ今回の説明だと深刻な話ばかりだが、「燃え尽き」に限って言えば身近な現象でもある。なんかやり遂げた後で、なんかやる気でない。次に着手する予定はあるのになかなか手が出ないとか。
私もたまに、死んだ目でソリティアとか上海ゲームとか延々とやってることあるし。
・頑張りすぎた結果としての燃え尽きなので。動けない自分を憎むよりは、どちらかと言えば今までの燃費の悪さを反省するべき場面だろう。
大抵は長期的に見れば持続可能な活動パターンでは元から無い。
面白いことに人は「やれない自分」を簡単に憎むが、「アホな計画立てた自分」はスルーする傾向がある。
自己責任の部分としては(それに寄生する他人も多分悪いんだが)、断れずに全部引き受けてなかったか。他人に任せられずに1人で仕事を抱えてこなかったか。仕事に夢中で不摂生ではなかったか。特に睡眠時間。
仕事に仕事以上の何かを投影していないか。自分の存在価値やら生きてる意味やら。一見よろしいが、これは非協力的になる。意固地になるから人が離れる。責任感というよりはタスクへの縄張り意識。結果仕事は抱え込みやすい。
つまり全体最適(チーム/会社)を考える場面で部分最適(個人)に拘る。
頑張ったつもりはない 苦しかった覚えはない
・さて、ここらへんでちょっと疑問が湧く。実際に燃え尽きてしまった人々の中には、それまで心から楽しんで、充実していたと過去の日々を振り返る人もいる。
要するに、この場合実感できるストレスはないわけだ。今現在の定義でも、フロイデンバーガーの定義でも、燃え尽きる原因は「慢性的な強いストレス」であるはずなのに。
ところで、努力家は一般人が引くような活動量の上で「このくらい普通だろう」みたいなことを言ったりすることがある。その内ぶっ倒れたりする。自分で普通だと思っていても、体や心が追いつかない可能性はあるだろう。
・意志が心身を引きずり回している状態。火事場の馬鹿力を発揮するような状態が常だとしたら、ガタが来ても不思議ではない。
25分動いて5分休憩するポモドーロテクニックも、「バーンアウトを避けよ」というのが原則の一つだったりする。休憩を取らないと煙を出しながら走っている感覚がしてくると。
適度な休憩はそのまま燃え尽き症候群の予防になるだろう。
フロイデンバーガー自身が目にした光景も、同僚たちはそれまで精力的だった。
・見方を変えれば「仕事に意義を見出しすぎた」かもしれない。その分一生懸命に、その分重要に感じ、慎重を要し、楽しく疲れる充実した仕事だ。
仕事に意義を見いだせないというのは1つの大きな理由だったが、一方で「仕事の意義を見失った」ことにより燃え尽き症候群になった例もある。
https://kokoro.mhlw.go.jp/over/867/
この自分や周囲へのイメージの変化は参考になるだろう。
自信がある状態から疑心暗鬼へ、最後には報われない/割りに合わないと思い始め、風邪で寝込んだことをきっかけに引きこもった。
そして一ヶ月の療養を経て、ようやく「自分が疲れていた」と気づけたという話。
疲労に前兆があったとしたら、最初の自分や仕事への「イメージの変化」の部分だろう。ただこれは通常、疲労のサインだなんて思わない。
・逆を言えば、(当人としては)頑張ったつもりがない・苦しかった覚えはないのにこうなる、ということはあり得ることになる。
めんどくさいことにそれが本当に普通で、なんか一生そのまま元気で平気なのもいるにはいる。
・ストレスに不快感を感じるとは限らない。個人的には寝る前の一日に対しての充実感も、疲労感の肯定的評価だしな。
筋肉痛が一番わかり易い例かな。筋トレを頑張った証拠とか、これから筋肉が増えるとか、そういった肯定的評価がされることは多いだろう。
燃え尽き症候群しない人
・不燃物。
Kahn(1978)は,「理想を言えば,(ヒューマンサービスの現場では)燃え尽き症候群しない人を採用すればよい」 と述べている。
もちろん, これは逆説的な表現で, ここで言う燃え尽き症候群しない人とは, 定型的なサービスの発給を常とし, 何か問題が起こると, いわゆる 「マニュアル的な対応」 で事を処理してしまうような人たちを指す。
彼らは, 確かに, 消耗することはないが, 相手から信頼され, 感謝されるサービスを提供できるかと言えば, サービスの量はともかく, 質はあまり期待できないかもしれない。
www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2007/01/pdf/054-064.pdf
要するに対人サービスの質と、燃え尽きるリスクはトレードオフの関係にある。
燃え尽き症候群が、人に対して熱心に、人間的な対応ができる者がそれをし続けた成れの果てだと考えると、残念にも思える。
まぁ結果だけ見ればやりすぎたというか熱心すぎたのは否めないのだろうが。
・ただ文面的に現場の裁量で最善をやれってのが当たり前になってるようなこうなんかもにょる。環境的・システム的な問題隠れてないかこれ。
サービス業に限らず、「仕事ができるところに仕事が来る」のが当たり前の認識になっている。個人営業なら結構なことだが、雇われの身の話でこれだ。挙げ句光栄なことだ、ありがたがれ、みたいな。
やってる側もやらせてる側も、自分が潰される/潰そうとしているとは気づいてないだけのかもしれない。
メモ
「共感」の使いすぎか
・人間の脳内の神経回路の内、共感する部分と分析的思考をする部分は別々にある。
これらは片方が活発になるともう片方が抑圧されることがわかっている。
まぁ簡単に言えば、辛いことがあって泣いてる人でもいたとしよう。心からそれに同情するのと、こいつ本当に泣いてるのかと疑うのとは同時にはできないだろう。後からはできるだろうが。b)共感と分析って、言い方変えれば同意と疑念だと思う。同意するなら疑念を持てない。疑う限りは同意はできない。
燃え尽き症候群のように片側だけ酷使し(今回は共感部分)、もう片方を日常的に抑圧し続け、やがて酷使している側が「燃え尽きた」場合、どうなるか。
これが仕事だった場合どうだろう。分析的思考では共感能力は行えない。瀕死の共感能力を使い続けるしかない。それが日常で、それがずっと続く状態。
・サービス業じゃなくても、「気配りができる(出来すぎる)人」は人と合うたびに酷使することになってしまう。当人が、それがやりたくてやっている、楽しいことだったとしてもだ。症状として出社拒否があったね。
つまり原因は「ストレス」というよりも「脳疲労」と捉えたほうが良いのではないか。そうだとした場合、自覚がないというか、日常を楽しんでいたとしても燃え尽き症候群になる可能性にも納得がいく。
筋トレが楽しいのと、疲れるのは同時に起こり得るわけだ。故障のリスクも変わらずある。これが「気持ち」の問題になった途端に、楽しいのに疲れるなんておかしい、なんて解釈になりがちで。
どれだけ楽しいことだろうが、毎日ぶっ続けは無理だろう。しかも今回は二本の足の内の片方しかロクに使わないで歩くような状態だ。
一番現実的な予防法は、恐らく「上手に休憩すること」ではないのか。そのためには日頃何を酷使しているのか知らなくてはならない。
その他
・「仕事にやりがいを」と管理職や経営者が言ってる場合、「お前が仕切ってる限りどんな仕事内容でもやりがいはなくなる」というケースはあり得る。「やりがいを感じられない」のが、労働環境の悪さによる個人的達成感/職務効力感の低下の可能性。
このようなことを言っている者に「給料上げろ」とのヤジが真っ先に飛んでいくあたり、労働環境は全体的に悪そうだ。
・医学的に使われる症候群やシンドロームとは、「原因不明だが同時に起きる一連の症候(病的変化)」を意味する。
「なんでか知らんがああなる人多いよね」みたいな感じ。
シンドロームの本来の意味は「同時進行」であり、同時発生や大勢に確認できることを意味する。
・バーンアウト burnout 自体が燃え尽き症候群を指す。他には疲れ果てること、極度の疲労、あるいは熱損傷を指す。
表現としてかなり適切だろう。実際にやり過ぎによる燃え尽きだから。
・個人的には、やる気のある者が突然こうなったから燃え尽き症候群って言われているだけで、そうじゃなかった場合、「ブラック企業でうつになった」というのと大した違いはないように思える。
ただ、燃え尽き症候群の場合は自らの行動によりこのようになることが、比較的多いと言える。問題のない職場環境でもなり得るし、自分で予防できる余地も大きいだろう。
[amazon asin=”4781910696″ kw=”燃え尽き症候群”]