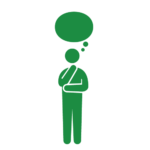- 学習時の目的や方針が違うよ。他人には飲み込みが早く見えるだけの場合もあるよ
- 飲み込みが悪い人が自爆していることもあるよ
- 飲み込みが早くなくても構わないこともあるよ。自分に何が必要かは考えようね
・「飲み込みが早い」と言う場合、「手早く習得/学習した」というニュアンスが強い。課題の習得や理解、学習能力が高いこと。
飲み込みが早いと言われるのは、褒め言葉と受け取っていいだろう。似たような言葉は色々あり、
- コツを掴むのが上手い
- 身につけるのが早い
- 理解が早い
- 吸収が早い
- 成長が早い
- 覚えが良い
などとも表現される。
「頭の出来が違う」「才能」などとされることもあるが、大体はそうでもない。
・飲み込みが早い人は大別して
- 素直に教えられたことを吸収する
- 目標に対して効果的に学習する
の2タイプがある。
・評価者からは、飲み込みが早い人は「教えたことが身についている」と見えている。なので基本的には教育役が生徒役に使う場面が多い言葉。
つまり他者からの評価が軸となる。このため努力による妥当な成長でも、他より早けりゃ「飲み込みが早い」とは言われる。
このため「飲み込みが早いように見えるだけ」な事柄も今回は含める。
例えば影で努力をしていた、復習をしっかりやっていた、他に似たようなことを学習/経験していたからこっちで楽ができたなど。
・単に飲み込みが早いだけの場合は、スピードが早いみたいなものなので、事故る時は事故ります。なので飲み込みが早いだけで「優秀」ともならない。
例えば思い込みが激しいとか、知ってることと同じだと判断したけどそうじゃなかったとか。
これを防ぐためにはある程度の自己監視能力などは必要で、逆に「自信」なんて持ってると暴走の余地もある。
・ 分からなくても飲み込んで、先に進んだほうがいい場面も多い。逆に「飛ばしてしまった」ことになり、後で後悔することも有る。この区別をつけることは必要。
学習内容の内で「主流」と「傍流」の区別がつけれることは、飲み込みの早さの素質と言えるだろう。前者は遅延してでも理解する必要がある。後者は後からでいい。
主流と傍流の見分けについては彼らが優れていることもあるが、飲み込みが悪い人が自爆していることも多い。不要なこだわり、完璧主義、思い込みなど。
飲み込みが早い人の3つのタイプ
- 素直に吸収する、飲み込めるタイプ。
- 要点を抜き出して効率的に習得できる、見切りタイプ。
- 他人からそう見えるだけでやることやってる(その手順には手慣れている)、堅実タイプ。
素直に吸収する「飲み込める」タイプ
・一番「飲み込みが早い」という言葉のイメージと一致する。言い方を変えれば「上手な丸暗記」。
これは、「どれだけ素直に受け入れられるか」にかかっている。マニュアルや信頼できる人からの教育が相手ならば有効だろう。
イマイチ信用しきれないようなら、疑っておいた方が正解な気もするが。
飲み込みが早い人は「飲み込める」人
・素直に真似できるかどうか。素直にやってみることができるかどうか。素直に「そういうことだ」と納得できるかどうか。
言葉通りに飲み込む。疑問を持たずに素直に受け取るとも言える。
一見すると疑問は持ったほうが学習としては良さそうだが、疑問の持ち方の問題や目の前のことを学習するにはその疑問はまだ早いこともある。
・飲み込みが早い人は結果を得ることが目的なので、お手本を、あるいは目標を「再現/実現」しようとする。つまり「理解」は後回しになる。
これは一見不実だが、動物としての学習は「模倣(つまり素直に真似すること)」がベースであるため効率がいい。まず出来るようになること。
意図していないこともあるが、「何ができたら良いか」という目標の明確化を行っている。
学習スピードが速い人は脳の活動が少ない
・カリフォルニア大学の実験では、物覚えがいい人ほど脳の前頭皮質(前頭前野)の活動が少ないことがわかっている。
これは物事をしっかりと計画する時に使われる部分。他にも意思決定、社会的行動、反応抑制、行動の切り替えなど多岐にわたる。このため雑に理性や人間性の部分だと言われる。
物覚えが良い人ほど、ここの活動が少ない。高度で複雑なことを頭でやっているわけではなく、素直に飲み込んでいると言える。
・「脳の活動が少ない」と言えば一見バカっぽいが、「無駄なことをやっていない」と解釈すればいいだろう。逆を言えば余計なこと考えてるとそれだけ物覚えは悪くなる。
研究者はこのことからいくつかの認知ツール(脳機能)が学習の妨げになっている可能性を見ている。
・余計な脳の機能を素早くオフにできる人が、飲み込みが早い人だとされている。
反対に飲み込みが悪い人は、頑張りすぎや考えすぎが原因で学習に不要な脳機能が活発になっているとされる。「気合の入れすぎ」とか「力みすぎ」って言ったほうが良いだろうか。
このような「脳の過活動」が原因の不調は割と多い。少なくとも「学習の時間」だけは素直な気持ちで取り組んだほうがいいのだろう。
余計なアレンジ/思い込みをしない・経験からも学ぶ
・余計なアレンジや思い込みをせずにそのまま自分に取り込める人。
例えば料理がいつまでも下手な人は、レシピ通りにせずに大抵余計なことをやる。
やれ強火のほうが早く火が通るはずだ、調味料の量はこのくらいでいいはずだ(目分量)、みたいな「こうであるはずだ」または「自分はわかっている(と思ってるだけでわかってない)」というのが多い。
この上味見もしないのは「うまく出来てるはずだ」ってところだろうか。
これらは実行のための知識の中に推測が混ざっていると言わざるを得ない。挑戦としては結構だが、失敗してもフィードバックしてないあたりただの「思い込み」だろう。
・何よりも恐ろしいのは、「同じ失敗をし続ける」ことだ。塩を目分量で入れたら入れすぎた。じゃあ次は控えめにするかと言えばそうでもなく、計るかと言えばそうでもなく、また同じくらいぶっこむのはいる。
思い込みで動き、現実からのフィードバックは得ていないように見える。それやるなら習得してからにするべきだが、何故か習得前にそうする。「余計な脳機能が働いている状態」にも見えてくる。
・飲み込みが早い人なら一度の失敗で懲りるだろう。というか最初から計量してから入れそうなものだ。
フィードバックや「教訓」を得られているかどうか、という話でもあるのだが、どうも極端に飲み込みが悪い人は一つ一つの工程に対して「やり終わったら終わり(後は知らない)」という感じで、結果(身についているかどうか)を全く気にしてない傾向が強い。喉元過ぎれば熱さ忘れるみたいな。
つまりここでも結果を意識しているか/していないかの違いが、飲み込みの早い遅いにはっきり出ている。
守破離
・物事の修行の段階について、守破離という概念が有る。これも「まずは素直に飲み込む」ことを説いている。
- まず教えられたことを守る。
- 次に、他の知識を取り込んだりして枠を破り、発展させる。
- 最後に、それらから離れ独立した、新しい独自のものを確立させる。
・「守」の段階は、「私意を差し込むことなく基本を身につける段階」であり、これがその後のベースとなる。いかにこの点をしっかりと、かつスムーズにやるかは飲み込みの速さに直結するだろう。
この「私意を差し込まない」ことは、脳波としても観測されているだろう。先程の、「物覚えが早い人ほど学習時に前頭前野の活発が少ない」と。
逆にどう見ても初手で「破」とか「離」とかやっちゃってるのがいたりする。まぁ何かしらそこから生まれるかもしれないが、少なくとも「習得」というより「参考資料」の扱いだそれは。
関連:
_理解力がある人と守破離/習絶真
中国語の部屋
・「中国語の部屋」という思考実験がある。
その部屋に、中国語で書いた短いメモをドアの隙間から差し入れると、中国語で書いた返事のメモが返ってくる。当然中にいるのは中国人だ、と普通は思う。
実際には中にいるのはイギリス人で、中国語はさっぱりわからない。メモに書いてあるのは文字ではなく「記号」だと思っている。
ただ「この記号の並びにはこう返せ」という膨大な量のマニュアルがその部屋にはあり、そのとおりにしているだけという話。
・このイギリス人は、記号を元に記号を書いて送り返していると思っている。部屋の外からは「中国語のメモに中国語で返事を返している人がいる」と見える。
つまりは意味がわからなくてもできるし、他人には「分かってるからできる」ように見えるという話。加えて言えば、「出来るようになるためには、分かる必要はない」。ただし、ものすごく落ち着かない。
・中国語の部屋に対しての反論で面白いのが、イギリス人+マニュアルという部屋全体を一つとして見るべきであり、その場合この「部屋」は中国語を理解していると言える、というものである。
スマホを持っていれば、「あなたは遠く離れた人と会話することが出来るか?」と問われてもYESなわけで、しかしこれは「人間」の生物としての能力ではないだろう。
要するに、飲み込みの速さを気にするあまりに、無意識に「自分の能力」という枠に捉えられていないだろうか。自分を補助する「道具」を作ることを考えてもいいかもしれない。
要点を抜き出す「見切り」タイプ
・頭が良さげに見える。ただ特殊な視点や手順だったりで、本能的に受け付け難い面はある。総合的な経験値が物を言う部分も大きい。一朝一夕でこうなるのは難しいだろう。
飲み込みの早い人を、一部は嫌う
・「飲み込みが早い人」は、一部には嫌われる傾向にある。理由は簡単で、「ズルい」ように見えることがあるからだ。彼らを好まないのは、手段や手順にこだわる生真面目なタイプが多い。
あるいは物事は「苦労という名の努力」で達成されるべきであり、「工夫をする努力」による達成は認めない、というような信念の持ち主。
「要領がいい」なんて言葉は、時に「お前ってズルいよな」のようなニュアンスすら含む。これも同上。
・飲み込みが早い人は最短距離を狙う事が多い。効率的、効果的な方法・手段を考え、用い、習得や達成を手早く行う。他に多くは求めない。端的に言えば彼らの多くは「ドライ」である。目的だけがあり、真っ直ぐそれに進む。
反面一般人は、それと比べれば過程にこだわり、手順にこだわり、充実感を求め、達成感を求め、成長を求め、失敗を恐れ、不安により保険を打ち、色々と足かせがある。
目的以外のやること・注意を払うことが多い(モチベーションに関わるので一概にこれが無駄とも言えないのだが)。
・ゴールまでの道のりが初めから違う。「やろうとしていること」自体が違う。むしろゴールだけ同じで他がほとんど違う。
この違いは飲み込みの早いか遅いかに直結する。余計なことをやってるかやってないか、目的に対して集中してるかしてないかの違いだから。
まぁ色々求めても良いんだが、早さで競おうとするのは無理がある。目的のために「どこまで割り切れるか=専念できるか」という話だ。専念しようとするのなら、それ以外の期待は雑念に近い。
・ただ、どうも飲み込みが遅い、要領が悪い人は、飲み込みの早い人に見られる「自分のための理解、自分のための工夫(覚えるための工夫)」そのものを、「やってはいけないこと」と認識しているようにも見える。
無駄に客観性を重視したり、後で怒られるような「勝手なこと」だと思っているような。学習や習得に「作法」があり、それを守らなくては全部「ズル」と思っているような。重症例だと年号の語呂合わせすら「不真面目だ」とするのもいる。
・「なぜ」気に食わないのか、「なぜ」ズルいと思うのかは、自己分析したほうが良いだろう。何かしら自分の側にこだわりがある。
自分にそう思わせる「こだわり」は大切なのかもしれないし、無駄に遠回りな道を当人に選ばせたりしているかもしれない。
飲み込みが悪い人の無駄
・飲み込みの早い人を一部は嫌う。逆を言えば、「飲み込みの速さ」を演出する要素自体に対して、人が毛嫌いするような部分が含まれていることになる。
・まず何よりも「無粋」というのがある。最短距離いくものだから、苦労やなんやかんやを乗り越えるなんてドラマティックさはない。
逆を言えばいくらか普通の人は自分が「勝者」あるいは「困難を克服した者」になるイメージを課題に対して期待する。努力のナルシシズムとでも呼ぼうか。
・体育会系的な「苦労の報酬としての成功/達成」というイメージを持つ者も多い。飲み込みの早い人の「最適解とその結果」ではなく。
尤も、動物にもすぐに報酬が得られるのにわざわざ遠回りして報酬を得る傾向があるらしく(コントラフリーローディング)、本能だと思うが。逆を言えばこの機能が理性的ではない可能性がある。
せっかくやる気を出したのにあっさり終わったら、不完全燃焼のような気分を味わう時もある。まるで課題に対して感情面での報酬を期待していたかのようだ。
・人は変化を嫌う傾向があるが、同様に自分の成功や達成も避けたいと思う面がある(ヨナ コンプレックス)。このためガンガンいく飲み込みが早い人を見て落ち着かない気持ちになるというのもあるだろう。
分析・研究している
・ティム(ティモシー)・フェリスという実業家で作家で、他にも色々やってる人物がいる。私が知っている限り、飲み込みが早い人物と言ったら彼だろう。
おかしなレベルで飲み込みが早い。散打(格闘技)で素人の状態から4週間くらいの練習で世界王者になった。素人レベルから一ヶ月くらいでダンスの大会に出て、タンゴにまつわるギネス記録を達成した。
加えて日本語を含めて6ヶ国語を話せる。動画内でも少し使ってるね。かなり流暢だ。とんでもない内容だけどね。
・その習得の早さのコツを水泳を通じて説明しているが、まず「システムの理解」をした。次に実践。
散打で世界王者になった話も、ルールを研究し、ルールの穴を付くような戦い方をしたらしい。それで勝っちゃったわけだから、まぁ前述の通り「ズルい」と思われるような面はやっぱりあるわけだ。相手サイドからの批判もあったという。
・見切りタイプの飲み込みが早い人で、「数撃ちゃ当たる」とか「猛特訓をする」みたいな量的な努力を初手でする者はいない気がする。
それをやるのは何をやったら良いのかはっきり分かってからであり、その前に理解/分析に努める。努力に於いても「量より質」の傾向はかなり高い。質や方向性を見極めてから量。
ただし方向がわかってからは行動量も多い。総じて良質な経験値を大量に取得できる。
逆に経験値の悪食が、要領が悪い人。これはとにかく動いてみよう、というのではなく、「これで良いはずだ」という誤信念によりただひたすらに悪手を繰り返す形で。
・ティム フェリスで言えば、それほど人間離れした内面を持っているというわけではないだろう。まぁ、元々は。今はどうだか知らんけど。躁鬱気質で、自殺を考えたことも有る。
ただ、「闘争心」は大事だと思っているようで、マインドフルネスをやる際に「闘争心が消えてしまうのではないか」という心配があったそうな。やってみたらそんなことなかったそうだが。
闘争心と言っても、相手が他人とは限らない。ストア哲学(「ストイック」の語源)に造詣があるから、恐らくは自分や課題に対してだろう。
ちなみに動画内でも言っているが、交換留学で日本に居たことがある。その時「過労死」の概念を知ったとされている。不名誉なことに、「過労死」って日本語はそのまま外国でも通用する。そのくらい日本には多い。
彼は後に本を出版し、その初の著書は35カ国で翻訳されるベストセラーになるのだが、タイトルは『「週4時間」だけ働く。』である。影響はあったのかもしれない。
よく観察している
・飲み込みが早い人は学習意欲は高い傾向がある。
人がやっていることに興味を持ったり、自分がそれをやったらとシミュレートしたり。実際に課題が与えられる前に、心の準備も、頭の準備もしていると言える。
・手順の一つ一つをおぼえるというよりも、全体の心的イメージを作るような。表面だけなぞるのではなく、そこに至る背景や内面を知る。例えば手順そのものではなく、「なんのためにそれをやるのか」を知るなど。
一見すると「飲み込める」ことと逆に見える。遠回りに見えるかもしれないが、これは「事が始まる前」の態度であり、他の人がまだ何も考えていない時に、飲み込みが早い人はこれをやっているという話。
これは「予習」に近い。あるいはリハーサル。その分差は付く。真面目な人でも毛嫌いせずに行えるポイントでも有るだろう。
・心的イメージは軽視されがちだが、限界的練習に於いてはこれを作ることが最大の目的ともされる。
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/1866/”]
「見る」と「観察する」
・自分に関係ないと思った物事は良く見ないから覚えない。ただすれ違っただけの人の顔なんて、いつまでも覚えてはいないだろう。
「明日は我が身」みたいな感じで他人の話が自分に関係有ると思ったら、よく見ないと困るからよく見る。結果覚える。
・人は「見る」と「観察する」の2つの見方ができる。見る方は普段の見方。
例えば学校の授業で隣の席のやつの顔を写生するとして、変な所にホクロがあるとか、そういった細かいことに初めて気づくことがある。毎日目に入る顔なのに、ここで初めてそれに気づくわけだ。
この例での写生のように「見るだけじゃ済まない」という時に、初めて「観察する目」で見れるようになる、ということは多い。
・推敲の仕方の一つとしても、一文ずつ一字一句丸写しにしろ、ただし見ながらやらずに見て覚えてからやれ、みたいなのがある。相当めんどくさいが。
これもほとんど写生とやってること同じなわけで、やっぱりこれで「目が滑る」ことで見逃していた違和感などは気づいたりなどはある。時間がかかりすぎるのが欠点だが、精度はやはり高い。
・ノートの書き方に於いてデジタルか手書きか、というのは長く続くトピックだが、デジタルで学習効率が落ちる主な理由として「頭使わないでできちゃうから」というのが多くの研究で目にする指摘だ。
反対に手書きは「遅い」ため、頭の中で書くべきことを吟味し、必要ならば圧縮などをする必要がある。これがそのまま理解度を上げるための一助となっている説などもある。
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/1783/”]
・脳は結構でしゃばりで、普段の認知には補足がかなりはいっている。
例えば老人は段々目が悪くなっていくものだが、視界がかなり狭かったり、虫食いのように部分的に死んだり、片目が全く見えなくなった上で、「当人が自覚がない」という事がある。脳が補正しまくるもんで、見えてるつもりになるため。
錯視でも、白黒画像に色がついて見えるなどがある。
↓こういうの。
色がついて見える分お得に思えるかもしれないが、「色が見えている間は白黒画像が見えていない」ことに考えを向けてもらいたい。これすなわち分かったフリ、思い込み、勘違いの状態。そしてこれが普段の状態。
時には注意深く、歩みを遅らせる必要もあるということ。
コツや要点を見つけるのが上手い
・コツや要点を見つけるのが上手い。これは覚えるべき物事の量が減る。ちなみにコツの語源は「骨」である。
概要としての全体像と、注目するべき要点の構成。この2つで頭の中に理解の骨組みが出来上がる。
建物の間取りを覚えればいい話で、家具配置や本棚にある本のタイトルまで覚えようとするなら無駄になる。
何をどこまで覚えるかを把握する必要は有るため、やはりここでも目的意識は必要となる。
・コツや要点は割と教えてもらえるかも知れない。こうすればいい、ここを気をつけろ、ここは間違えやすい、ここは抑えなければならない、と。まぁ周りも困るから。
「そこしかやらない/気をつけない」人とかはいるわけだ。これは要点「だけ」、それも教わった部分だけ抑えている状態。
全体像を持っていないと、その状態が危険だと気づかない。
・「コツ」は他にも転用ができることが多い。例えばティム・フェリスもそうだったが、言語に於いてのコツを押さえれば6ヶ国語の習得に繋がるなど、その後に大きく影響を及ぼす。
・この様な物事の構造やルール/システムの把握(メタ知識や知識の構造化など)の総量は、以降の飲み込みの早い/遅いにもつながることになる。
卑近な例で言えば、PCも含めた大抵の家電は、パワーボタンに同じマークが有る。動画プレイヤーの再生、早送りなども各プレイヤー共通して同じマークだろう。これらを覚えれば、同じ「初めて見たもの」でも、理解度は最初から違う。
完全コピーをしようとしない
・要点を押さえようとする態度は、裏を返せば初めから完全再現や完全なコピーなんてするつもりがないということでも有る。当人がどんなつもりかは知らないが。
ティム・フェリスの散打の話も、プレイヤーとしては十分な習得だったが、拳士としての振る舞いは最初から身につけるつもりはなかったのだろう。なんか文句言われてたっぽいし。
・観察力・洞察力に長けるということは、覚える量のスリム化と、思い出す時の正確さに繋がる。
「覚える前」に情報を分析し、取捨選択、整理している。「シンプルに捉える」とも言える。量が減るからすぐ覚えられる=身につくのが早い。さらに他に転用できる余地がある。
・極端に飲み込みが遅い人などは丸暗記の傾向+完璧主義な傾向がある。教えられたことを「絶対」として、何も欠けずに覚えなくてはならない、としている。覚える量としては最大値になる。
反対に飲み込みが早い人の場合、圧縮や簡略化を行う(これも今までの経験や知識が物を言う)。情報の要点だけを見切り、そこだけ押さえればいい。覚える量としては最小値になる。
彼らは一見記憶力がいいように見えるが、こういった圧縮や簡略化を自然と行っている。特徴をピックアップするのがうまい。「やるべきこと」の量からして違う。
これはノートのとり方などでも現れることが有る。「丸写し」をするか、「後で自分が使いやすいように書く」かで。
・一方で、飲み込みが遅い人も圧縮や簡略化を行っている場合もある。
ただそれは不可逆圧縮(元に戻らない)に近い。要点を見いだせなければ、重要な部分を切り落としてしまう余地がある。これではただ単に雑なだけとなる。
忠告しておくが、飲み込みが早い人と「早さ」で競わないほうがいい。クオリティが更に犠牲になる。
・シンプルにマインドマップで分かっているだけ書き出して、つなげてみるのも有効だろう。抜けが有るなら気づけるし、十分だと思うなら飲み込めたということだ。自己評価でだが。
要点を言語化する
・飲み込みが早いというのは「身につける」に近い意味を持つ。このせいで経験的、感覚的なものと捉えられる。間違いではないが、「頭での理解」をしなくていいわけでもない。このために要点の言語化は必要になる。
飲み込みが早い人は「習得」するつもりなのだが、飲み込みが悪い人は「特訓」するつもりなことが多い気がする。そりゃ数こなす思考になる=手間がかかる=飲み込みが悪いと評される、となる。
・人間の頭の中は当人が思っている以上に「狭い」ため近視眼的になりがちで、その分構造化が難しくなる。群盲象を評す。間近で見るから全体が見えづらい。
言語化は、記録、保存の助けとなる。この分頭の容量が節約できるため、全体像や各要点の繋がりと言った構造化にも手が届くようになる。
・前述のマインドマップなどは、頭の中の可視化と整理を目的として行われることが多い。準備や整理、まとめ。ノートをまとめるのと違うのは、見聞きしたものではなく自分の頭の中がメインであること。
可視化されたそれは、そのまま自身の理解度の現れでもある。不足や不備や不審点を見つける=復習や予習の課題発見にもなる。なのでなるべく実践を前提として書いたほうが良いね。
このようなことを試みていれば、自ずと言語化、可視化は為され、知ってることはもちろん、「知らない」という事実すら活かすことができる。
疑問の解消に拘る
・その疑問が「要点」だったら儲けもの、そうじゃないなら以降は気にしなくていいと判別できる。
・聞くのもタダじゃない。教えられる側が「説明を遮っては悪い」と遠慮して、結果教師役が一方的にしゃべるだけで終わる、というパターンも多い。
「説明してもらったんだからわからなきゃいけない、でもわからないからわかったふりをしよう」というケースも有る。ただこれでは教えた意味がない。相手にとっても不実となる。
・教師役が遮られることを露骨に嫌がったり、知ってることを「暗唱」すればそれを聞いた奴は出来るようになると思い込んでいたりとかもある。
これでは一方的な演目に終わりやすい。これらの点は当人の対人スキルや、性格、人間関係の問題なども影響はある。
・本来は教える側は伝えるというタスクが、教わる側は理解するというタスクがあり、己の目的を果たせば相手も果たしたことになるため利害関係は一致している。
ただどうも人間の動物的な本能がこの辺りをおかしくしていることもある。一人で喋ってると段々と「演説」になってしまうとか(もちろん聞き手は「聴衆」と化す)、教わることより「会話している雰囲気」を優先して分かったふりをしてしまうなど。
・どちらかと言えば、頭に浮かんだ疑問を無視することのほうが難しいだろう。ただし「後でやろう」としてそのまま疑問の解決を後回しにすることからの、
- なんとかなったのでやっぱいいや
- 何が疑問だったのか忘れた
- そんなことをしている暇はない
など、「結局何もしなかった」ことによる、学びの機会のロストは多い。
疑問とは自分の理解や状況が怪しいかもしれないという疑いであり、確認・復習しておいたほうが良いという「気づき」であるのだが。
自分の記憶力に頼らない
・記憶しようとするのではなく「記録」として残す傾向がある。そしてそれがうまい。
・「要点」を見つける能力が高いことを示す。
メモやノートをしっかり取るというのは、「後で見返して何のことか分かる」レベルが求められる。この上で、素早く、端的に書くことが。
つまり観察・洞察力で要点を見つけることに加え、省略する力が必要になる。「いつどこで必要になるのか」の推測力も。
・コーネル式というノート術が在るが、あれも「理解してから書け」またはなるべく簡潔に箇条書きなどで書き写せとされる。丸写しは頭を使わないから。
ひたすら書くタイプの勉強法もある。しかしやることが単純な分、回数が必要だ。一回やって十分な成果が得られるかは怪しい。
・これらは使ってれば伸びるタイプのスキルではある。少し拘ったほうが後々得だろう。
明日の自分は他人
・「今わかる書き方」は、数分後には「わからない」となっていても別におかしくはない。
人間は一時的な作業領域を利用して物事を理解している(ワーキングメモリ)。これは長くても数分しか維持できない。
書いたときには一時記憶で「書いていない部分」を補足して理解できるが、それが消えたら何書いてあるのかわからない、となる。
逆に「書いたら安心」「困った時だけ見ればいい」という使い方(=自分のメモ能力を知る機会が少ない)は、その使い方自体はアリだがちゃんと出来てるかどうかは再び読むまでわからない。
能力不足だった場合、メモのとり方を上達させる必要性に気づかない。土壇場で過去の自分が裏切ることになる。
・これらのメモは「自分が重要だと思った知識」の集大成だ。「自分なりの要点」か、それに近いと言ってもいい。これらをまとめることは、自分の頭の中の整理にも繋がる。
・メモの内容を2つに分けるとすると、脳の拡張領域としての記録と、アーカイブ的な「後で使える形」が理想なものとがある。前者としてなら走り書きで構わないが、後者を期待して前者を行えば失敗する。
まとめたものを教師役に確認してもらえば、自分の理解が正確か否かも双方わかる。
関連:
_メモをとる時の注意点
悪い意味での自分を信じるようなことはしない
・優秀な人間ほど、自分の記憶をあまり当てにしていないように思える。
例えば物をよく無くす人の方が、「どこに何があるか自分には分かる」とか言う。無くしたら「次からは気をつける」「もっと注意する」と言う。
実際に物をなくさない人は、置き場所を決めて、いちいち覚える必要がないようにしている。まぁその分他人が勝手にいじったりしたら怒る。
前者は「能力」で解決しようとし、できていない。
後者は「システム」で解決しようとし、できている。
やはりここでも過程(やり方)に拘るか、結果に拘るか分かれている。
・「成長」という概念が時に足を引っ張る。工夫すりゃ済む話を「身につける」「練習する」という回りくどいタスクに変えてしまう。
結果何度も繰り返し失敗するようなことを自分からやったりだとか。「練習」をしようとして。
前後を把握している
・構造化。これも要点を見つける能力に関わる。
・全体から見てその作業がどんな役回りなのかの理解。
その作業の前の工程、後の工程を把握している。これをすれば今の自分のタスクのスタートとゴールのイメージがかなり正確に作れる。
ここを抑えれば、「次で困ることになるから慎重に」「ここを前の工程でやっておかないと困るから確認しないと」などのポイントが分かるようになる。或いはここを気をつけることにどんな意味があるのか、という理解にも繋がる。
・理解が進めば、それだけ適切な行動が可能になる。無駄のない仕事ぶりとなる。「必要な力加減」がわかる。それ以上に時間や手間をかけて時間を無駄にはしない。
情報同士のリンクからの発見や仮説
・情報同士をリンクすることが、理解を深めることになる。
例えば、
1.関西出身かつ著名な小説家が多い。
2.関西弁は「感染する」ことがある。
3.関西人が下手な関西弁の真似を聞くと不快に思うが、これは「音痴な歌を聞かされている状態」に近いとする説がある。
この3つだけだと「関西」「関西弁」以外に繋がりは一見見えない。
3だけで「関西弁が音やリズムとしてキレイである可能性」が出てくる。逆説的にね。
こうなると、2は「音やリズムがキレイだから感染しやすい可能性」が出てくる。流行りの歌が耳に残るように。
追加で、
4.7~8割程の人は本を読む時、頭の中で「音読」しているとする説がある。
を加える。
ここから、1は「文章のリズムやテンポのセンスが高いからである可能性」が出てくる。
こうなると良い文章を書きたいなら、音読を想定して、音やリズムを意識して書いてみようか、程度の仮説は立てられるだろう。
なお私はやらないめんどくさい。ついでに言えば方言って標準語と比べると大抵リズム特化になる気がするから別に関西弁に限らないと思う。ので1は正直怪しい。好きな作家で関西出身、てのはいるけれど。
ともかく、芋づる式に色々ぶっこ抜けたりする。閃いたり、理解したりと。
他人にそう見えてるだけの堅実タイプ
隠れた秀才タイプ。思うに天才よりも秀才のほうがいい。参考にしやすいし。
影で努力している
・特に今日学んだことのまとめや、今後やりそうなことの予習など。単純にやることやってるパターン。
これについては幼少期からの習慣であることが多い。知能はともかく、学習習慣は家庭環境の影響は大きかったりする。
基礎部分が頑丈になる。後は知識を追加していけばいい。更に強固となるだろう。
必要だと確定する前から予習に手を付ける
・「必要になるかもしれないから」が動機でもう予習を始める。これが重要なのは反対を想像してみればわかるだろう。
「言われてからようやく動く」のが、飲み込みが早いと言われることに近いか遠いか。
シンプルに「早く手を付けたから完成するのも早い」という話。競争で言えばフライングしてる。大体は張り合ったり嫉妬したりするのが勝手に競争としているだけなので、ズルではないね。ゴールの速さしか問われないなら有効な手段となる。
・一方でこのようなことをするのが嫌いな人も多い。必要だと確定する前に練習や勉強をすることが、単に損かもしれないからとか、金が出ないのに仕事のことやりたくないとか理由はいろいろだが。
ただし時間の投資は、勤勉さで才能に勝つ常套手段の一つでもある。質も問われるけど。
必要になってから動く方略は、遅延評価勉強法やパラシュート勉強法など実在するのだが、これは基本すでに忙しくて時間がない人間が効率的に動くためのものだ。
努力を隠す
・この上で、一部の人は努力を隠す傾向が高い。多く知ってるが、基本的に理由は「邪魔されたくないから」だ。
人目が気になるからというのも有るし、努力している人を見ると「抜け駆けしようとしている」とか騒ぐ不健全な仲間意識を持った者のせいでもあるし、「そんなことをしても無駄だ」と曰う選民思想や冷笑主義者のせいでもある。
うんまぁ、隠したほうが利口な気がしてくるな。
・結果、「いきなり化けた」ように見える。あるいは「初めからいきなりできた」かのように。
下地が自然とできていた
・予備知識と慣れに直結する。類似した経験がある、或いは類似した技術を習得しているパターン。
・同じ「始めて」だとしても、スタート地点は平等ではない。各々の経験により変わる。ドラクエやったことあれば、コントローラーに触ったこともない奴と比べればFFもやれるだろうって話。
・能力、性格から見てそれほどじゃないはずなのに、一定のカテゴリでだけ非常に飲み込みが早いなどの現象が起きる。
小学校のクラスでいなかっただろうか。ドッジボールやサッカーしか頭にないようなのが三国志や戦国武将にだけ異様に詳しいとか。
そういうのが複数人居たから聞いて回ったんだが、共通して兄か父親が家でその手のゲームしてたの横で見てたってさ。
彼らにとっては「知ってるゲームキャラが授業に出てきた」という感じになる。
他人が見れば「一を聞いて十を知る」となるだろうが、当人からしてみれば「知ってることと同じだった」ということになる。別分野(この場合はゲームと授業)の知識の流用。流用している自覚もないだろうが。
・これは才能は経験で補える、あるいは「再現」ができるということでもある。
飲み込みが早い人の特徴
・飲み込みが早い人の特徴として、
- 自立心、向上心、独立心が高い(成長する動機・欲求が強い)
- 要点を見つけることができる(学習量のスリム化、目的への効果的な努力ができる)
- やることやってる(実行力と、量による質のイメージの成長)
- 変な思い込みを持たず、素直である(思い込みに気づいて修正できる、余計なことをしない)
- 努力に対しての効果を考える(軌道修正)
など、頭の処理能力というよりは動機、目的、手法の差が大きい。何よりも目的にコミットする意識は高い。
・また、元からスタート地点は同じではないことが多い。
- 過去に類似した経験が有る
- 他の知識や経験からの転用
などはある。
裏を返せば、飲み込みが早くなりたいなら「習得/学習」という概念それ自体のコツや、自分に必要になる知識や経験を推測しての予習などで補える。
関連ページ:
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/1626/”]
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/1286/”]
飲み込みが早い人は「分かるかどうか」よりも「できるかどうか」
・アウトプットができるかどうかを意識して学習している。例えば自分が人に教えられるかどうか。自分がそれをできるかどうか。
誰だってそうだろ、と思うかもしれないが、案外そうでもなかったりする。
・そこらでよくある「悪い例」としては、
「教わったことをその場で暗唱できれば、人に教えられるし実行もできるはずだ」という勘違いだが、次の日当たりでまぁ事故起こす。
後で復習なりまとめるなりしない限りは。何せ他にもやることも覚えることも色々あるからね。埋もれるか、消えることもある。
・逆を言えば教える側にしても、相手が本当に理解してるかどうかの確認は簡単ではない。
だから「今覚えたことを説明してみて」みたいにアウトプットさせるなんてこともする。
(ちなみにこれらを省略すれば簡単に「わかりやすい説明」が可能だが、これは教えたつもり/わかったつもりになれるだけであり、娯楽としての雑学ならともかく学習としては何の価値もない。
実際、それらを見て自分に必要であると思った者にとっては明らかに「足りない説明」のため、彼らは自分で調べる。
まぁきっかけにはなるが、教材にはならんという話。)
・このため「後で人に教えるつもりで覚えろ」「自分がやる時のことを意識して聞け」などの教わる側の心構えが今でもある。
行動主義と経験値
・飲み込みが早い理由の一つとして、他よりも多く経験値を稼いでいるからだ。同じ一日でも密度が違う。
・飲み込みが悪い人は、方法や過程に拘る。大抵は不安感から来る用心深さであり、失敗したくない。
(日本人は遺伝子的には悲観主義が多いので珍しくもないが)
相対的に飲み込みが早い人は、不要な不安感を持たないか、自分の中のその感情に対処できる。その分必要な行動ができ、経験を積める。
(必要な不安や緊張も感じないのもたまにいるが、やっぱり事故率も高い)
・飲み込みが早い人と違い、それ以外の大抵は「納得してからやってみよう」「自信がつかなきゃやってはいけない」となりやすい。
「とりあえずやってみよう」とはならない。その分遅い。これは時間が減るということでもある。着手の早さと行動量で劣ることになる。
・「十分に勉強してから」というのは安定志向の慎重派としてはアリだが、必要な勉強量は見積もったほうが良いだろう。その「十分」が下手したら「永遠に」と同義かもしれない。
理屈の理解と、できるかどうかは別物。仕組みを全く知らなくても、「スイッチを押せば明かりがつく」ということは覚えられる。
学習するべきが「明かりの付け方」だった場合、明かりがつく原理を理解しようとするのは既に「脱線」になる。
こういった実用面での習得の場合、生真面目=飲み込みが悪いとなりやすい。実際に行き過ぎた完璧主義や度が過ぎた真面目さを「悪」とする意見もある。
横道を切り捨てるかどうかではない、優先順位としての話。横道を正道と間違えてはならない。冗談抜きで「後でやれ」ということに執着する傾向は、飲み込みが悪い人には多い。
大抵の人にとっては感情的にもスムーズとはいかない。「わかるんだけど納得いかない」みたいな感情が邪魔をする。なんとなくの不安感が湧く。
「理屈は知らんがどうやったら良いかわかる」という覚え方が嫌いだったり。
確かに理解はあったほうが良いが、「まず使い物になる=できるようになろう」というのを目指すのも悪くないはずだ。その後で理解を深めることもできる。
・普通の人はやってること、やろうとしている事自体に(相対的に見れば)無駄が多い。別の何かにそれが役立つことは確かにある。しかし「本命」がいつ身につくのかという視点だと、やっぱり遅くなる。
「今はできない自分」を受け入れ、いつか出来るようになると信じて行動する
・単純に行動した数が多い。行動を惜しまない。陳腐な言葉ではあるが。
大抵の場合、過剰な丸暗記や義務感につながるのは「失敗して怒られて恥をかきたくないから」という思いが強い。これは根深いものであり、誰もがいくらかは持っている。
一方、飲み込みが早い人はこの辺りを必要経費として織り込んでいる。自分は初心者であり、失敗することもあるだろう、と。その上で行動する。 もちろん予測できる被害に対して備えはする。
謙虚であり、アクティブでもある。この謙虚さから質問することにも比較的抵抗が少ない。
・平たく言えば、現状の「できない自分」をそれほど恥だとは思ってない。出来るようになるつもりでいるということは、今はできないことを暗に受容している。自分の成長性に対しての信頼もあるのだろう。だからこそ「今は」できない、と受け止められる。
一方大抵の場合は「わかっているふり/できるふり」を無自覚にしていることの方が多い。例えば全くの素人なら「サルでもわかる○○」なんて本を読んだ方がよほど飲み込めるわけだが、年や立場相応の小難しい物を初手で選びたがるのは多い。
(こういう本は多くの人の助けになっている。まぁタイトルが挑発的なのは否めないが。どの道「初心者用」を飛ばしたがる人間は割といる)
・ダニングクルーガー効果として有名だが、能力が低いほど自信がある。つまり馬鹿であるほど学習動機を持たないため馬鹿であり続ける。
対象に興味がない場合にも学習動機はないが、自分の「本命」に対して無能で自信がある状態は最悪と言える。
反対にその道を努力している人間ほど、実力に反比例して自信は一度下がる。自分の実力を知り、できないこと/わからないこと/知らないことの存在を知り、それらを意識しているから。最後に、実力と自信が一致するようになってくる。
・人の「理想の自分像」は、理想自己/義務自己の2つがある。
理想自己はそのまま「なりたい自分」。将来的なもの。
義務自己は「そうじゃなきゃならない自分」。今すぐできてなきゃいけない。
これらはそのまま、「目的」に対しても当てはまる。
前向きに行動できるのは持っているものが「希望」だから。失敗は元から織り込める。今の自分が「いつか」そうなることへの期待。
後ろ向きに失敗を恐れるのは、背負っているものが「義務」だから。出来なければ自分の価値が「下がる」ので失敗するわけにはいかない。このため「避ける」ことが選択肢に入る。
・皮肉なことに、今すぐできなきゃいけないと思っている方が伸びが悪くなることもある。焦りや緊張により。
動機が義務だからこそ「できるようになりたい」じゃなくて「できなきゃいけない」になるわけで。恐怖心が募るため、保守的になる。
その分努力や労力でカバーするので、表面上あまり問題にはならないのだが。
慎重なら慎重のままでいい
・この慎重さは悪いことでもない。事実飲み込みが早い人は派手にコケることもある。要は飲み込みが早い人の一部に「怖いもの知らず」なだけのタイプがある。
大量の経験を身体で覚えたタイプ。これも一つの「下地」であるから、他に適正が生まれたりはする。
・慎重派は、自分は逆に安定重視思考とか大器晩成なのだ程度に思っておいて差し支えないだろう。
実際、融資を募っておいて全然動かないもんで某組織心理学者は投資をしなかった学生4人が、後に大成した例がある。[efn_note] ワービーパーカー。10億ドル以上の企業価値を持つ。 [/efn_note] [efn_note] 独創的な人の驚くべき習慣 アダム・グラントのTED。ギバーとテイカーの提唱者。[/efn_note]
「この夏をそれに捧げたんだな?」
「いえ、失敗した場合に備え全員インターンシップに行きました」
「卒業したらフルタイムで働くんだよね?」
「いえ、念のために全員別の仕事にも付きます」
オンラインでメガネを売る会社の予定なのに、サイトも作ってなかったと。
後に、この時彼らは人々が安心してメガネの注文ができる方法を探っていたことが分かる。
要するに、直接的(わかりやすい)な活動だけで良いわけでもない。「準備のセンス」ってのは、多分ある。
・総じて「誰か」になろうとするよりは、自分の特徴を活かしたほうがいいかもしれない。
飲み込みの速さの本質の一つは事前の深い理解であり、すでにそれがあるからこそ別のことの飲み込みが早い。というパターンも有る。
この場合、本来はこの例のように地道な準備などが本質であり、パッと見のわかりやすい「すごさ」とは逆方向を向いている。
案外、慎重派の方が得意分野では飲み込みが早くなれるかもしれない。
・まぁ限度ってもんがある。慎重が度を越せば臆病であるし、怖いから正直やりたくなくて、最大限先延ばしする口実としての予習・準備をいつまでもする人もいる。
このような度が過ぎた慎重さは、自信のなさ、自己評価の低さ、失敗時の周囲のリアクションの想像上の恐怖などに由来していることが多い。
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/2041/”]
分かったふりをしない 理解度チェックをする
- 学習習慣の違い
- 飲み込みが早い人は自分が飲み込めたかどうかに拘り復習する
- 飲み込みが悪い人は「わかった」と思ったら終わり
・飲み込み=身につけるのが目的なので、飲み込みが早い人は「自分が飲み込めたか・まだ飲み込めてないか」は気になってくる。
どこまでの理解・習得がゴールかは目的によってそれぞれだが。
・飲み込みが悪い人の場合、飲み込めてないのに「理解した」と感じてしまう。なんとなく分かった、もう大丈夫、って思う。確認しない。これは大抵の場合「今はわかる」という状態で、後で忘れる。
忘却曲線という有名なグラフがある。これによれば「分かった」と思った20分後にはその内容の58%しか頭に残っていない。一日後には34%。一ヶ月後には21%。これは法則性のないランダムな単語での調査であり、体系的な学問などではもうちょっと忘れにくいと言われているが。
陳腐だが「人は忘れる生き物だ」というのは正しい。初日がかなり最悪で、7割前後は忘れるのが人間である。「わかった」と思ったことがこのザマだ。記憶力を自慢するよりも素直に復習するのがよほど要領がいい/飲み込みの早い人間の所作だろう。
「人は忘れる生き物だ」と理解しているかいないかで復習のモチベーションも変わる。天然ではなく秀才的な飲み込みが早い人の場合、身につけるのが目的なので始めから復習はメニューに入っている。
・総じて学習習慣の違いとして、行動が大きく分かれる。
ゴールが違う
・飲み込みが悪い人は、
- 何を教えられてるか、自分がどうなれば良いのかがそもそもわかってない(話聞いてるだけ・本読んでるだけ・周りについて行ってるだけ)
- 実際の行動に紐付けて聞いてないから、どこを覚えれば良いのか分かっていない・どこまでできればいいか判断ができない
などが見られる。つまり受動的。受け身。
・飲み込みが早い人は前述の通り目的に対して能動的。アクティブというか、アグレッシヴというか。なのでやる気があるように見られることも多い。
・飲み込むべきものを宿題のように「与えられた課題」ととるか、自分の目的のように取り組むか。
モチベーションの問題もあるのだが、それ以上に「終われば良い」と「覚えなきゃ意味がない」という認識しているゴールの違い。
身につける・行動するつもりで見る/聞く
- 話として聞いているだけでは身につかない
- 後で誰かに教えるつもりで聞く
- 後で自分がそれをやるつもりで聞く
・目的意識の話。飲み込みが遅い理由の一つとして、「実行することをイメージしていない」事が挙げられる。簡単に言えば、学ぶことの使い道を考えていない。
最終目的が「できるようになること」を前提とした場合、実行することを考えていないのは、何が必要なのかわからないこととほぼ同義となる。迷子。
・「話」として聞いて「言葉の意味はわかった」とするのは、頭でだけ分かっている状態。実際にできるかどうかは怪しい。
一方、実行イメージをする場合は「手順」として聞いて、「実際に出来るかどうか」を考えることになる。
これにより自分はここからわかってない、ここの説明は飛ばされた気がする、というのはわかる。「このまま説明が終わられたら自分がやる時困る」という形で。
実践を意識することで「退屈な勉強」から「事前説明/リハーサル」に近い感覚になる。聞きながらすでにシミュレートしている。聞いたことを役立てるつもりでいるとも言える。
・これは学生の勉強に於いても言える。例えば「テストに出るか」「出るとしたらどのような形か」を気にして授業を聞けば、点数は上がるだろう。
この様な狙いを持って事に当たることに「罪悪感に近い手抜きをした感覚」や、機会損失の恐怖に近い「見逃しへの恐れ」が湧くこともある。このため「丸暗記」が始まりやすい。これは飲み込む量としては最大値となり、飲み込みが悪くなる。
飲み込みが遅い場合、キレイにノートを取ろう、一つも逃さずに書き取ろうなど、既に方向性が違う。「実践・実戦を意識しているのはどちらか」を問えば答えは明白だ。
・しかしその様な人でも、テスト直前で教科書を見るとしたらどうだろう。明日テストが有るという時に授業を聞くとしたらどうだろう。
テストに出そうなところを意識することに自然となる。そしてそれは、その目的に対して役立つ。
その感覚を初めから持っていれば、その分違う。
・同様に「後で誰かに教えるつもりで聞け」というのも「使い道」の一つであり、それだけ身が入る。
何より他人に教える必要がある限り、「分かった気がした」程度で済ますわけにはいかなくなるから。
自分で自分の伸びしろを見つける
・「仕事に慣れる」のは新人の目的の一つでは有る。残念ながら、慣れた後で成長はほとんど止まる。
逆に少し緊張するような「挑戦」をする場合、学習能力が高い状態を維持できる。
・陳腐な言い方をすれば、現状に満足すれば成長が止まる。まだ足りないと思い新しいことに挑戦したり、レベルアップを意識するならばまだ伸びる。そういう話。
そしてそのためには課題発見能力、目的を得るという形での自分の伸びしろを知る能力が居る。
両者の差は客観的には「飲み込みが遅い・早い」と映るだろう。というかまだ足りないと思ってる人以外は成長が止まる。
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/1887/”]
理解力を上げる 飲み込みを早くするには
何を飲み込もうとしているか自覚する
・心理学で「構え」と言うのだが、簡単に言えば「どんなつもりで学習にあたるか」という心構えが違えば、目や耳や頭に入ってくる情報も違ってくる。無意識に構えていることも多い。
脳は目的に関連しそうな情報を強調する。当然「何が強調されるのか」で差が出る。何を目的とするのか、目的があるかないかはそのまま「頭に入ってくる情報」に差が出る。
「飲み込めた」と自覚するゴールも当然違う。「どこまでやるか」にも差が出ることになる。案外要領が悪い人のほうが遠大なゴールを設定している事もある。それ故に走るつもりがなく、歩くつもりになる。
判断力は必要
・飲み込みが早いということを、飲み込めるタイプ、見切るタイプとここまで分けてきた。だが現実には、状況次第で切り替えるべきだ。少なくとも両方使える。逆を言えばその判断と切替はできる必要がある。
・見切るタイプには「理解」が必要になる。当然楽ではない。難易度は比較的高い。「見切る技術」自体が未熟であれば時間がかかる。要領が悪い人と見られる。
例えば「スイッチを押せばライトが付く」という件で、その通りに覚えればライトのオンオフは可能になる。
この場面で「なぜスイッチを押せばライトが付くのか? なぜもう一度押すと消えるのか?」とか哲学を始めれば知るべきことも覚えることも膨大になる。
これは無駄ではないのだが、特に仕事においてはさっさと役に立つレベルになってほしいというのはある。加えて教えなきゃいけないことは山積みだ。次が待っている。
・飲み込めるタイプ、さっさと「できる」ようになれば、予定は順調に消化できる。もっと教えてもらえるから、当然できることが増える。客観的に見たら、この二者の実力は大きく差がつくことになる。
・これは「詰め込み教育の流れに乗れるか」という話だ。頭の善し悪しであるとは言えない。例えばエジソンに義務教育は無理だった。アインシュタインも、どうも快く思っていなかったフシがある。
エジソン少年はおそらく、義務教育に対してはそれをやらなかった。泥団子2つくっつけて「1+1は1じゃないか」と言うのはどう見ても「飲み込めてない」。
当時の担任だか校長に「おまえの脳は腐っている」とか言われたそうだし、一事が万事この様子だったと思われる。
これは客観的に見れば要領が悪い。非常に悪い。飲み込みが遅いどころか全く飲み込めない。
見方を変えれば、時に「理解」は(まだ)必要なく、これはこう言うものだ、こうすればこうなると「飲み込む」ことが必要であることがある、となる。
関連:
_要領が悪い人
飲み込んでから理解
・もちろん飲み込むだけでも問題がある。当然ながらトラブルに弱い。想定内のことなら最速のアウトプットができるが、想定外のことだと最速で間違えるかフリーズするかのどちらかになる。
「テストで点取るためだけの勉強」と言えば分かるだろうか。この表現は勉強だけできるやつの代名詞っぽいが、少なくともテストで点を取るという目的自体は果たしているため、間違ってるとは言えない。
むしろ「勉強なんぞ全てテストの点数のためだ」と割り切って効果的な勉強をする者もいる。ただし「テストで点取る以外でも使える勉強の仕方」ではないため、そこが弱点とはなる。
・これは技能単位での丸暗記に近い。丸暗記の弱点と言ったら、おなじみの「応用力の不足」だ。
応用力
何が応用力となり得るか、といえば「システムの理解」に他ならない。メタ知識とも呼ばれることがあるが。
例えばパソコンのキーボードでタッチタイピングができ(野生のタイピングではなくシステム的な理解をしていれば)、この上でテンキーのある点に気づいていれば、間違いなく初めてでも手元を見ずに数字入力だけならできる。
繰り返しになるが、成長率に補正がはいるというよりも、スタート地点に補正が入る。
1を聞いて10を知る、とまでは行かないが、これは1を知って2を実行できている例だ。
・「似たようなもんだから似たような使い方はできる」という話だが、理解度が低いとそもそも似たような2つが「似たようなもん」に見えない。
共通点がまったくない別物に見える。そうなれば当然「ああ、アレと同じか」とはならない。0からのスタートになる。
もちろん大して重要じゃない、「できりゃいい」だけのことなら、パターンだけ覚えてハイサヨウナラ、でも構わないと思うが。
「理解」の優先順位は常にトップとは限らない
・スマホを使っている奴は別にスマホを作れない。でも使える。
鳥は空を飛べるが、別に航空力学を知ってるわけじゃない。でも飛べる。
システムの理解とは、まず実態というか対象があって、それを分析、調査、研究して明らかになる=言葉にする科学のような属性が強い。既存の物事に「なぜ?」と問うことから始まる。
・「覚える」という段階で「研究」を始めるのは大抵の場合歓迎されない。カリキュラムが出来上がっている「整理された分野」が特にそうだが、後は覚えるだけ・身につけるだけとなっていることに対して車輪の再発明やってる状態になる。
車輪の再発明自体は理解に貢献するのだが、「はよ出来るようになれ」と言われる場面でこれをやるなら飲み込み遅い人扱いはされるだろう。
システムが気になる性格は別に悪いことじゃない。自主的な予習や復習の頻度は比較的高い。
・どのみち実用的な覚え方は、
- まずできるようになる(模倣・コピー)
- 理解する(身につける)
という形が良いのだろう。まず飲み込む。次に見切る。
守破離と同じような形になる。仕事だと特にね。まぁ業種によるか。
一方で、正反対の順番で覚えようとする人も多い。動機はそれぞれだが、いずれにせよ「万全を期そう」とすると遠回りしやすい。
具体的思考と抽象的思考
・思考を具体的思考、抽象的思考と分ける考え方がある。
一般的な言葉のイメージとしては具体的な方が「賢い」、時には「真面目」と思われがちだ。実際の所は反対で、抽象的な概念の扱いが高度認知機能とされている。具体的なものはそのまま覚えればいいから脳的には楽。
賢かったり難しかったりするのは「抽象的なものを具体的なものに落とし込む」という作業。
・直観像記憶、世間ではフラッシュ記憶と言われている「写真のように記憶する能力」は、人間は子供のときは有って、大人になると失われる動物的な領域の能力とされる。ちなみにチンパンジーにも有る。
逆に「目標」は抽象的ではよろしくなく、具体的じゃないと何をしたら良いか思いつかなかったりで、一長一短。
・「抽象的」なのは具体性のない直感的、感覚的、曖昧なものであるが、その概念を扱うには関連する情報とのリンク、柔軟性なども必要になる。認知症になるとこの辺りがダメになってくる。
例えばおまんじゅうがあるとします。
「おまんじゅうある?」と聞かれたら「あるよ」と答えられるのに、「何か甘いものはある?」と聞かれてもおまんじゅうは浮かびません。
抽象的な考え方が低下すると、特定の物を言うとわかりますが、あいまいな表現になるとわかりにくく、たとえ目の前にあっても「ない」ということになります。
https://info.ninchisho.net/symptom/s40#id1-1
まぁなんというか、Googleの検索能力(抽象的)と、そこら辺のアプリに備わってる完全一致しか見つけられない検索能力(具体的)との違いに近い。具体的じゃないと対応できない、というのは不便となる。
・「理解」もまた、具体的なものと抽象的なものがあるように思う。多分だが、抽象的な理解やイメージは「群体」なのだろう。だから具体的にしようとすると失われるか、量がすごいことになりやすい。
・具体的な理解とは、丸暗記に近い。抽象的な理解とは、関連する情報を抜き出して扱う、イメージ群をそのまま使うという高度認知機能でもある。「応用が効くのはどちらか」を考えれば答えは明白だろう。
やはり具体的な理解をして(飲み込む)、抽象的な理解をする(見切る/理解する)という形がスムーズだろう、となる。
実践と理解
・教える側と教わる側の食い違いの原因にもなり得る。
教える側が理解を目的とした「抽象的な理解」をさせようとしていても、教わる側が「具体的な理解」、即ち実践的なことを教わっているつもりで聞いているならうまく行かないだろう。
教師役は時に「考えさせるための課題」を与えるが、生徒側がそれを「指示/命令」のつもりで受け取るならば伸びない。
・逆に教師役がとりあえずこれ丸暗記しろ、出来るようになれと実践的なことを促しても、部下が抽象的な理解を得ようとして回りくどいことをしてれば、伝わってないことになる。
この辺りはやれ教えるのが下手だとか、やれ真面目に聞いてないだとかとされがちだが、「構え」が食い違ってるだけかもしれない。まぁ意図は説明したほうがいいね。
メモ
・まぁ人間、勉強すれば結構なんでも覚えるものなんだが。差が生まれる理由の多くは「習得のための知識」があるかどうか、自分の弱点を潰せているかどうかが大きい。
・勉強すれば結構なんでも覚えるもんだが、人によっては勉強するべきはその技術よりも、「勉強の仕方」のような知識が先かもしれない。
・関連:
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/2399/”]