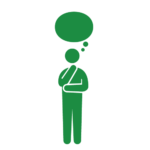・一言で言えば「負け惜しみ」。
すっぱいブドウ
・イソップ童話から。
狐が高い所のブドウを取ろうとぴょんこぴょんこ跳ぶわけだが、届かない。ついぞ諦めた狐はこう言った。
「どうせあのブドウは酸っぱかったんだ」。
・概して「自分が手に入れられなかったものにケチをつける」というような言動に対してすっぱいブドウだと指摘される。欲しかったものや、目指していたことなど。
まぁガチャで出なかったSSRを悪し様に言うだとか。
当人の心中で完結してれば別に良いんだが、それを口に出してしまうと「持っている人」からしてみればケチを付けられた以外の何者でもないため、よく揉め事になる。
・フロイトが心の防衛機能、そのうちの「合理化」の説明をするために引用したのが初だと言われている。
ストレスを感じることに対して、自分の見方や感じ方を変え、「問題ない」と捉えようとする機能。
・一見すると負け惜しみ、諦めたことの正当化だが。
ぴょんこぴょんこ跳んでた「動機」はもちろん、ブドウが食べたかったからだ。そして能力的にそれは無理。ストレスが貯まる状態。
ブドウが欲しい + 取れない ってのは、無限ループする。永遠にぴょんこぴょんこするはめになる。これをやる動機は「ブドウが欲しい」である。
だからすっぱいブドウは「ストレスから脱するために動機/理由を無価値にする機能」であるとも取れる。疲れ果てるか死ぬまで跳んでるよりはマシだろう。
甘いレモン
・手に入れたものや自分の状況を「これはいいものだ」と思いこむこと。
いいものをいいものだと認識しているのではなく、「それしかないから」良いものだと思い込むこと。
物に限らず、自分が置かれている状況、自分の変えられないこと、どうにもならないことなどでもありえる。
まぁ変えられないものに対して前向きになれる点は結構なことだろう。ただ、こちらの方が色々やばいと思う。
・酸っぱいブドウと対になっている。
ストックホルム症候群
・碌でもない対象を肯定する類似した例。
・1973年、スウェーデンのストックホルムで銀行強盗が人質をとって立てこもった(ノルマルム広場強盗事件)。
サブマシンガンを持った犯人が9人を人質に。後5人は交渉により開放されている。残されたのは女性3名、男性1名。
最終的に犯人2人は逮捕されるのだが、人質たちの事件から解放後までの動きがおかしいことが注目を集めた。
- 犯人に変わり大統領へ交渉の電話をかける
- 犯人が寝ている間は人質が警察に銃を向ける
- 解放後は犯人をかばい、警察に非協力的な証言を行う
電話はまぁ脅されていたにしても、他の部分には自主性が見られる。
これらの現象は、
- 場を支配している犯人の許可なくしては飲食、トイレすらできない状態では従順になるしかない。
- そのうち犯人の小さな親切に過大な感謝をするようになる
- 犯人側も人質に対しての態度が変わる
とされている。まんまモラハラ加害者と被害者見たいな話だが。実際、「虐待」に属する話にはストックホルム症候群の例はよく見られるようだ。
・よど号ハイジャック事件でも乗客と犯人との奇妙な連帯感が示唆されている。
フェスティンガーの実験
・いい部分が無い方が「甘いレモン」になりやすい。
1:つまらない作業をさせる
2:報酬を払う
A:少ない B:多い
3:その作業の「面白さ」を次に作業をする人に伝える
・順当に考えれば、報酬が多く貰えたBグループが熱心に面白さを伝えてくれそうなものだが。
実際には、報酬の少なかったAグループの方が面白さを伝えることに熱心だった。
・Aグループはつまらない作業 + 少ない報酬で、いいことがなんにもなかった。
加えて「つまらない作業の面白さを伝える」と良かった探しに思考を向けることで、「あの作業は本当は面白かったのかも知れない」と認知を修正したことを示す。
これがカルトやマルチの被害者だった場合には、割ととんでもないことになるだろう。
・このような対立する認知(今回のつまらない仕事+良さを伝えるなど)があることを「認知的不協和」と呼び、人はそれを解消、あるいは低減するための何らかの圧力をかける、とフェスティンガーはしている。
すっぱいブドウの場合は「動機/価値/理由」を除去することによって認知的不協和を解消した。
甘いレモンの場合は「良かった探し」により「これには価値があった」として認知的不協和を解消する。
逆を言えば、Bグループはつまらなかったが金額でそこそこ満ち足りたため、「仕事自体はつまらない」という認知を保てたと言えるだろう。
これらの機能は何のためにあるか
・「心の整理」としては、一定の価値があると認めることができる。
変えられないものを前向きに捉え、未練を断ち切って、執着を手放す効果はあるだろう。
・また、「状況に適応するため」であるとも言える。
すっぱいブドウは対象に価値がないと決めつけることで結果的に「諦め」がついた。
甘いレモンの方は「問題ないと思い込む」ことで決着がついた。
これだけだと現状に甘んじることになるが、心理的な執着が開放されることにより、物の見方も変わり、適応が可能になる。
実際ストックホルムの例で言えば、少なくとも被害者たちは犯人に殺されること「は」なかった。この時点で生存としては「正解」とは言えるだろう。
これが「自分は本当はいつもどおりに仕事を終え帰るはずだったのに」といつまでも現状を嘆いていたら、まぁ態度も行動も当然違い、下手したら殺されていたかも知れない。たられば話だけどね。他の人質は適応していたのだから、悪目立ちはしただろう。
ストックホルムとは別の事件の被害者が、ストックホルム症候群は「適応」であり、病気ではない、と主張している。
適応するしかない状況だった、と。被害者が犯人への協力という「犯罪行為」に正当性を見出そうとするのは、生き残るための戦略である、と。
脳が、認知を変更することによって当人を動かしているように見える。
ちなみにストックホルム症候群の発症の要素として、「直接的かつ継続的な虐待を伴わない不親切」が挙げられている。
逆を言えば「従っていたほうが生存できる」=「適応する価値が高い」と思える環境だったと言える。
・特に「甘いレモン」に言えること。
本来はちょっとした自分への慰めや励まし程度の働きであるのだろうが、ストレスが強すぎたりしてこのバイアスが強く出れば、相手への「狂信」のような状態になる可能性も否めない。
虐待する親をかばう子供、モラハラされている事に気付けない被害者、DV夫が「いつか変わってくれる」と信じ続けている妻など。
DVは蓄積期、爆発期、ハネムーン期のサイクルを持つと言われている。この内「まとも」であるハネムーン期を相手の「本来の姿」だと縋ってしまうのは、バイアスがかかっていると言われてもしょうがない。
ストックホルム症候群にしたって、銃器持ってオラついてる強盗に親しみなんてどう考えても持てるわけがないのに、持ててしまったのだから。
・必要な機能ではある。恐らくは。
その分過剰にならないように気をつけることと、一部の精神的潔癖症とでも言うような、真面目・完璧主義的な価値観の場合にはこの機能を抑制しすぎて、ストレス溜めこんで、ヒステリー起こさないようにもするべきだろう。多い。
この場合、「問題に向き合ってないと不安」というメンタルなので、簡単ではないかも知れない。
・どちらも本気でそう思い込み、それが現実と異なるため、周囲と対立を生んだり、声高に主張して他者を巻き込んだりする「二次災害」を産みやすい。
思っても言わないほうがいいだろう。機能自体は「自分にとっては」、時に有用だと思われる。
参考
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E7%9A%84%E4%B8%8D%E5%8D%94%E5%92%8C