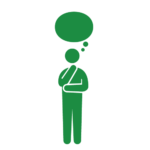TED:先延ばし魔の頭の中はどうなっているか
おもろい。ああいうイラストって見やすくていい。彼のサイトを見た限り、多分自分で描いてるねこれ。
以下、個人的趣味で再解釈したり色々とするため先に言っておくが、コンテンツとしてはこの話は既に完成しているだろう。テーマに対して答えているというか。
先延ばしに関する4つの要素
まぁもちろんこれは概念の擬人化だ。
おさる
・Instant Gratification Monkey。
instantはそのまま。Gratificationは「満足」の意味がある。
だから「すぐに満足感/達成感がほしいサル」とも言える。
・すぐにご褒美が欲しいおさる。絵がね。いいよね。むかつき具合がいい。
ある意味「近視」である。近くのものしか認識できない。理性的意思決定者がやりたいような「最後には勝つ」タイプの行動は「つらいこと」との認識しか持たない。
ティム・アーバンは先延ばし屋だけにこの猿がいると冒頭ではしているが、最終的には「みんな先延ばし屋なんです」とまとめている。
・「猿」は時に、人間の内面の衝動性/獣性の象徴として扱われることがある。今回もそうだし、マインドフルネスの分野ではあれやこれやを気にする心を「モンキーマインド」と呼んだりもする。
どうも「嫌悪を感じる人間らしさ」のシンボルになってるような気がするね。
多分、誰の中にもいるだろうね。
・快/不快、好き/嫌いで物事を測る。シンプルで、おなじみで、真面目なときほど邪魔になるモジュール。最も厄介なのは、アホな上に異常に影響力が強いことだ。
多分このサルは、脳の側坐核の擬人化だろう。知覚した情報に対して、過去の記憶から真っ先に好き嫌いを決める。快不快も決める。このモンキーがやる気が出るかでないかを握っている。
かなり好き嫌いに左右されるのは、人間が動物だった名残という話もある(まぁ今でも動物だが)。本来は一瞬で良し悪しを判断し、避けるかどうか決める、というシステムだった。
「楽な方を選ぶ」のもこのためだろう。楽というより確実だから。つまり、「安心」。
・まぁ「人間」の目には、これは絶望的に怠惰で非生産的な刹那快楽主義に見え、ましてや自分がこのような行動を取るということは(それも重要な局面でだ)許せないわけで。だが、上記の通り一応「機能」としては多分、働いている。それも正常に。
・ちなみに、ティム・アーバンがTEDトークを引き受けた時の内面が語られているが、このような快諾して後から焦るパターンもまた、出だしはおさるの意思決定にも見える。
理性的意思決定者は「自分が何を引き受けたかわかっているのか」とツッコミ役に回っているのもこう考えられる材料の一つ。おさるは速攻で別の興味(インド)に移っている。
別に一般でもあるだろう。遊びに行く話が出て、その時は遊んでいる時のイメージを思い浮かべて快諾する。
で、日が近づいてくるにしたがって具体的な/現実的な準備やらなんやらが“目につく”ようになると、だんだんめんどくさくなってくるだとか。
更に日が近づいてきて、「そろそろ準備しないとな」とか思いながら重い腰を上げるみたいな。
やりたいと思ったことでも、やらなきゃいけないことでも、こういう事はある。確定申告とかああいうのは、毎年ギリギリの日に混むわけで。みんなそんな感じじゃないのか。言わないだろうけど。
・相当に直感的、本能的であるが、それでも人類は結構これに打ち勝ってきたはずだ。そうじゃなきゃ農業発達しないだろう。植えたはしからほじくって食いそうだし。
理性的意思決定者
・Rational Decision-Maker。
Rationalには理性的な、合理的な、推論の、そして「正気の」、などの意味がある。
Dicisionは「決定」など。
・俯瞰的な視点を持っている。
長期的な時間間隔を持っている。このため「気の長い計画」を立てたり、「最終的な利益」を意識したりする。
あるいは「望んだ結果からの逆算」により予定を立て、「今とるべき行動」を計算する。後者のほうがあり得るか。
・大抵の人間が「自分」と認識しているであろう理性的部分。肝心な時におさるに負けたりするので自己嫌悪やらなんやらになったり。
「何をするべきか」を見出すことができる部分。おさるの視野より広いため、これが可能になる。
・おさるとは相容れない立ち位置にある。あちらは見えてる部分に対しての評価を下すが、こちらは将来的な要素も含めて価値を下す。
例えば「確かに嫌いだが、やっておけば後で楽になれる」というような判断/価値を見出すことができる。
でサルが「でもいやだし! 嫌いだし! そんなことより楽しいことしようぜ! っていうかこれじゃなけりゃなんでもいいよ!」みたいなな。
こちらは基本的に、地道な努力を推奨する立ち位置にある。こう言った物事は、「ご褒美」が出るのは最後の最後だ。おさるとは絶望的に相性が悪い。なにせ「すぐにご褒美がほしいおさる」なのだし。
・動画内でも少し触れられているが、「妥協点」が発生することもある。これを拡大していくのも手段の一つだろう。やるべきことを、より簡単に、より楽しくする工夫だとか。
ただ、少しおかしいのは、「別にそれほど嫌がってるつもりはない」ということがほとんどだということだ。「そこまでいやか?」と自分で思う程度のことに対しておさるが暴れるわけで。
私はあれだ、これワードプレスの下書きに突っ込んでて前日の続きを今書いてるわけだが、サーキュレーターのホコリを取りたくてしょうがないからな今。
・目の前のことは大事に思える。未来のことは小事に思える。人にはそんな傾向がある。
体に悪いと知りながら暴飲暴食をしてしまう、などはこのせいだと言われている。
目の前の物事の過大評価と、将来の過小評価。
だがこの2つは、元から別々のモジュールによる評価であり、比べてすらいなくないかこれ。
つまり評価基準そのものが2つある。おさると理性で食い違いが当然に発生し、より本能に近いおさるの意見が優先される。欲求や目的の内容ではなく「古株だから」って理由で採用されてる気がする。
だとしたら人間の仕様自体が泥舟のようなもので、なんとかしなければならない。
パニックモンスター
・AAAAAAAAHHHHHHHH!!!!!
これを擬人化しようって発想はなかったな。素晴らしい。
・「恐ろしい結末が近づいている時、突然目を覚まします」。これは違う見方ができる。
近づいてきてようやく認識できるのは、おさるだね。おさるがパニック起こしてるのではないか。
この上で、テンパってバックレたんじゃなくて、おさるがようやく理性的意思決定者に「協力的」になった結果、自分のカタログスペックよりも上の成果が出せるのではないか。残り時間が大体やばいから目をみはる結果にってほどじゃないだろうが。
理性的意思決定者だけで最初から締切間近のスペックが発揮できるっていうのなら、計画段階でそれは織り込まれてるだろう。でも現実にはそうじゃない。
“実力以上”に感じられる集中を、こういう時はしているものだろう。目標を立てる時も、ペース配分する時も、マイルストーン置く時も、この時のスペックが前提として織り込まれてはいない。
・パニックモンスターは結局の所、緊急事態に於いての特殊モードではあるだろう。おさるの活力と理性的意思決定者の意思/目的とを持った状態。
普段この力を発揮できないのはなぜか。私達はそれをやるべき理由を“頭ではわかっている”状態ではあるが、“実感”としては恐らく足りてない。ド近眼のおさるが知覚できるほどには現実感が足りない。
将来のことを甘く見積もるのは、理にかなっているとは言えるんだ。「後でなんとかなる」という余地がまだあるから。目の前のことを優先するのは動物的には「合理的」とすら言える。
その余裕が尽きた時、パニックモンスターが出る。
緊急中毒
・ここで言われているパニックモンスター、つまり先延ばしを打破する力は、一部では「緊急中毒」と呼ばれているものだ。あまりいいものとしては扱われない。
特に、ここで言うパニックモンスターが“なんとかしてくれる”という認識を持ってしまい、ギリギリまでほったらかす悪い癖が付きやすいと言われている。
・なによりも、彼が語っている通り“締め切りがないと現れない”ため、締め切りのない物事(この中には人生に必要なものが含まれる)に対して打つ手がない。その結果、“先延ばし”をし続けることになる。
あくまでも計画通りに物事を進めたいのなら、パニックモンスターに頼らないことになるが、色々引っかかる。まぁ後述。
舵
・これを忘れてはならない。自身のコントロール権。その座。
つまり人がおさるとして脱線をエンジョイしている時、理性的意思決定者としての視点も存在していると言える。
今回のような先延ばしが話題だと、大体こんな話が出てくる。「先延ばしで全く予定と関係ないことをしていると“罪悪感や焦り”が募り、ようやく本来の作業に戻る」など。
この罪悪感や焦りを感じているのは、長期的な視野を持てる、つまり「計画」を認識できるだけの視野を持つ理性的意思決定者だろう。
つまりこの状態、ゲームにおいてコントローラーを手放さずクッソ下手なプレイをし続けるおサルを、理性的意思決定者が指を加えて見ている状態となる。
で、これだと今度はパニックモンスターは理性的意思決定者じゃないのかとも思えてくる。端的に言えば、上記のような経緯の果てに、サルに対してブチギレたかのような。わからんね。
2種類の先延ばし
・彼は「締切の有無」で先延ばしを2つに分けている。
締め切りが近ければパニックモンスターがなんとかしてくれる、として。では締め切りがなければ。
・締め切りがないもののほとんどが“自分からやりたいと思ったこと”や“自分のためになること”ばかりなのが目立つ。
裏を返せば締め切りがあるものは社会的なプレッシャーやペナルティが存在している。信頼を失う、無能だと思われる、自分に多大な不利益が生じた上で自業自得=助けて貰えそうにないなど。
ハッキリ言ってしまえば、「自分が行きたい方向にケツを蹴ってもらいたい」という人も結構いる。
エクササイズとかそれ系で鬼軍曹みたいなキャラが時々流行るだろう。ああいうの。
・締め切りがないものは自分のため、未来のため、夢のため、目標のためと、結構“未来への努力の投資”のような属性がある。
これは裏を返せばやらなくても別に今より困ることにはならないし、何なら諦めさえすればなかったことにすらできる。
先程の「余裕が尽きたらパニックモンスターが出る」という話とつなげるなら、この場合「余裕がいつまでも存在する」。
これはいざとなったら諦めればいい、という大げさなものではなく、「“今”やらなくたって、別に後でいい」という形が多い。
・時間管理マトリクスで言う「B(重要だが緊急ではない)」そのもので、軽視しがちだが本質的に重要であると言われているもの。
これに対しては、それほどやる気が出ない。トーク中で自分のおサルに強い苛立ちを感じているようなメールがたくさん届いた、とあった。その中でも大学生が多かったとも。
一番「自分のこと」を考えることが求められる時期だろう。当然、何かしら計画/目標を立てるだろう。だからこそ、この問題に最も直面する。
・緊急中毒はよろしくない、というのも一種の理想論かもしれない。
私達は「やらなきゃいけないこと」に追われ、「やるべきこと」は放ったらかしになりがちで、ぶっちゃけて言えばパニックモンスターに相当に頼っている、というのが実情ではないだろうか。
本当の意味での、自分にとっての「やるべきこと」に対して、この問題に苦しめられるというのがその証拠だ。
パニックモンスターがでない途端に、これほどまでに「自分が自分の思ったとおりに動かない」ことを思い知らされる。
・裏を返せば、パニックモンスターを召喚するために、締め切りを小刻みに設定するのもアリかもしれない(自分で決めた期限をちゃんと守る性格してるならだが)。
・トーク中に彼が示した「人生カレンダー」は、「人生/寿命」という締め切りを意識させるためのものだろう。
自分の命が有限であることは誰もが認めるところだ。まぁこれまた頭でわかっていても実感がないからアレなんだけど。
ともかく、誰もが有限と認める“寿命”を意識すれば、「余裕」なんて感じない、かもしれない。
メモ
・正直な所、この問題に本能vs理性という見方を私はしていない。本能vs別の本能だと思っている。
いや、モジュールvsガジェットと言ったほうがいいんだろうか。まぁどうでもいいや。
・トップドッグとアンダードッグ/インナーゲーム
似てるよねぇ。サルと決定者の関係に。
・トップドッグ&アンダードッグゲシュタルト心理学で言う勝ち犬と負け犬。理性と本能。
トップドッグが「やれ」と騒ぎ、アンダードッグはのらりくらりと言い訳する。トップドッグは一時的には勝つが、最終的にはアンダードッグが勝つとされる。
この2匹が頭の中で喧嘩しながら人は何かをやったりやらなかったりする。
・インナーゲームも“2人の自分の争い”だ。スポーツ心理学の分野。
セルフ1がトップドッグのような部分。セルフ2は実際に体を動かすような部分。
ご多分に漏れずセルフ1が騒ぎ立てるので、セルフ2は“萎縮”してしまい、実力が出せない。これが「緊張」と呼ばれる状態だとされる。
早いもの勝ち
・2人の自分、という話ならファストとスローという概念も並べておきたい。意味としてはどちらも言葉通り。
ファストは「早い思考」。直感的なもの。ヒューリスティック。経験則とか。
スローは「遅い思考」。私達がイメージする思考はこちら側に入る。
今回で言えば、おさるはファスト、理性的意思決定者はスローに該当するだろう。
・何か余計なことを思いついた時、ファストでは「やろう」となったとする。やるべきことがある状況でそのまま実行したなら、おさるに舵を奪われたことになる。
やるべきことを意識しているのがスロー=理性的意思決定者ならば、「それどころじゃない」との決断を下すのは、おさるが舵に飛び乗った後となりやすい。
この場合だと、スロー側はファストが動くたびに消耗する。毎回サルを追い払わなければならない。
スローのしつこさに負けた状態が、私達が「集中が切れた」とか呼ぶ脱線、雑念、上の空の状態だろう。
問題はアホが先走ってその処理に追われる点になるが、どうしようもないなこれは。お手上げ。
・なおたちが悪いことに、「根拠」の数は少なければ少ないほど“正しさに自信を持ちやすい”という逆説的な研究がある。要するにバカもといシンプルな方が意見として強い。
ファストはまぁ、元から精度よりも速さを優先しているためそれほど論理的ではない。
スローは反対に論理的ではある。つまり「自分がやるべき理由」はつらつらと挙げられる。
結果、逆説。私達が「これほどやるべき理由があるのになぜ先延ばしてしまうのか」とか思うことになる。
むしろ先延ばしにしたい理由を挙げたほうが有効かもしれないが、これはこれで怖いな。
他にやることないけど先延ばしたい
・ここで言われている先延ばしは、タスクを先延ばししているのではなく、それ以外の誘惑に「割り込まれた結果」だとも言える。
「後にしよう」「まだやらなくていい」と思う時とは、「今やりたいこと」を前にしたときだ。
自分の先延ばしはそう言ったものではなく、他にやりたいことがなくても手がつかないんだ、という人もいるだろう。だが、こう考えたらどうだろうか。
「やりたくなさすぎて、相対的にどうでもいいことが“今やりたいこと”に見えてくる」と。
例えばベタだが、“勉強してると部屋を片付けたくなる”だとか。
それ、自分で「そんなキャラじゃないのに無性に部屋掃除したい」とか言ってる人もいるわけで。
・先延ばし関係のまとめ
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/3291/”]