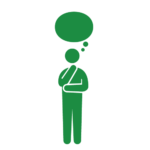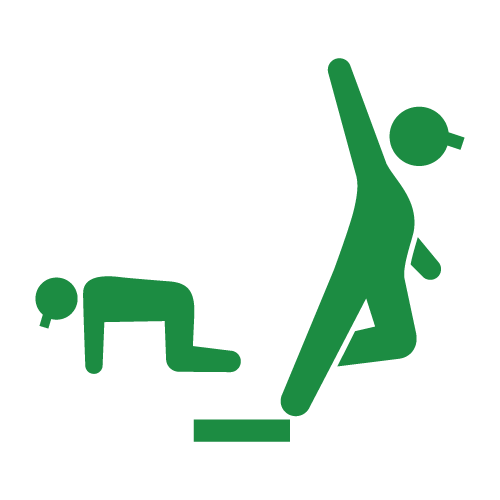
・人目を気にしない人間もあまりいない。
程度の差はあるが、大抵は気にしたくなくても気にしてしまうだろう。
人の目が気になる人の特徴
・人の目が気になる人にも、アッパー系とダウナー系がある。
良く思われたいから気になるか、バカにされたくないから気になるか。
アザー コンプレックス
度が過ぎて人目が気になる傾向はアザーコンプレックスなんて呼ばれたりもする。
othersで他人。コンプレックスはよく「劣等感」とされるが、本来は心理学でも複合体という意味。感情の複合など。
単純に、他人が気になりすぎて色々頭の中ごっちゃになりがちな人とかそんな解釈でいいだろう。
アザーコンプレックスは恐らく専門用語ではなく、自然発生したか、メディアが作った言葉だと思われる。
少なくともこの様な言葉が発生する程度には「人目が気になる」というのは共感される感情だと思われる。
プライドが高い 自意識過剰
・プライドが高いって言葉はうぬぼれていて、傲慢で、競争主義で、負けを認めない限り負けないと思ってるみたいなイメージを持たれている。
育ちすぎた自己イメージを他者の評価から守るための防御感が、外に対しての攻撃性や誇張、競争意識として出ているタイプ。
ちなみに七つの大罪の一つ「傲慢」は英語で pride である。
・一方で自意識過剰って言葉も同レベルだと思われがちだが、「自分は見られている/関心を持たれている」という意識がより強い表現だ。こちらは過敏型自己愛に似ている。
結果、自惚れているような印象を与えるが、実際には不安や恐怖の感情が強い場合も多い。この場合他者評価ではなく、実害の懸念などもある。
わかりやすい例だと、女性が帰り道に誰かにつけられてたと感じた、と人に話した時に「自意識過剰だ」と返されるパターンとか。話者は実害の懸念をしているが、受話者は自惚れているように取ってしまう。
・これら両方、人の目を気にしている。
すぐ謝る傾向
・これはダウナー系。
駄目なやつだと思われていないかと気にしていることが多いなら、承認欲求の内、「拒否回避欲求」のほうが強いタイプだと言える。否定的評価の回避。
「悪目立ち」をしたくない。ことなかれ主義的にすぐに謝って「鎮火」しようとする傾向はある。逆ギレするパターンもあるが。
この辺りは個人の性格による。拒否回避欲求はあくまで「動機」であり、どんな行動をするかは分かれる。
この上で、こんな話がある。
心理学的に、相手の返答に対する明確さとスピードには、その人の自信の程度に影響があると言われています。
https://withonline.jp/work/life-secret/WrZ8s
ここではすぐ謝るのは、自信がないことの現れとされている。
脊髄反射で謝るってのはスピード的には良いが、「明確さ」という点では致命的にアウトになる。
「すみません」ってのは、ある意味万能である。非を認めたように一見見えるし、一見謙虚だが、「とりあえず」で言っとくにも無難な言葉。「対応」ではなく「反応」になっている。
なぜ反応が出るのか。人目を気にして常に緊張していたり、元から自己評価が低く自信がなかったり。
結果すぐ謝るクセが出て、それは周囲に「自信がない」と取られる。という悪循環。
自己主張をしない
・これもダウナー系。悪目立ちしたくないから。
人に嫌われたくない、悪く思われたくない、という思い。
ただこの心理を逆手に取ってコントロールしようとする、反社な生物もいる。
・まぁ普段ならいいが、必要な時にも自己主張できなくなるようだと困ることになる。
他人を尊重し、自分を尊重しない態度。ノンアサーティブと呼ばれる。
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/1552/”]
人の目が気になる原因と心理
人の眼からはなんかビームが出てる
シリアスブレイクした。
簡単に言うと、人は無意識に「視線」を物理的な影響力が有るものとして解釈しているとの説。実際にはビームは出てない。
Scientific Americanは世界的に広がる「視線は何かを放射している」という信念について調査した、複数の研究について解説しています。
2019年の研究では、被験者が座ったテーブルの上に「ペーパータオルに似た円筒形のチューブの画像」を表示したディスプレイを置き、テーブルの端に人の横顔を映した写真を、視線がチューブを向く位置で設置しました。
ディスプレイはキーボードと接続されており、特定のキーを押すとチューブが傾いていくようになっていたとのこと。https://gigazine.net/news/20210106-gaze-physical-force-illusion/
1. チューブが立っている。
2. それを横から見ている「顔」の画像がある。
3. 「もうすぐ倒れる」と思うところまで被験者にチューブを傾けさせる。
4. 「顔」がある場合、かなり傾ける被験者が多かった。
5. つまり、「見ている人の目線が、倒れようとしているチューブを支えている」と被験者は認知しているのではないか
みたいな話。
昔見た米海兵隊のシゴキの動画でリー・アーメイよろしく教官が顔近づけて兵士を怒鳴りつけてるんだが、兵士は上の方見て決して目を合わせないんだよね。これの解説が「目を合わせたら失礼だっつってぶん殴られるから」だった。
また、動物は見つめられるのを結構嫌う。ネコとか有名どころか。犬もそう。相手によるけどね。大体は見つめる=威嚇と解釈される。
一方で犬に限れば(他は知らん)自分たちはガン見してきたり、アイコンタクトは嬉しかったりと文脈によって様々ではあるが。逆に文脈次第では確実に敵対行動と受け取る。
本能的に「視線」は結構嫌う余地はあるんじゃないかと思える。
加えて人には「穢れ」として認識されやすい傾向は元からあるんじゃないだろうか。動物で言えば「警戒心を呼び起こすべきシグナル」として。
どちらかと言うと評価
「人の目」というのは衆人環視的な、実際に「目につく」こと自体を気にする面と、「見られてどう思われるか」を気にする他者評価を気にしている面がある。この2つはつながっている。
特に悪いことしてるわけじゃなければ衆人環視は気にしない、と言いたいところだが、謎の罪悪感やら劣等感やらでもうここからアウトな人もいたりする。
またHSPなどを始めとして、単純に人が多い場面や対面する場面だと認知的な負荷が上がるなどもある。「見られる」ことによって、相手の頭の中を意識してしまう面はあるだろう。
人と会って別れた後に一部によく発生する、「脳内反省会」なんかも、人の目(自分が相手に与えた印象)を気にしている面がある。全部じゃないが。
実際の人の目は「起点」に過ぎないことが多い。実際の悩みのタネはそこからの連想や推論となる。人前に出なくても、想像しただけでアウトな人もいる。
「気にしない」は有る種の解決になる。気分的に難しいだろうけど。
ただ後述するが、実際に「気にされてない」ことも割とある。「推論」が消極的な方向で過剰だと、なかなか当人気づけない。
承認欲求
・見られたい理想像はそれぞれだが、自分が望んだ通りに他人に思われたいという点では変わらない。ただしこの評価への欲求は、
評価を「獲得」したいのか
評価を「維持」したいのか
大きく分けてこの2つ目標に分かれる。
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/1306/”]
称賛獲得欲求
・人気者になりたい、感心されたいなどの欲求。
言葉通り、意図した称賛を獲得するのが目的。
これにより積極的な傾向が強まる。
・恐らく、一般で言われる「承認欲求」はこちらに入る。
・自己愛性人格障害の研究においても「称賛獲得欲求」はあり、通常の称賛獲得欲求と「極めて類似している」とされる。
一応違いは有る。通常はあくまでも実力でそれを得ようとするが、自己愛は手段に拘らない傾向がある。
拒否回避欲求
・嫌われたくない、変だと思われたくない、拒絶されたくないなどの欲求。
言葉通り、拒否されることを回避することが目的。評価の維持。
これにより現状維持と消極的な傾向が強まる。これらを果たすには、「目立たない」「余計なことをしない」のが一番だから。
・これは今よりも悪い評価にならないように、などの「失墜」への懸念とも言える。
どちらであるかで行動が変わる
・この2つはその者を正反対の行動に導く。異性への告白に於いては賞賛獲得は行動的に、拒否回避は抑制的に働くとする研究も有る。
主婦に於いては賞賛獲得が強ければ「愉快で元気」であることを演じて友人関係などを求め、拒否回避が強ければ「義理の親に可愛がられるよう」演技する傾向がある。
・だが、賞賛獲得と拒否回避は他者が見分けるのは困難だ。自分にすら見分けられるかどうかちょっと怪しい。
例えば女性に多い「痩せたい」という意図は、一見すると人の目を気にした拒否回避欲求に見える。要するにデブだと思われたくないと。
だが実際のところは称賛獲得欲求の要素が強いという。「どれだけ痩せたか」は彼女たちにとっては、周囲の評価を高めるための「スコア」らしい。
自己呈示
・人に見せたい自分は、必ずしもありのままというわけでもない。初めから人目を意識した「背伸びした自分」である。
他者に対して「自分をこうだと思わせたい」という一種の演技。これを「自己呈示」と呼ぶ。
例えば優しく思われたいから人当たりよく振る舞う。賢いと思われたいから頭が良さげなことを言ってみる。明るいと思われたいから面白いことを言おうとして失敗して嫌われる、などなど。
特に多くが「自分が考える社交性」を演じているように見えるが、素は見せないほうが自然だからな。
言葉にすればちょっと残念な人っぽいが、まぁ大なり小なり誰もがこの辺りは意識しているだろう。
また虚栄が暴かれるリスクが有るため、普通はそれほど実態とかけ離れた演技はしない。普通じゃない奴もいる。
反面、上手く行き過ぎることもあり、「仲良くなってくると人付き合いが苦痛になる」なども起こる。背伸びを当たり前だと思われてるからね。
・人が自己呈示をする動機は、一つは他者からの評価・印象が自身の利益/不利益に繋がるからだとされている。
また他者からの評価の上下は(社会的な)自尊心の上下に直結する。
このため、平たく言えば自己呈示は「ナメられないように良く見せよう」という心理でもあるし、「自分に自信を持ちたいから評価されたい」「自信を失いたくないから恥をかきたくない」という心理でもある。承認欲求と類似。
・人は基本的に、この「演技」には手を抜かない。というか抜けないだろう。諦めることはあるかもしれないが。
よほど中身が無い限りは、他者評価による社会的メリットよりも、自尊心への影響を人は気にしていると思う。
・他人に「評価」されるにしても、どのような評価が目的なのかはそれぞれだ。
賢い、可愛い、かっこいい、頭がいい、親しみやすい、優しい、厳しいと思われたい者もいるし、恐怖の対象になりたい者もいる。また、相手にも依るだろう。
こういった意味では誰も彼もが「キャラクター」をある程度意識して演じている、とも言える。
内在化
・社交的に振る舞うと、社交的だと周囲に認識される。それを維持するためにはまた社交的に振る舞う必要がある。
このようなサイクルで、本来「演技」だった自己呈示は自分のあるべき姿に内在化することがある。
別件となるが、人の性格は実際に変わる。そしてそれに有効なのが、「なりたい性格のように振る舞うこと」だったりする。
・面白いことに、匿名だと内在化は起こらないとされる。
「自分はこう見られているからそう振る舞おう」と感じる余地があるからこそ、内在化が起きるとも言える。
良く言えば「期待に応える」ってところか。これまた苦しみの元ともなりがちだが。
「人の目に自分から触れる行動」の内容が、社会に面している時に出る性格に取り込まれていく、とか言えばなんかそれっぽくはあるな。
・見方を変えれば、「外面から全く影響を受けない内面もない」とも言える。
ただし、「認識される外面」とは、自分の思考的材料や方法に依る計算結果だ。「予測」であり、「現実」とは限らない。だからこそ、認知の歪みや認知バイアスなどは問題となる。アレは予測を現実だと捉えている状態だから
人は「どう思われたか」をどのように認識するか
・結論から言うと、認識なんてしていない。推論している。まぁそりゃそうだ。脳同士は繋がってないし。
この「人の目の推論」の材料が、「自分が自分を見て、自分が自分をどう思うか」をそのまま転用しているという説が有力となっている。
スポットライト効果
・自分が注目される「心当たり」があると、現実以上に「自分は注目を集めている」と感じる心理がある。
「どれだけ注目を集めたか」にはバイアスがかかる。
ギロヴィッチらが行った有名な実験がある。
研究室でアンケート用紙を記入してもらっている実験参加者たちの中に、遅れてきた実験参加者(以下、遅刻者)が入っていくというものである。
ただし、遅刻者には大物歌手のTシャツを着て部屋に入るように言われた(当時この大学では、その歌手のTシャツは絶対に着たくないという学生が大多数だった)。
この実験は何度か行われたが、平均すると、部屋にいた者のうち約20%が遅刻者のTシャツに気づいたが、遅刻者は約50%の人に気づかれたと答えている。
https://kagaku-jiten.com/social-psychology/individual/self-presentation.html
簡単に言えばクソダサTシャツ着てるという「目立つ理由」があるから、本人は実際の倍以上に「気づかれた」と感じたということ。
反対に何かに自信を持っているのなら、良い方向に解釈するだろう。この実験は、自分の考え方や感情を、他者が自分の何をどう見たかを推論する時にそのまま利用することの示唆なのだから。
帰属
何を原因だったと推論するかは「帰属」とも呼ぶ。結果から原因を逆算すこと。何に帰属するかが人によって偏りがあり、ある者は人のせい、ある者は自分のせい、なんて帰属の仕方をしたりもする。
帰属を始めとした推論は所詮推論であり、確定ではない。要するに「これのせいだと思った」程度のものなのだが、認知バイアスよろしくかなり「直感/確信」に近いレベルでそう思う。
クソダサTシャツの例は、遅刻することで人の目を集める→人の目が「何を見たか」の推論の段階でクソダサTシャツに帰属されている。
当人が元から気にしていた結果、倍以上に「気づかれた」と感じた、という流れ。
このように、精度はかなり怪しい。まぁ直感レベルなので。
・まとめれば、「自分で自分を見る目」でしか人の目を考えない。
自分の認識している「心当たり」しか、他者からの「評価の受け皿」がない。自己評価が低い、あるいは自信のない人間には大抵励ましの言葉は届かないものだ。
・コンプレックスがある人間は、そのコンプレックスに「気づかれた」と、そしてコンプレクスが理由で他者が自分をこう扱うのだと思いやすいということでもある。自分が気にすればするほどに。
人の心を察する「心の理論」のシステムはまだ未判明だが、いくつか仮説が有る。今回の話はそのうちのシミュレート仮説が近い。
[blogcard url=”https://embryo-nemo.com/1199″]
他人のリアクションからの推論
・相手が自分をどう評しているかは、自分に向けられた言動から推測することになる。
人間は元から表情を始めとした「非言語的なメッセージ」や、「沈黙」「無反応」までも自分へのフィードバックとして得ている。これらはそのまま深読みしすぎる余地にもなる。
例えばプライドが高ければ、最初から気づいていないだけのことを「無視された」と捉えたりとウザいことにもなりかねない。
・要するに、自分がどう思われているか極度に気にする人間は、他人の言動が「自分に向けられた」「自分に対して行ったもの」に見えるということでもある。スポットライト効果の例のように、この時点で間違っている可能性もある。
また、一部の精神病んだ者はかなりこの傾向がある。そのような病の症状としても存在する。
・そして「自分が予測していること」に帰属させやすいだろう。
自信がある部分、気にしている部分に注目が集まっていると感じ、他人はそれに対してリアクションをしていると感じやすいという話。
結果をどう捉えるかは目的に依る
・実験として、称賛獲得欲求が高い人と拒否回避欲求が高い人それぞれに「集団に於いて自分が意見を示し、周囲がそれに賛同するパターン、否定的なパターンのシナリオ」を読ませ、感情を尺度で測るというものがある。
要はなんか発表させて、賛同されたり否定された時の感情の質を見る。
1997年11月、346名、平均年齢19.45歳。
・否定されるシナリオに対して、賞賛獲得欲求が高い人は怒りや恥の感情が高くなった。
怒りの感情としては「悔しい」「許せない」「頭にくる」「バカバカしい」「腹立たしい」の5つ、つまり怒りの項目全部と相関があった。
恥の感情としては「体裁が悪い」「バツが悪い」という項目に相関があった。
これは彼/彼女たちにとって、否定されることは目的外=予想外の出来事であり、自分の行動よりも、評価をした他者や状況にその原因が帰属されると考えられている。つまり自分が失敗すると思ってない。
「予想外の結果になったんだから自分以外の何かのせいだろう」みたいに考える。
この「自分以外」は他人だけじゃなく、(帰属理論によれば)タイミングだったり運だったりもあるだろう。必ずしも性格が悪いわけでもない。
しかし翻ってみれば、よく人のせいにする奴は自信過剰な目立ちたがりが多いな。
・一方拒否回避欲求が高いと逆なのかと言うと、別にそういうこともない。
こちらは恥、怒り、照れと相関があった。
どの道意見を否定されたら怒りと恥が沸き起こるのがデフォということでいいだろう。
ただしこちらは特に恥の感情が強かったとされる。
こちらの場合は彼/彼女たちは最初から恥をかかないことが目的だった。
このためそれに「失敗」したのだから恥を感じるのだと考えられている。
・肯定的なシナリオの場合、賞賛獲得欲求と満足感に正の相関があり、恥とは負の相関があった。
劣等感が強い者が「一発逆転」を狙いがちなのも、人の目を気にした成れの果てかもしれない。
拒否回避欲求が高い場合、肯定されるシナリオでは満足感と照れの感情が高かった。こちらはどちらにせよシャイだね。ただ当人が照れを恥だと捉えているとしたら、インポスター症候群のように目立ちたくない、成功したくないという心理に繋がりそうに思える。
人の目が気になることの対処法
人の目を気にすることは別に悪いことではない、というか、社会的アニマルであるヒューマンにはむしろ必須な能力と言える。無けりゃ空気読めない=協調性ゼロとなる。
問題となるのは、人の目を「気にしすぎる」ことであり、その分「自分でない」時間が長くなること。
気にしないでいられるか
・ベタな解答としては「気にしなきゃいい」だが、「できたら苦労しない」の大合唱になるな。
精神の埒外にあるものはわが精神に対しては無である。そのことを学び取れ。さすればおまえは真っ直ぐに立つ。
マルクス・アウレリウスは皇帝なんだが、「皇帝化されぬように」なんて自分に向けて書いてあったりもする。
他人の目や期待に応えすぎて自分を見失わないように、みたいな意味とも取れる。皇帝なのに。皇帝だからこそかも知れないが。
自省録は彼の「自分への言い聞かせ」に近い。誰かに向けて書いたものではない。つまりは常々意識していないと飲まれるくらいには人に纏わり付く問題では有るだろう。
・気にしないこと自体は不可能でもないんだが、できたらできたでイカれたことになる余地もあるので、よろしくない。
そもそも人の目を気にすることが不要かと言えばそうでもなく、なきゃないで困るだろう。
問題なのは人の目を「気にしすぎること」だ。不要なところで気になったり、気にしすぎて過剰な行動をとったり。
この問題の寛解は、人の目を気にすることの「コントロール」によって果たされる。
気にする内容を吟味する
・「人の目」の問題とは、個人と社会の関係性の問題に近い。「期待」あるいは失望や軽蔑への「恐れ」、具体的にそれを与える余地があるのは確かに他者・社会ではある。
その分、不当だったらぶん殴る必要もあるんだが、それどころか自分からそれらを想像して、プロクルステスの寝台のように自らを引き伸ばし、あるいは切り落とすような面が人にあることは間違いない。
クソクレーマーに対してとりあえず謝る企業とか思い浮かべればいいだろう。なお、クレームとクソクレームの違いは判別できるよう心するべきだ。
・犬が他人に無駄に吠えたり噛んだりしないようになることを「社会化」なんて呼んだりするんだが、人は自らを社会化しようとしている部分がある。
人類の様を指して「自己家畜化」なんて呼ぶこともあり、結構根が深い。
ともかく、社会化自体は結構だが、なおさら内容には気をつけたほうが良いだろう。
要するに大抵の人間は「社会」のツラした意見にかなり弱い。これは操作や扇動に頻繁に悪用される。
気にする内容を吟味しないと、卑怯者の小細工にだいぶ振り回されることになる。
逆に内容を吟味すれば、ストレスそのものが減る。
誰からも好かれることは不可能だと知る
・これも吟味・選別の話となる。
・好かれると言うか、誰からも「嫌われない」ことからして無理。
人間は、表面上のものを見て、他人の内面やその行動の経緯を推測する、ってスタイルの認知をする。
で、認知バイアスの話でもそうだが、とにかくやたらと推測し、なおかつ出来が悪い事が多い。この上で確信を持つというめんどくさい所がある。
例えば前後即因果の誤謬。さっきAを見た後で現象Bが起きた、Aが原因に違いないと思いこむ、なんてわかりやすい酷さがあるだろう。天然で冤罪発生機な所がある。
つまるところ、何をどう気をつけた所で勘違いするやつは出てくるし、それに「確信」をもつからそれ以上知ろうとはしない傾向がある。
イデオロギーや好き嫌いの問題も出てくるしで、人類全部がお気に召す人柄・振る舞いってのは不可能だ。
・反対に気が楽になった、主観的幸福度が上がったなんて言われるのが「人の目を気にすることをやめる」というのであったりして。
もちろんこれは「今まで気にしすぎていた人々」に向けての話だ。「おまえはもうちょっと人の目を気にしろ」というのも普通にいる。
身だしなみ
・非言語的な要素、例えば身だしなみや仕草、振る舞いなどは気を使ったほうが良いと言える。
このような「見ればわかる」部分は、自身も「自分はこう見られているだろう」と考る材料になる。
実際先程の実験では、ダサT着てただけで過敏型自己愛みたいになってたわけだし。
ゆうても必要なのは孔雀のような方向じゃなくて、清潔感だろうね。
SNSをやめる
・結局の所、大きく見せようとするでも、避けようとするでも、人の目を気にする心理として劣等感の存在は大きい。だから人の目に対して誇張して想像上の低評価を払拭しようとするか(これは等身大の自分を隠すため実際には評価を避けている)、人の目そのものを避けて評価されることを避けようとするか。
まぁ事の大小を問わないなら誰もがやっていることだ。
「評価」というのも語弊があるか。自称批評家の頭がおかしいのも世の中には確かにいる(注)が、実際の所、懸念しているのは「他人が自分を見た感想」って言い方のほうが近いかも知れない。
注(アレも一発逆転狙いの例で、自分が評価される側になりたくないのが動機なことが多い)
この「他人の感想」を推論する材料の一つが「世間の相場」であり、ここでSNSと話がつながる。
・先に言っておくと、仲間内の連絡程度の使い方ならSNS使用に問題はないらしい。
ただし受動的に、なんとなく長い時間眺めているようだと、幸福度が下がっていたそうな。フェイスブックの話な。
フェイスブックをやめたグループは、幸福感と生活の満足度が上がり、抑うつと不安が減少した。その効果は人によって違うが、だいたい約25〜40%ぐらいだった
理由が、他人の「お見せできる自分」しか流れてこねぇようなもん見続けてる(世間の相場」が脳内で不当に上昇する)&等身大の自分と比べるもんでほぼ自己評価が下がる。
で、自己評価が下がれば人の目は気になり始める。「見られたくない」と思うから。自分のこと「見せられない自分」と思ってるようなもんだし。
元々が、自分が幸福かどうかすら自分でわからない者も多い、とも言える。
・こちらではソースが確認できなかった話なのだが。
ブータン王国ってのがある。ちょっと前まで信号もなかったそうな。
その国が、国民の幸福度が世界一だったことがある。今はそうじゃない。
なぜ幸福度が落ちたのかというと、ネットとかで外の世界の暮らしぶりを知ってしまったから、という話を見かけたことが有る。
ブータン王国は確かに貧しい国って印象を受けるが、主観的幸福度とそれはまた別の話だった。この話の通りの原因なら、「比較対象」が目に入ってしまうと、満ち足りていたはずの人も比べてしまうということになる。
・類似した話で、ゲームを一つ作り上げた人の記事がある。
ただの大学生が自作ゲームを1本作るまでに経験した数々の地獄のお話
もうタイトルからして「地獄」なんだが、辛いなりに最後の方は楽しくなってきたそうで。
その段階でもしんどかったことの一つとして挙げられているのが、「Twitterの化け物開発者からくる劣等感」となっている。
もうどの世界でもですね。絵師さんの世界とかよく聞きますよね。本当に凄い人は凄いです。見ない方が良いです。Qiita書いてる人も天才です。彼らは人生5周目くらいです。感謝して1周目の私たちに教えてもらいましょう。
単純に比較して凹むよか、こうやって割り切って、学べる所は学ぶくらいの気持ちのほうがメンタルによろしかろう。前向きだし。
参照サイト
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpjspp/11/2/11\_KJ00002442204/\_article/-char/ja/
https://kagaku-jiten.com/social-psychology/individual/self-presentation.html